
1996年(平成8年)にSANKYOから登場した時短デジパチ「フィーバーアラビアンDX」
(メタリックで次世代感タップリの「FF枠」)
★現金機(デジパチ)、ドラム機
★賞球…7&15
★大当り確率…1/227
★大当り図柄…赤7、魔女、王冠、Fever(F)、宝石、ランプ、青7、壺、女王の9種類
★ドラム停止順…左→右→中 (但し、中・右同時回転リーチ、全回転リーチあり)
★有効ライン…5ライン(計45通り)
★最高16ラウンド継続
★出玉…約2300個
★時短機能を搭載
・「赤7、青7、F」の3図柄で当ると、大当り後、100回転の時短モードに突入
・時短突入率=1/3
・時短中の連チャン率=35.7%
・時短大当り後、100回まわすと通常モードに戻る(「次回大当りまで継続」ではない)
★小デジタル確率…通常時、時短中ともに「1/3」
・小デジタルは盤面左下、半円(C字型)のLEDランプ。1~6のうち、1と2で当選)
・小デジ用チャッカーは、メインアタッカー左下にひっそりと存在。メモリーの有無はドラム左右の赤丸ランプで把握できるが、点灯数までは判らない。
★小デジ変動時間…通常時=約30秒、時短中=約3秒/7秒(小デジのメモリー状況で変化)
★電チュー開放時間…通常時=0.5秒×1回 時短中=1.5秒×2回
(電チューはヘソについていた。性能(拾い)は良い)
★実戦店…登戸「ハトヤ」、新百合ヶ丘「ダイヤモンド」、新宿「日拓1号店」、高田馬場「日拓本店」、有楽町「UNO」、赤坂「エスパス日拓・赤坂A館」、神楽坂「神楽坂センター」など多数(設置率高し)
★CR版の兄弟機…「CRスーパーアラビアンクイーン(CRFアラビアンGP)」
1997年3月登場。大当り確率=1/251。1/2で確変突入。5回のリミッター付き(新基準機)。
爆発力はフルスペックに劣るが、その分、CRにしては確率が甘い。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
別名を「スーパーアラビアンクイーン」というように、かつての大ヒット機種「フィーバークイーンII」(1993年、保留連チャン機)の後続機として本機がお目見えしたのが、1996年の12月。
但し、クイーンをそのまま踏襲した訳ではなく、文字通り、「アラブ」のエッセンスを振りかけた、独特の仕上がり具合になっていた。
ドラム回転音やリーチ音もアラブ調だったが、元祖クイーンの「面影」も感じられた。
図柄もクイーン同様、「赤7」「青7」があった。その他、クレオパトラの「女王」(元祖クイーンにもトランプの「女王」図柄があった)、空飛ぶ絨毯に乗った踊り子風の「魔女」、羽根付きの「王冠」など、アラビックな図柄が多数。
「赤7」→時短
「青7」→時短
「F(Fever)」→時短
「女王」…単発
「魔女」…単発
「宝石」…単発
「王冠」…単発
「壺」…単発
※その他、単発図柄の「ランプ」も存在。
4種類のリーチ、右ドラムのスベリ、そして大当りの期待をあおる「予告フラッシュ」と、打ち手を魅了する要素は満載。まさに、「ドラムの三共」らしく、完成度の高い演出だった。
低確率のフルスペックCR機が幅を利かせた当時、1/227という良心的な確率も嬉しかった。
(この直後、CR機も爆裂度を抑えた確変リミッター付きの「新基準機」が登場)
クイーン的な仕込み連チャンこそないが、出玉を減らさずに時短中に再度大当りする、「疑似連チャン」が十分期待できた(時短連チャン率は35.7%)。
但し、時短モードは、時短図柄の大当り後100回で終了。次回当りが約束されたスペックではないが、時短ループ、単発後の(自力)数珠連チャン、時短終了直後の引き戻しなど、出玉を大きく伸ばす要素も多かった。
本機を「マイルドな出方※」と呼ぶ人も多かったが、私はそう思わない。「1/227」の確率が織りなす好調時の出玉の「波」があり、ヘソが甘ければ、時短と早い初当りを絡めて、一気に箱を積む力も持っていた。その一方、大ハマリが少ないのが大きな魅力といえた。
※「爆発力がない」といった印象を持つ人は、実戦店の釘が露骨にシブかったのではないか。事実、新装から警戒して釘をシメる店もあったし、時短中に玉減りする酷い調整の時もあった。
なお、当時は、「射幸性」を煽る営業を自粛する空気もあり、「3箱規制」といった自主規制で、積んだドル箱を途中でカウンターに流させるホールもあった。
「射幸性」といえば、この時期は、かつてホールを賑わした連チャン機に「社会的不適合機」の烙印を押して、撤去するような動きも目立った。店に大きな恩恵をもたらした「恩人」に対して、掌を返したような酷い仕打ち。一般ファンにとっては、何とも理解しがたい流れであった。
まぁ、そんな背景があったからこそ、本機のような「疑似連チャン機(時短連チャン機)」を、ホールも重宝したのだろう。本機は、当時の現金機の中において、かなりのヒットを飛ばした。都内・神奈川でも、新装で次々と導入されて、97年の代表機種となる可能性も存分にあった。
ただ惜しむらくは、本機のヒットとピッタリ重なるタイミングで、元祖クイーンIIの正統後継機、「フィーバークイーンJX」(1997年)がリリースされた事だ(CR版は「CRFクイーンJX」)。
コチラは、ハッキリと初代クイーンIIを「踏襲」したリメイク版で(現金機は1/4で次回まで小デジ確変、CRは1/2で確変・5回リミッター付き)、97年中盤から下半期に、大きな注目を集めた。これが、本機の存在感・注目度を、薄めてしまった感が否めない。
★右ドラムの「スベリ」について
ドラム停止順は、基本「左→右→中」だが、右ドラムが一旦停止した後、再び動く事があった。これが右ドラムの「スベリ」で、アクション発生時はリーチ及び大当りの期待度がアップ。
スベリのパターンは、「7コマスベリ」「8コマスベリ」「9コマスベリ」の3つ。大抵は7コマか8コマのスベリだが、稀に9コマスベる事があった。
(参考)右ドラムのスベリコマ数、振り分け率
・ハズレリーチで「右スベリあり」が選択されると、必ず「7コマスベリ」となる。
・大当りで「右スベリあり」が選択されると、7コマスベリが6/7、9コマスベリが1/7。
・右が左に対して+1コマでハズれる時(非リーチ)は、スベらずが4/7、8コマスベリが3/7。
7コマスベリは必ずリーチが掛かるが、単なるハズレリーチも多い。
(但し、スベリ無しよりも期待度はアップ)
8コマスベリは、左ドラムに対して、右が「+1コマズレ」で止まる為、絶対リーチにならない。
9コマスベリは必ず大当りする。だが、振り分け率はそれなりに低く、頻繁に出た訳ではない。
しかし、右が一旦停止してスベった時、「普段より余計にスベッたな」と思ってリーチになれば、感覚的に「大当り」と判断できた。普段はスベッて上段にテンパイする図柄が、下段までスベって来た時など。
また、左の停止図柄に応じて、右の「一旦停止図柄」もセットになっていたから、これさえ頭に入れておけば、7コマと9コマの違いを見分ける事も出来た。
ただ、スベリは割と素早く起こったので、対応図柄を瞬時に判断しかねるケースもあった。
そこで、7コマと9コマの違いを見分ける為、スベる前後の右ドラムの挙動に着目する、以下の判別方法もあった(あまり知られていないが)。以下、図説を加える。
まず、左ドラムの中段に、何らかの図柄(大当り図柄のみ、ブランクを除く)が止まった場合。
(「ブランク・図柄・ブランク」が止まるケース)
ここから右が7コマスベる時は、やはり「中段」に何らかの図柄が一旦停止する。直後に7コマスベリが発生して、左中段と同じ図柄が右「中段」に再停止して、リーチとなる。例外はない。
つまり、「ブランク・図柄・ブランク」が一旦停止して、「ブランク・図柄・ブランク」が再停止する。右中段の図柄は入れ替わるが、「図柄が中段停止」そのものは変わらない。
一方、9コマスベる時は、「ブランク・図柄・ブランク」→「ブランク・図柄・ブランク」のパターン以外に、「ブランク・ブランク・図柄」(下段)で一旦停止してから、「ブランク・図柄・ブランク」(中段)で再停止するケースが生じる。
即ち、下段で一旦停止後、中段で再停止するパターンだ。この「変則パターン」が起きれば、「9コマスベリ確定」で必ず大当りする。
したがって、左中段に図柄が止まった時、右ドラムの下段で図柄が一旦停止後、スベリが発生した時点で、大当りを確信してよい。左右の図柄が何であれ、「変則スベリ」さえ知っていれば、ある程度は大当りの「先読み」が可能だった。
(右スベリが発生した瞬間、大当りと判る)
次に、左ドラム「上段and/or下段」に、何らかの図柄(ブランク除く)が止まった場合。
まず、左の停止形を大別すると、上下共に図柄がある場合(W図柄)」と、「上段単独図柄」、「下段単独図柄」の、3パターンに分かれる(配列上、必ずそうなる)。
・W図柄…「図柄・ブランク・図柄」
・上段単独図柄…「図柄・ブランク・ブランク」
・下段単独図柄…「ブランク・ブランク・図柄」
ここから右が7コマスベる時は、(i)W図柄が一旦停止後、別のW図柄で再停止(リーチ)、(ii)上段単独図柄が一旦停止後、別の上段単独図柄が再停止(リーチ)、(iii)下段単独図柄が一旦停止後、別の下段単独図柄が再停止(リーチ)、の3パターンとなる。例外はない。
特徴的なのは、右スベリが起きる前後の停止形が、必ず「同じ」である点だ。
(W図柄→W図柄、上段単独→上段単独、下段単独→下段単独)
一方、9コマスベリは、「W図柄→W図柄」に加えて、「W図柄→下段単独」「上段単独→W図柄」「中段→上段単独」という、4つの変則パターンがある。なぜ「変則」かといえば、7コマスベリと違って、スベリの前後で右の停止形が「変化する」からだ。
よって、コチラも変則スベリと判った瞬間、大当りを確信できる。このうち、「W図柄→下段単独」と「上段単独→W図柄」の2パターンは、右が再停止してリーチが掛かった時点で判別可。残る「中段→上段単独」はもっと早く、右スベリが起きた瞬間、大当りする事が判る。なぜなら、左の上/下段に図柄がある時は、7コマスベリなら、絶対に中段には一旦停止しないから。
以上が、右スベリ発生時における、お手軽な「大当り先読み」(9コマスベリ判別法)である。
左の停止形に応じてパターンが幾つかあるが、法則自体は単純。実機をお持ちの方は、検証してみるのもいいだろう。
★リーチアクション(4種類)について
・ノーマルリーチ(中ドラム再始動は鉄板)
中ドラムがややスローで1周回った後、2周目のリーチ図柄を通過後、超スローに切り替わる。
徐々に低音→高音に変わるアラブ風リーチ音が、元祖クイーンのジリジリ感を彷彿とさせた。
但し、ノーマルのままでは滅多に当らない。元祖クイーンは、この「ジリジリ」リーチから当たるのが醍醐味だったが、本機では低信頼度のリーチに「格下げ」となった格好だ。
但し、「滅多に当らない」とはいえ、ノーマルで当る事もたまにある。解析によれば、初当り時の約17回に1回が、ノーマルで当る。
なお、中ドラムが一旦ハズれた後、再始動すれば、必ず大当りする(三共得意の「二段階」)。
但し、ノーマルの再始動アクションは、通常時と時短中とで異なる。通常時は、「1コマスベリ」「7コマスベリ」「19コマスベリ(約1周)」「1コマスベリ」の4パターン。時短中は「19コマスベリ」「23コマスベリ」のロング再始動のみ発生。
・不思議なリーチ(中ドラム再始動は鉄板)
ノーマルから発展するSPリーチ。ノーマルが超スローに切り替わって1周した後、さらに2コマ進んだ時点で、左右ドラムがガクガクと揺れ始める。
1周以内で止まる「ショート」と、2周目に突入する「ロング」があって、ロングの方が高信頼度。特に、右7コマスベリからのロングは、信頼度約6割と激アツ。
中ドラムの再始動パターンは、「1コマスベリ」「7コマスベリ」「1コマ戻り」の3つ。
・さまようリーチ(中ドラム再始動は無し)
左ドラム停止後、中・右の図柄が揃った状態でスクロールを開始。しばらく回りっぱなしの後、「一旦停止→回転」を繰り返すようになる。
左の停止図柄が1つだけなら、シングルリーチ確定。一方、左の上&下段に図柄が停止した「W図柄」の場合、中・右が斜めに揃っていればシングルだが、平行揃いで回っていると、ダブルリーチとなる。
そして嬉しい事に、ダブルリーチ型の「さまようリーチ」は、大当たり確定。さらに、ダブルリーチ時は必ず一方が時短図柄なので、1/2で時短図柄での大当りが期待できる。
なお、4種類あるリーチの中で唯一、中ドラムの再始動アクションが無い。
・魔法のリーチ(中ドラム再始動は鉄板)
ドラム回転中に突如サウンドが激しく変わり、全ドラムが高速回転後、図柄が揃って一旦停止→同時回転→中ドラム1コマズレで停止→同時回転と派手に動く。最後に図柄が揃って止まれば大当りとなる。但し、「揃った」と思った直後に、中ドラムが1コマ落ちてハズれる事もある。
中ドラムの再始動は、「1コマ戻り」と「19コマ(約1周)スベリ」の2パターン。
さらに、時短図柄(赤7、青7、F)で魔法のリーチが掛かれば、100%大当りする。高速回転後、一旦揃った図柄が時短図柄であれば、その時点でドル箱を用意してよい。
★予告フラッシュ(前兆)について
ドラムが始動する直前、「ピピピピピピ!」とけたたましい音と共に、ドラム周りの飾りランプが一瞬激しく点滅することがある。これが連続するのが、本機の大きな特徴の一つである、「予告フラッシュ」だ。
最低2連、最高で4連続するフラッシュの出現で、大当り期待度も大きくアップした。但し、「ガセフラッシュ」も存在したので、最後まで気が抜けなかったのも事実。
フラッシュ発生の前提条件は、「時短中でない事」、「保1でガセフラッシュ発生がしない事」。
保1にガセフラッシュが残ったまま、新たなフラッシュ抽選が行われる事はない。よって、フラッシュは最高4連続まで。
上記条件が揃った状態で、始動チャッカーに入賞。この時、「保2以上が点灯している事」も、フラッシュ発生の必須条件となる。よって、フラッシュは最低でも2連する。
この時に入賞した玉で「大当り乱数」を引けば、「8/23」でフラッシュ抽選を行う。当選すると、それまで点灯していた全保留でフラッシュ予告を発生させる、内部処理を行う。
フラッシュには、「ピピピピピピ」と短めの予告音が鳴る「ショートフラッシュ」と、「ピピピピピピピピピピ」と予告音が僅かに長い「ロングフラッシュ」がある。
大当り時の連続フラッシュは、「ショート」からのハズレ(ハズレリーチも含む)が何度か続いた後、対象となる最後の保留消化時に「ロング」が発生して、必ず大当りする。
但し、同じ条件下で「ハズレ乱数」(ハズレリーチ含む)を引いた時も、「1/683」のガセ抽選に当ってしまうと、同様の処理が行われて、全く嬉しくない「ガセフラッシュ」が起こる。この場合、発生する連続フラッシュは、全て「ショート」になる。もちろん、対象となる最後の保留消化時も、ショートとなってしまう訳だ。
つまり、ショートフラッシュは必ずハズレとなり、ロングフラッシュなら必ず当たる。
予告音の長さのちょっとした違いだが、よく観察すれば見逃す事もなかった。フラッシュがロングだと判って瞬間に安心できる。一方、4連目のフラッシュがショートだった場合、「ガセ確定」となる。
★通常時のドラムの「即止まり」現象について
本機は、各ドラムが停止する際、通常は「ダーン(間)、ダーン(間)、ダーン」と、一定の間隔がある。
しかし、時折「ダン、ダン、ダン」と素早くドラムが停止して、「即止まり」アクションを見せる事があった。
なお、時短中は、ドラム変動時間の短縮で即止まりするケースが頻発するが、ここでの即止まりは「通常時」に限る。
この即止まりが当初は怪しく感じられて、「大当りの前兆」とか、「特定の形で即止まりすれば、次回転で大当りする(リーチ目)」など、色々と物議をかもした事もある。
即止まりのパターンには、(1)単なるハズレ停止、(2)リーチが掛かってハズれる、(3)リーチが掛かって大当り、の3パターンがあり、即止まりの大当り信頼度も気になったりした。
しかし実際には、単なる「演出」の一環として、用意されたものに過ぎなかった。
即止まりは、大当り時の1/5、ハズレリーチ時の1/10、バラケ目ハズレ時の1/30で発生。
したがって、リーチが掛かれば多少は期待できたが、単なるハズレ(バラケ目)でも、ランダムで発生する仕様だった。結局、前兆やリーチ目とは、何の関係もなかった訳だ。
フィーバーアラビアンDX(SANKYO、デジパチ)
阿藤快さん、逝く…
俳優、阿藤快(本名・公一)さんが、今月14日、都内の自宅で病死された。
死因は、「大動脈破裂・胸腔(きょうくう)内出血」とのこと。
偶然にも、11月14日は阿藤さんの69回目の誕生日だった。
つい最近まで、TVで拝見する機会も多かった阿藤さん。事実、亡くなる直前まで、舞台や映画の仕事を精力的に行っていたという。
ただ、背中の痛みなど、体調の悪さを漏らす事もあったとか。
名優の突然の逝去に際し、驚きと共に、深い悲しみを禁じ得ない。
阿藤さんは、数々のTVドラマや映画で、記憶に残る「バイプレイヤー」として知られた。かつての人気ドラマでは、武田鉄矢「金八先生」の強面ヤクザ役などが有名。その後も、田原俊彦「教師びんびん物語シリーズ」の教頭(御前崎=「教師びんびんI」)や同僚教師(長曽我部=「教師びんびんII」)、中山秀征「静かなるドン」の世話役・猪首硬四郎などを好演。「強面で、ちょっとコミカルな人情家」を演じさせれば、見事にハマった。体や顔も大きかったが、それ以上に大きな存在感を見せた。
また、テレビ東京の「いい旅・夢気分」や、日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」といった、数々の旅番組にも出演。自然体で、誰とでもざっくばらんに接する阿藤さんの優しい人柄が、画面からジンワリと滲み出ていた。まさに、「旅人・阿藤快」は、阿藤さんのライフワークだった。さらに、グルメリポートなどにも定評があった。口癖の「何だかなぁ~」が、お茶の間を和ませた。
ところで、阿藤さんといえば、90年代、「パチンコ好き芸能人」の代名詞的な存在でもあった。
年末・年始の特番で「芸能人パチンコ大会」があると、ちょくちょく阿藤さんは顔を出していた。
また、90年代は、ゴールデンタイムに「パチンコ特集」をOAする事が多く、そういった特番で、現地のホールに出向いて、リポーターを務めたりもした。
もちろん90年代は、プライベートでパチンコに興じる事も多かったと聞く。 (C)テレビ東京
(C)テレビ東京
コチラは、1996年(平成9年)OA「TVチャンピオン・史上最強パチプロ王選手権II」(テレビ東京)で、スタジオゲストとして出演した時(この大会では、大崎一万発氏が優勝)。
「パチンコといえばこの方」のテロップが、阿藤さんとパチンコの繋がりを、如実に物語る。
そして、この番組が放映されたのが、何を隠そう、「1996年11月14日(木)」であった。
当時、人気のパチンコ企画に、記念すべき「誕生日のゲスト出演」を果たした日から数えて、ちょうど19年後の同じ日、名優・阿藤快は旅立ったのだ。何という偶然であろうか。
ただ、見方を変えれば、パチンコも「偶然の産物」。そんなパチンコをこよなく愛した、阿藤さんらしい「偶然の一致」ともいえる。
この時期、芸能界の「パチンコ好き」といえば、中村玉緒さん、蛭子能収さん、そして阿藤さんといった方々の顔が、真っ先に脳裏に浮かんだ。歌手の和田アキ子さんも、「芸能界のパチンコファン」の代表格として知られた。「いいとも青年隊」出身の久保田篤氏も、「マンション久保田」の呼び名で知られる、芸能界随一の凄腕パチンカーであった。
余談だが、パチンコと同様、阿藤さんは「競馬」も大いに好んだ(近年は、「競馬愛好家」のイメージの方が、むしろ強かった)。
なお、このOA当時は旧名「阿藤海」の名義だが、2001年に「阿藤快」と改名。改名を行った日も、やはり誕生日(そして命日)の11月14日である。
件の「TVチャンピオン」にゲスト出演した阿藤さんは、パチンコの「魅力」について、「僕は、(好きになった)台に凝るんです。台に向かって集中して、人生のように、苦労して、苦労して、フィーバーが来た時の、喜びと爽快感。『行ったー!』みたいな。騒音の中で戦うのもいいですよ。」と発言している。
この放映回では、大同の一発タイプ普通機「ミサイル7-7-6D」を使った「出玉勝負」もあった。ただ、クルーンにねじ込んだ玉が、奥のハズレ穴ばかりに落ちて、何ともイライラする展開に。そんな様子を見た阿藤さんが、思わず「僕は、ああいうのは嫌いです」と呟いたのが印象深い。振り分けタイプのアナログな権利物タイプより、「図柄が揃えば大当り」の、シンプルなデジパチタイプを好んだ事が窺える。
それを裏付けるように、阿藤さんは、TVチャンピオン放映の2か月前、97年9月に同じテレ東でOAされた「パチンコスタジアム」(司会は、コチラもパチンコ好きで知られた斉木しげる)にもゲストで出演。勝負台のSANKYO「CRフィーバークイーンJX」(1/2確変、5回リミッター付き)を、斉木さんと肩を並べて楽しそうに打っていた。
(ロケ地は千葉市美浜区「みはま会館」→現「メガサイバー美浜店」) (C)テレビ東京
(C)テレビ東京
「TVチャンピオン・史上最強パチプロ王選手権II」。スタジオに訪れたSPゲストのスエイさん(末井昭氏、「ゴンゾーロ末井」として大会に出場。「ミサイル」対決では、最初の一発で手前穴に入れて、見事に勝ち抜けた)と、和やかにトークを行う阿藤さん達。
(右端は番組MCの田中義剛。その隣は、女性MCの松本明子)。
このシーンでは、当時話題となった爆裂CR機「CR大工の源さん」の「源さん・目尻攻略法」の噂で盛り上がった。
これは、「液晶にいる源さんの顔の、向って右の目尻が太いと設定1、左右が同じなら設定2、左が太いと設定3」といった怪しげな噂が、一部で出回った事を受けたものだ。
ネタの真偽について訊かれたスエイさんは、「噂ですから、何とも言えません。信じたい人は、信じればいいと思います」とお茶を濁しつつも、「私は信じません」とキッパリ断言。阿藤さんやスタジオの笑いを誘った。
言うまでもなく、設定判別可能な「眉毛攻略法」など、存在するハズもない。目尻や黒目の形、背景の壁の継ぎ目など、液晶の一部が台毎に微妙に異なる現象は確かにあった、だが、それを「設定判別」と結び付けるのは、やはり短絡的であり、「オカルト」と言わざるを得ない。
そんな訳で、「名脇役」「旅人」として世に知られた阿藤さんだが、私にとっては、「90年代・パチンコ愛好家」としての側面も、強く印象に残っているのだ。
今まで、長い間、我々視聴者を楽しませて下さり、有難うございました。そして、本当にお疲れ様でした。どうか、ごゆっくりお休み下さい。
阿藤快さん逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。
アクティブ(平和、デジパチ)

1990年(平成2年)に平和から登場した、オマケチャッカー付きデジパチ「アクティブ」。
★旧要件機
★賞球…7&13
★大当り確率…1/270
★最高10ラウンド継続
★出玉…2000~3000個(オマケチャッカーのクギで変動)
赤・緑・黄の大きな7セグ(2ケタ)と、外周のルーレットを組み合わせた、独特なデジタル構造が印象に残る。90年暮れ~91年春に、JR巣鴨駅前の「三益球殿」(閉店)などで打った事がある。
この時期、平和の2ケタデジタルというと、ちょうど、デジタル一発台の「サイクロン」が人気を博していた頃だ(他社では、マルホンのデジパチ「レインボー」も、2ケタデジタル採用)。
本機も、サイクロンを彷彿とさせるデジタルだが、7セグが赤一色だったサイクロンと違って、「赤・緑・黄」の3色デジタルが特徴。それを、緑と赤の「ルーレットランプ」が、グルリと取り囲む。
まず、中央の2ケタデジタルが、派手な音と共に「左→右」の順で止まった後、高速で時計回転を続けるルーレットランプが停止する。
ルーレットは細かく20分割されているが、数字や文字の表記はない。また、ランプは基本的に「緑」で、「3時」と「9時」の当り位置のみ「赤」ランプとなっている(2ヶ所の当り位置には、「ATARI」の表記)。
当時、「数字とルーレット」の組合せでヒットを飾ったのが、三共「フィーバーボルテックスII」。2ケタドットと円盤型ルーレット(数字入り)を採用。強力な保留連チャンも魅力だった。図柄が揃った直後、ドットにメッセージが流れる「5.6秒」(チャンスタイム)にチャッカー入賞させれば、点灯した保留玉が約1/2で連チャンした。
ただ、ボルテックスは、先に外の「ルーレット」が止まり、次に、内側の「デジタル」が停止する。ルーレットと左デジタルが同数字でリーチ、最後に右デジがスロー回転した訳だ。
その為、「折角なら、最後にルーレットが止まる方が面白かった」との批判もあった。
私自身は、リーチが掛かり、右デジが停止直前、スローから「超スロー」に切り替わる一瞬を、むしろ「アツイ」と感じた方だが…。
それはともかく、本機はボルテックスと違って、ルーレットが「一番最後」に止まる構造だった。ルーレットの「視覚効果」がいっそう強調されて、大当りへの期待感を煽った。
なお、本機と同時期に出た、西陣の旧要件デジパチ「スーパールーレット」も、やはり7セグとルーレットを組み合わせた、特徴的なデジタルだった。但し、コチラは中央が1ケタデジタルで、その周りをルーレットが二重に取り囲む。中央デジタル→外側ルーレット→内側ルーレットと停止。さらに、内ルーレットは、赤と緑のランプが交互点滅。内ルーレットがリーチ図柄の位置で停止しても、赤ランプが点灯していないと「ハズレ」となる。
本機は、中央の2ケタデジタルに、赤か緑のゾロ目が出れば、リーチ発生。図柄は数字のみ、赤・緑ともに「0~9」の10通り。つまり、赤も緑も「00~99」のゾロ目でリーチ。リーチパターンは20通り。
赤、緑の図柄が10個づつ(左右ともに20×20)、リーチパターンが20通りだと、リーチ発生率は単純に「1/20」(20/400)となりそうだが、実際は違う。デジタルには、赤と緑の他に「黄色」の数字もあって、黄色は単なる「ハズレ図柄」にすぎない。その為、リーチ確率は「1/27」と少々低めで、なかなか同色ゾロ目にはならない。その分、リーチ時の期待感は大きいが…。
リーチが掛かると、けたたましい効果音と共に、外周ルーレットが速度を落として、時計方向に回転する。この時、ランプは対角の2ヶ所が同時に点灯して、風車の如くクルクル回り続ける。
最終的に、「3時」と「9時」の位置(赤ランプ)でルーレットが止まれば、大当り(2ヶ所が同時に点灯して当る)。先述の通り、当りの位置には、実に判り易く、「ATARI」とローマ字で表記してある(ビデオゲーム機の「ATARI」を思わせた)。
大当り確率は、手元に詳細な解析資料がなく、正確な数値は不明。ただ、当時の攻略誌は、大半が「1/270」としており、当ブログもこの説をとる(「1/256」説もアリ)。
なお、表面上の大当り確率を計算すると、ハズレ図柄も含めた出目パターンが「540通り」あり、リーチの組合せ(赤のゾロ目、緑のゾロ目)は「20通り」。さらに、ルーレットが「ATARI」に止まる確率は「2/20(=1/10)」。よって、表面上の確率は、20/540×1/10=「1/270」となる。
当時は、表面上と内部の確率が同じ台が、少なくなかった(出目カウンターが大当りカウンターを兼ねる場合もあった)。
平和のデジパチも、本機と同じく’90年登場の「舞羅望極II」※「ブラボーセンチュリー」「グリース」は、いずれも「表面確率=内部確率」だった。おそらく、本機の内部確率も、表面上と同じ1/270と思われる。但し、当時としては「辛い」数値なので、今後も調査を続ける。
※舞羅望極IIの確率は、表面上が「1/243」、内部が「1/242.5」と、僅かなズレがある。
大当りすると、盤面下部のメインアタッカーが開放。アタッカーはシンプルな構造で、左右のバー(アーム)が、Vの字にパカッと開く。
アタッカーは10カウントで閉じるが、バーの両端に当った玉が、左右オマケチャッカーに流れるから、プラスアルファの出玉を稼げる。最高10ラウンド継続だが、アタッカーのVゾーン入賞が継続条件の為、途中でパンクする事もあった。
アタッカー開放時間は「約20秒」と短いが、ゲージ構成はオマケに流れ易く、1回交換やLN制のホールでは、2800~3000発の出玉も十分期待できた。
一方、無制限のホール(都内では上野に多かった)では、オマケを露骨にマイナス調整する事も多く、2000発前後しか出ない店(台)もあった。
肝心の「連チャン」についても、やはり解析データ不足で明言はできない。但し、当時ホールで露骨に連チャンしていた印象はなく、そういった雑誌情報も少ないので、「ノーマル機」の線が濃厚であろう。
なお、「パンク」と「連チャン」の関係については、91年当時の必勝ガイド誌に、ある興味深い「読者情報」が寄せられた事がある。
それは、「パンク攻略法」とでもいうべき内容で、大当りの6ラウンド目、アタッカーに一発だけ入れたら(Vゾーン以外)、打ち出しをストップ。
そのままパンクさせると、保留玉の消化時に、センターのデジタルは回り出すが、ルーレットランプは動かず、赤い「ATARI」の位置で止まったままになる。その状態で、左右デジタルがゾロ目になれば、ルーレットが当り位置にあるから、無条件で大当り(ダブル)が来る、というもの。
件の読者は、この方法で、実際に何度も連チャンさせたとのこと。また、同様の報告が、別の読者からも、複数寄せられたいう。
ただ、私自身は、本機でのパンク体験は一度もないし、保留連の経験もない(数珠っぽく、早めに当る事はあったが…)。
上記ネタの真偽については、個人的に今も「謎」だが、「ガセネタ」の可能性も、多分にあろう(マジネタならば、「オリジナル攻略大賞」(オリ攻)受賞で、有名になったハズだ)。
※なお、大変有難いことに、本機の「実機動画」が、現在Youtubeで公開されている(リンクは自重)。「平和、アクティブ」で検索すればヒットするので、興味ある方はご覧頂きたい。
フィーバーボルテックスII(三共、デジパチ)
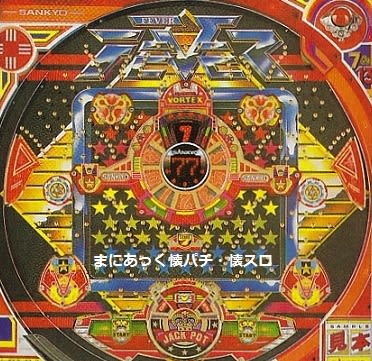
1990年(平成2年)に三共から登場した現金機デジパチ「フィーバーボルテックスII」
★賞球…7&13
★大当り確率…1/240
★センターに円盤式ルーレット、その中心に2ケタドット
★図柄
・ルーレット…0~9(10通り)
・左デジタル…0~9、J、K、L、M、P(15通り)→英文字はハズレ図柄
・右デジタル…0~9、J、K、L、M、P、H(16通り)→英文字はハズレ図柄
★大当り図柄…0~9の3つ揃い(10通り)
★最高10ラウンド継続
★出玉…2000~3000発(勿論、それ以上もそれ以下もある。オマケのクギ調整で変化)
(コチラは、別Verのメラ(セル))
前回、平和「アクティブ」を取り上げた際、ルーレット式デジタルのくだりで、本機を引用した。
で、当ブログの「過去記事」をリンクしようとしたら、記事未作成だった事に気付いてビックリ。
もう、ずっと前にアップしたつもりでいたので、今回、慌てて記事作成に至った次第だ。
本機は、1990年秋に出会って以来、その魅力に取りつかれて打ち込んだ、思い入れある機種である。言わずと知れた、強力な「保留連チャン」が最大の特徴。
大当り時、特定のタイミング(チャンスタイム=5.6秒以内)で始動チャッカーに入賞させれば、点灯した保留玉が「約1/2」の高確率で連チャンした。その為、普段から保留ランプに「空き」を多く作っておくのが有効だった。
「ルーレットとドット」という特徴的なデジタルに加えて、こうした「連チャン」と「技術介入性」がファンの心を掴み、本機は同年の大ヒット機種となった。
さらに、体感器や腕時計を使った、大当り直撃の攻略法も生まれた。但し、コチラは、明らかに機種の「設置寿命」を縮めたので、腕時計はともかくとして、体感器ネタについては、一般ファンの私からすれば、歓迎できない動きだった。
ボードゲーム「人生ゲーム」を思わせる、円盤型ルーレット(ダイヤル式電話も彷彿とさせた)。その中心に、小さな2ケタの赤いドットデジタル。この組み合わせが、本機の大きな外観的特徴だ。
シンプルな3ケタデジタル(ドットや7セグ)が主流だった当時、その独特の「面構え」に、グイッと引き込まれた事を思い出す。
始動チャッカー入賞で、まず、外周の円盤ルーレットが回転。高速で時計回りを続けるルーレットが「0~9」の何れかの数字で止まると、次いで、左ドット→右ドットの順で停止する。
ルーレットはステッピングモーターではなく、普通のモーターを使用。その為、レクサスシリーズのドラムアクションとは異なり、ひたすら「高速回転→即停止」の単純な動きを繰り返す。
また、「折角なら、ルーレットが最後に止まる方が良かった」との批判があった事は、前記事でも触れた通り。
まぁ、正論とは思うが、私自身は、むしろ「右デジ停止が最後で良かった」と思っている。
リーチ時に右デジがスロー回転した後、「ブレーキ」がかかって超スローに切り替わり、直後に大当りする一連の流れが、何とも気持ち良かったからだ。
ブレーキがかかるタイミングは、最終停止の1コマ前と決まっており、超スローの瞬間、当否を察知できた。初当りの時も連チャン時も、この一瞬に脳汁がドバっと吹き出したのだ。まさに、「刹那の興奮」といえよう。
※余談だが、当時のデジパチは、リーチが掛かって、僅かな間で当否が決まる仕組みだった。今のように、「一旦停止→再始動→一旦停止→再始動→ハズレ」のように引っ張ることもなく、当りもハズレも、ノーマルリーチからズバッと一発で決まる。この「潔さ」が大きな魅力だった。最近の世情を見ると、「往生際の悪さ」が各所で目立つが、リーチアクションの変遷と何か関係あるのだろうか…。
また、ルーレットの目が「0~9」の10通りしかなく(ハズレ図柄なし)、他機種よりリーチが多い特徴もあった。「眠くなるようなバラケ目の羅列」(田山幸憲プロ風)に悩まされない点も、最初にルーレットが止まる「利点」ではなかったか。
(「ハズレリーチが煩わしい」との反論もあろう)
大当りすると、盤面下部のアタッカーが開放。円型フォルムで、「桃太郎の桃」の如く、上部がパカッと左右に開く(割れる)のが面白い。最大10ラウンド継続となるが、各ラウンドでアタッカーのVゾーンに入賞しないとパンクする。
(ドットに出る「V」マークも、味わいがあって好きだったな…)
アタッカー開放時間は約21秒。自身の経験では、平均で2700発程度。オマケ次第で3000発(以上)出る事もあったが、無制限の店やボッタ店では、オマケの釘が異様に悪く、2000発を切るケースも。
先述した通り、本機の最大の特徴が、大当り後の「保留玉連チャン」である。
しかも、特定の打ち方をすれば、連チャン率を大きくアップできた。
その方法は、いたってシンプル。通常時、4つの保留ランプを極力つけないようにする。保ゼロがベストだが、時間効率を考えれば、保2まで点灯させても問題ない。
大当りになったら勝負。正確に言えば、大当りする「直前」からが勝負となる。
右図柄が揃った直後、ドット画面に「◇ 大当り スタート ◇」のメッセージが流れる。これが「チャンスタイム」の5.6秒で、この間に始動チャッカーに入賞させれば、点灯した各保留玉が、約1/2(51%)の確率で連チャンした。
したがって、チャンスタイム中に保留を多く点灯させれば、それだけ連チャンし易くなる。
まぁ、5.6秒で打ち出せる玉はせいぜい「8~10発」。成功しても「1個点灯」が多く、2つ入れば御の字という具合だった。もちろん、甘釘で運が良ければ、それ以上入る事もあったが。
但し、チャンスタイムの5.6秒は非常に短い為、大当りしてから打ち出すと、タイミングが遅れて、保留点灯に失敗するケースが多発した。また、慌てて打つと、「玉突き」の危険もあった。
なので、リーチ時は、スロー回転する右デジの動きを見て、大当り手前6コマから、フライング気味に打ち出す。もちろん、ハズレリーチの時もあるが、うまく当れば、チャンスタイムを最大限活用できる。ここまでフライングしても、保留が1個も点かないケースが多かった訳で、本機の連チャンには、「ヘソが甘い事」も重要な条件だった。
チャンスタイム中の点灯に成功しても、連チャン率は約5割で、必ず連チャンする訳ではない。2個入れた玉が両方「スカ」の場合もあり、最後まで油断できなかった。
なお、大当り毎にチャンスタイムは有効だから、うまくいけば、ダブル、トリプル、フォース…と、連チャンが伸びる事もあった。この爆発力も、本機の大きな魅力だ。
因みに、当時の攻略誌の実験(完全単発回し、チャンスタイム中に手入れで4個追加)では、「必勝ガイド誌」が61連チャン、ライバルの「攻略マガジン誌」が45連チャンを、それぞれ記録。
当時の実戦ホールで強く記憶に残るのが、小田急線・向ヶ丘遊園駅北口の「ニューギンザ」(現「GINZA P-style」)と、地下鉄丸の内線・四谷三丁目駅の「タイガー」(現存)である。
ニューギンザは、当時、通い詰めたホールの1つ。当時、小田急線で読売ランド前から新宿に出て、山手線で高田馬場駅まで行き、直通の学バス又は地下鉄で大学に通っていた。しかし、講義のない日(サボった日も多いが)や帰宅時、パチ屋の多い向ヶ丘遊園駅で途中下車して、北口の3軒(ニューギンザ、銀座ホール、銀座スター)と南口の2軒(プラザ、ぱちんこ遊園)を、よく「ハシゴ」した。中でも、ニューギンザは好みの機種が多く、足繁く通った。
本機がニューギンザに新台導入されてからは、暫く客付きが良くて、店に寄っても立見ばかり。その後、釘がシマるにつれて、空き台もチラホラ出始めた。「シマる」といっても、「2.2円」換金なので、都内よりクギは甘めだった。
そんな中、90年12月にこの店の新装開店があり、スロではコンチI、デジパチではキャスター、マーブルX、マジックセブンD、フィーバーフラッシュIなどが入る。
一方、旧台ボルテックスのシマは、新装後の客付きはイマイチ。だが、入口近くの一台のヘソが、やたら広いままの事に気付く。
因みに、当時の設置状況(1990年12月)を見取り図にすると、こうなっていた。
JC=ジェットカウンター(スロ用)
ニューギンザ、1990年12月当時の設置機種…マーブルX(奥村)、マジックセブンD(大一)、FレクサスIVD(三共)、FフラッシュI(三共)、ドリームX(奥村)、エキサイト麻雀5(ニューギン)、FボルテックスII(三共)、キャスター(マルホン)、ビッグポーター(マルホン)、ターゲットI(三共)、ジャスティ(西陣)、マジックカーペットI(三共)、うちのポチI(三共)、演歌道I(三共)、ディスクジョッキー(大一)、コンチネンタルI(瑞穂)、ベンハー(大東音響)
(区民館通りの正面から見て、手前は全てデジパチ、右奥が一発台、景品カウンター前がハネモノ。左端がパチスロのシマ。ボルテックスは右端、キャスターの向かい。ベンハーのシマには、翌年リノが入った。コンチIでバイト料をやられて、残りが小銭だけになった時、ダメ元で、一発台「ターゲット」のカド台に座ったら、100円で大当り穴に決まった事もある。景品カウンター側の裏口では、スロのモーニング狙いで毎朝行列を作った。
その「甘ヘソ台」を一週間ほど追ったら、結構な勝ち額になった。なので、私は新台時よりも、ちょっと後の年末に、本機でいい思いをした。但し、翌年初頭からは、一気にシブ釘化。
一方、四谷三丁目の「タイガー」は、大学の講義が終わり、書店のバイトが始まるまでの「時間潰し」に、よく利用したホール。
授業後、早大正門前から「早81、渋谷駅東口行」の始発バスに乗る(停留場の前には書店があったが、店名を失念。今は跡形もない)。河田町の東京女子医大やフジテレビ本社(当時)の前を通って、食品デパート「丸正」の前の「四谷三丁目」停留所で降りる。
そこから夕刻のバイトまでの空き時間を、件のタイガーや近くの「リボン」でよく過ごした。
タイガーは1Fがパチ、2Fがスロ。等価交換で、クギはかなりシブかった。
しかし、デジパチのオマケチャッカーは良く、1回当れば2600~2700発出て、1万円以上になった(地下が換金所だったかな…)。
で、そのタイガーで頻繁に打っていたのが、FボルテックスII。もちろん、ヘソはガチガチ。
しかし、運良くチャンスタイム入賞に成功すれば、連チャン毎に2万、3万と収支は上がる。
バイト前の短時間でチョチョイッと稼ぐには、打ってつけの環境だった。
そして、このボルテックスのシマには、毎回、同じようなメンツが陣取っていた。若者ではなく、地元の常連風オヤジが数名。結構なコワモテもいたが、皆、話せばいい人だった。
そんなオヤジ客の横で大当りさせると、決まって、「今、チャンス(タイム)で入った?」と聞いてきた。コチラが「2コ入りました」なんて返事すると、「良かったな、連チャン確定だ」と、我が事のように喜んでくれる。それがスカれば、オヤジも顔をしかめて口惜しがる。
お互い素性は知らないが、あの頃のホールの中には、こうした妙な「連帯感」があったと思う。
遊園をネジロにする地元学生(明治、専修の学生が多かった)に混じって「一匹狼」で勝負したニューギンザと違って、タイガーでの等価勝負は、クギはキツいが、心はゆったりしていた。
なお、その他の店では、新宿・歌舞伎町、旧コマ劇前の「ラスベガス」(閉店)や、新宿西口・大ガード前「ニューミヤコ」(閉店、現「カレイド」)などで、ちょいちょい本機を打つ機会があった。
まぁ、新宿なのでクギは推して知るべしだが、ニューミヤコは、割と良心的な営業をしていた。
★連チャンシステムについて
本機の大当り判定には、3つのカウンタ(A、B、C)を使用。
Aはルーレット用(0~9)、Bが左デジタル用(0~14※)、Cが右デジタル用(0~15)。
※「0~239」の240コマだが、必ず16コマおきに進む為、実質「0~14」の15コマ。
Aが1周するとBが1コマ、Bが1周するとCが1コマ進む。A・B・Cは、ケタ上がりの関係。
乱数Aは出目ではなく、ルーレットの「回転時間」を制御・決定。(既定の回転時間に、Aの時間分を加算する)。但し、停止位置が決まれば、その時の停止出目(0~9)も、自ずと決まる。
(ルーレットの停止図柄は、内部の光センサーで確認)
Aで決まったルーレットの停止図柄に、乱数Bの値(15通り)を加算して、左出目を決定。
同様に、ルーレット停止図柄に、乱数Cの値(16通り)を加算して、右出目を決定。
大当りは、「B=C=0」の時に発生。つまり、B、Cが共に「0」の場合。Aの値は不問。
(但し、Aは大当り出目決定カウンターを兼ねる)
当時のデジパチは、保留消化後、空きの保留エリアには、古い乱数が残る設計であった。
一方の本機だが、コチラの空きエリアには、なぜか必ず、「0」が強制的に書き込まれる仕組みになっていた。
これは、従来機にない手法で、連チャン打法を編み出す攻略誌の「裏」をかいた感じもする。
(当時は、保留全灯→全消化で、保4の空きエリアに入った大当り乱数を、保1~保3にコピーする連チャン打法や、ドンスペやレクサスの朝一単発打法などが有名)
だが、本機の連チャンシステムは、「必勝ガイド」誌の解析担当者・クマちゃん先生(大熊氏)が、実機を入手後、たったの30分で見抜いた。
空きの保留エリアには、乱数A、B、Cのいずれも「0」が書き込まれる。つまり、本機では、保留ランプが消えた箇所には、古い乱数ではなく、必ず「0」が入っていた訳だ(朝一に限らず)。
通常は、保留ランプ点灯の瞬間、新たに拾った乱数を保留エリアに「上書き」する。しかし、本機は、大当りメッセージがドットに出る5.6秒のチャンスタイムは、作業量が一時的に増える為に、乱数の上書き処理を失敗し易い。
失敗した場合、空エリアに入っていた「0」が生き残る為、「B=C=0」となって連チャンする。
但し、作業量は5.6秒の中でもバラつく為、上書きしづらい時間帯と、上書きしやすい時間帯に分かれる。それらのトータルの「上書き失敗率」(=保留連チャン率)が、約50%ということだ。
もし、5.6秒中、特に上書きされにくい特定のタイミングが見つかれば、大きな攻略に繋がったかもしれない。
なお、連チャン時は、ルーレット出目に対応する乱数Aの値も「0」となる。つまり、連チャンする時のルーレットの回転時間は、必ず同じ長さになるのだ。なので、連チャンする場合、前回のルーレット停止位置から、次回出目(連チャン時の大当り出目)の「先読み」が可能であった。
具体的には、連チャン時は、前回ルーレット出目に対して、「+2」又は「+3」の位置で止まる。
例えば、「5」で大当り後、保1でルーレットに「7」又は「8」が止まれば、連チャンが期待出来る。リーチが掛かれば、なおさらである。
同様に、保2のルーレットが「3」だった時、次回転で「5」か「6」がルーレットに出ればアツい。
★体感器、腕時計を使った大当り直撃法(ルーレットと右出目を揃える方法)
ルーレットと左デジタルに対応する乱数(A、B)は高速で狙えないが、右デジタル用乱数Cは、周期が約4.8秒※と遅く、外から狙う事ができた。「16コマで4.8秒」だから、1コマ=0.3秒。
※乱数Aの移行速度から計算したCの周期は「4.9152秒」。4.8秒よりは、やや長い。
右出目は、ルーレットの出目にCの値を加算して決まるが、前回の乱数Cが「0」とすると、周期である4.8秒後のCの値は、前回と全く同じ「0」となる。これは、Cが「0」以外でも同じだ。
したがって、ルーレットの出目に拘らず、Cの値が同じなら、ルーレットの出目と右出目の「差」も、やはり同じになるのだ。
この差を利用した「体感器攻略」が発覚したのが、91年の初頭であった。
手順は、まず「4.8秒周期」の体感器(0.6秒の8拍刻みなど)を用意する。ホールで打ち始めたら、任意のタイミングで始動チャッカーに1個入賞させる。出目を見て、ルーレットと右出目の「差」を確認する(ルーレットが「3」で右出目が「5」なら、その差は「+2」)。また、チャッカーに入賞したタイミングも、同様に把握する(0.6秒の8拍刻みなら、何拍目に入ったか)。
もし、この時の差が「+2」なら、乱数Cの値が「2」だった事になる。したがって、4.8秒周期で同じ位置を狙う限り、永久に両者の差は+2のままで、大当りは来ない。ここで狙うべきは、「C=0」となる箇所だ(ルーレットと右出目がゾロ目になる条件)。
先述の通り、乱数Cのカウンターは16コマ(右図柄の数と同じ)で、1周=4.8秒。つまり、図柄1つが「0.3秒」刻みである。
という事は、周期ポイントより0.3秒遅く拾わせればCの値は1増え、逆に0.3秒早く拾わせれば、1減る。
したがって、Cを現在の「2」から「0」にする為には、把握したポイントよりも2コマ分、つまり0.6秒早めに拾わせれば良い訳だ。
これは、ちょうど体感器の「一拍分」に当るから、前回のタイミングより1拍早く拾わせれば、「C=0」となって、ルーレットと右出目がゾロ目になる。
かくして、ルーレットと右出目をゾロ目で揃えたら、そのポイントを把握して、ひたすら4.8秒周期でチャッカーを狙う。後は、左デジタル用乱数が「B=0」になれば、大当りとなる。
さすがにBまでは狙えないが、Bは実質15コマしかないから、タイミングをいったん掴めば、あとは「1/15」の高確率で大当りがやってくる。
但し、周期はピッタリ4.8秒ではないから(計算では4.9152秒)、時間が進めば進むほど、体感器との「ズレ」が生じる。そのズレを適宜把握・修正すれば、体感器攻略は完璧となる。
さらに、体感器の代りに、秒針付きの腕時計を使った大当り狙いも可能だった。
これは、「4.8秒」周期を約5秒周期とみなして、秒針が5秒進む毎に、1区切りとするもの。
やり方も体感器と同様、チャッカー入賞の瞬間の秒針の位置と、ルーレット出目と右出目の「差」をチェック。後は、その差に応じて、ルーレット=右出目となるタイミングを割り出す。
ゾロ目ポイントを掴んだら、そこを基準に5秒刻みで打ち出せば、体感器がなくても、大当りを狙う事ができた訳だ。
但し、4.8秒と5秒では0.2秒の差があり、5周期で1秒のズレが生じるから、5周期=25秒経ったら、「-1秒」の修正を加える必要があった。
しかし、時計でズレを修正するのは骨が折れた為、秒針2回り=2分を1単位として、この2回りを5つのゾーンに分けて、ゾーン毎に打ち出すポイントをずらす「技」が考え出された。1周目と2周目の違いは、分針が「奇数分」か「偶数分」かで識別する。
なお、2分を1単位としたのは、「2分=120秒」が、ちょうど4.8秒の周期とピッタリ重なるから。
(120÷4.8=25)
こうして、「C=0」から遠いタイミングで打つ無駄を省けば、大きな投資の節約になった。
体感器より遥かに労力は多いが、体感器と無縁の一般ファンや、「体感器お断り」の店(まぁ、ほとんどの店がそうなるが…)で打つ人間にとっては、かなり有効な手段といえた。
ただ、上記の攻略は効果が高く(攻略会社が、ガイド誌の記事をもとに高値で売り出した程)、冒頭でも書いた通り、結局は「ヘソの激締め→撤去」という、哀しい流れを作ってしまった。
まぁ、間もなく新要件機が登場して、オマケチャッカーデジパチ全般が終焉を迎えた訳だが…。
ボルテックス好きだった私は、平打ちでも十分楽しかった本機が、体感器ネタで一気にシブ釘→撤去となり、設置寿命が短くなった事には、残念の一言である。
★本機の新要件版…「フィーバーボルテックスSP」
賞球7&15。大当り確率は、破格の1/144。新要件機だが、10ラウンド継続で、出玉は約1400個と少ない。九州を中心に設置されたが、都内でもごく一部に導入。当初は連チャン機か不明とされたが、福岡市の某店や都内・西小山の某店の実戦データから、「保1連チャン機」と確認された(連チャン率は約1/8。但し、無差別連チャン機。チャンスタイム攻略は無効。)
★布川敏和主演のVシネマ「パチンコ・グラフィティ」(1992年)では、松澤一之演ずるサラリーマンが、石塚英彦演じる店員とグルになり、不正基板で連日大当りさせるシーンがある。
その時、初日にタコ出ししたのが「パールセブン」(マルホン)、その翌日に爆裂させたのが本機だった。角台でドル箱をガンガン積み上げる様子に、藤田敏八演じるジグマプロが、「あーあ、盆と正月だ」と言えば、「クリスマスも来ますよ~、ほら来たクリスマス、おーい箱持って来い!」と、悦に入るリーマン。結局、深夜の「仕込み」が店長にバレたグルの店員が、ダッシュで店から逃げ去るという、何とも香ばしいシーンであった。
おむすびくん(平和、ハネモノ)

1994年(平成6年)に平和から登場した新要件ハネモノ「おむすびくん」。
当時、パチでは、同じ平和の「CR名画」なんかが出たばかりで、これが面白くて結構ハマっていた(西武新宿駅前「日拓」など)。ただ、名画は初当り確率が1/360と低く、幾ら追ってもサッパリ当たらない、ドツボの展開に見舞われたりもした。
そんな時、確率の甘いノーマルデジパチ(大同「フィーバールーセントDI」や三共「フィーバービューティフルII」など)に逃げたりもしたが、もっと安ゼニで勝負できるハネモノの本機を、やはり新宿の「アラジン」(現存)で打ったりした。
(’94年頃の新宿「アラジン」の様子…日拓は歌舞伎町だが、こちらは西口ヨドバシ本店界隈。この時期、アラジンの近くでは、スロ専「NASA」「マーブル」「遊」の3店舗も営業中だったが、いずれも既にクローズ。)
ご覧の通り、本機のモチーフは、「おにぎり」…というか、「おむすび」である。
「おにぎり」よりも、「おむすび」と言った方が、何となく「愛嬌」が感じられる。
小さなノリを頭に巻いた、三角の「おむすびくん」が、ヤクモノ内にデンと大きく構えていた。
なりはデカイが、表情はちょっと弱気で、頼りなさそうに見えた。手足も生えていたが、チープな作りで、ユルユル感満載のキャラだった。但し、おむすびくんの「両足」の動きが、ゲーム性に大きな影響を与えた。
「食べ物」がモチーフのハネモノは、過去にも色々出ていた(京楽寿司、すし五郎、ベーカリー、たぬき丼、タコヤキSP、いらっしゃいetc)。また、「料理」のカテゴリーに広げれば、「スーパーシェフEX」や「棒々鶏(バンバンジー)」なども存在した。
だが、本機の如く、食べ物自体を「擬人化」して、ヤクモノのメインキャラに据えたハネモノは、意外と珍しい。
遊技中、スランプに捕まりイライラしても(「クセ」の悪いおむすびくんも、結構いた)、トボけた表情のキャラと目が合った途端に、何だか憎めなくなってしまう…そんな「脱力系」の(神保隊長風にいえば「トホホな」)ハネモノだった。
まぁ、おむすびは、日本伝統の「ソウルフード」な訳だし、本機に愛着を抱くのも自然だろう。
盤面に描かれた「おむすびキャラ」達のセリフも、実にコミカルだ。いかにも酸っぱそうな表情で「梅ー ウメー」とか、パラソル片手に「おいら OMUSUBI KUNです よろしく お願いします」とか、スーパーマンのポーズで「私は 空飛ぶ おむすび へへ!!」とか、いきなり英語で「GOGO I LOVE YOU」など、どれもこれも「ユルキャラ」揃い。
また、盤面には「炊飯器」のキャラもいて、「私が炊いたのに 主役とって!!」と、脇役扱いに不満タラタラである。何ともユニークな盤面であった。
賞球数は「6&10&12」と変則的。左右オトシとセンターのチャッカーが「6個戻し」で、ヤクモノ内が「12個戻し」、その他が「10個戻し」となっていた。
最高継続ラウンド数は8回又は15回。初当りした瞬間、ヤクモノ上の2ケタデジタルで決定。そう、本機は「デジタル搭載型」のハネモノである。
デジタルの出目は、「00」~「99」の10通り。左右ゾロ目で同時回転する為、1ケタデジタルと同じ。
「77」が出れば、最高15ラウンド継続。その他の数字だと、最高8ラウンド。デジタルによる「ラウンド振り分けタイプ」だが、通常の当りでも8ラウンドなので、77が出なくても打ち止めが狙えた。
露骨にデジタルの連チャンを見せた「たぬ吉くん2」などと違って、「77」の出現率は、他の数字と同じ「1/10」である。意図的な連続性はないが、自力で77が続くことはあった。
やはり、前年(1993年)11月に起きた「ダービー物語事件」を契機に、露骨な「連チャン規制」の流れに向かっていた事が、かなり影響したと思われる。しかも、そのダービー事件で標的にされたのが、まさに「平和」であった。出来るだけ、「お上」に目を付けられない、穏やかな機種をリリースしても、仕方ないだろう。
ハネ開閉時間は、左右オトシ(1チャッカー)が0.5秒、ヘソ(センター、2チャッカー)が0.7秒×2となっている。
ハネに拾われた玉は、上段奥から、おむすびくんの左右の腕伝いに落下する。そのまま、下段ステージ両サイドの穴から出ると、おむすびくんの前を通って、手前V方向にアプローチする。
但し、ハネ開閉とほぼ同時に、おむすびくんの「両足」が作動を開始。おむすびくんの前に転がって来た玉を、巧みに「ブロック」してしまう。これが、V入賞率を低下させる要因であった。
それでも、ヤクモノ内の玉に勢い(スピード)があり、下段で角度良く転がれば、両足のブロックをかわして、Vに飛びこむ事があった。また、下段に来るタイミングが丁度いいと、足に当った玉が手前に転がって、そのままVに入ったりした。さらに、複数の玉がヤクモノに入れば、玉突きした玉がVを射止めるチャンスも生まれた。
但し、V入賞率は、台の「ネカセ」や「クセ」によって、大きく変わった。両足のブロックが苦手なおむすびくんは、「甘塩で食べやすい」お宝台。逆に、ヤクモノ内でハズレまくりの、「塩辛い(=しょっぱい)」おむすびくんもいた。もちろん、シマに足繁く通い、各台の特徴を押えておけば、立ち回る上でも有利になった。
大当りすると、下段ステージに通じる左右穴にストッパーがかかって、おむすびくんの両脇に、最大「3個」づつ貯留を行う。但し、片側3個の貯留が満タンになると、後続の玉は貯留されず、下段ステージにこぼれ落ちる(大抵はハズレ)。
なお、おむすびくんの足は、ラウンド開始当初は動いているが、ヤクモノ5カウント後、又はハネ10回開閉後に静止する。
その後、ヤクモノ10カウント又はハネ18回開閉で、貯留は一気に解除。左右3個づつの貯留があれば、V継続は容易だ(たまに、貯留玉同士の玉突きや、貯留不足でパンクしたが…)。
平均貯留個数も多く、貯留解除タイミングも遅かったので、出玉はそれほど悪くない。「77」が出て15ラウンド完走すれば約1300個、8ラウンド完走時は約700個が望めた。
さらに、デジタルに最高15ラウンド継続の「77」が出た時は、大当り後に「お楽しみ」があった。
それは、「77」で大当りした後は、おむすびくんの足の動きが変化する、という事である。
先述の通り、通常時は、ハネが開き始めるとほぼ同時に、おむすびくんの両足が作動を開始。この足が、下段に来た玉をブロックしてしまい、V入賞率を下げていた。
だが、「77」で当った後に限っては、おむすびくんの足が動き始めるタイミングが、通常よりも遅くなるのだ(ハネが完全に開ききってから、足が動き出す)。
その為、ヤクモノに入った玉は、足のブロックを受ける前に、下段ステージの手前を通過する機会が増える。これで、V入賞率は通常より大幅にアップした。
つまり、「77」が出た後は、次の大当り獲得が容易となっていた。これを「連チャン」とすれば、本機にも連チャン性があったといえる。但し、デジタルではなく、あくまでも、ヤクモノの特性を利用した、「疑似連チャン」である。
それでも、大量出玉獲得後、さらなる大当りチャンスが待っているのが、何とも嬉しかった。
なお、77が出て15ラウンド完走せず、途中でパンクしても、大当り後、足の動きは変化する。
当初は、こうした特性を知らない客もいたので、「77」のままヤメた台をハイエナ出来た(出目が「77」だから、すぐ判る)。但し、ナキも寄りも激悪な台で、たまたま「77」が出たような場合、次回の大当りに苦労させられた。
★クリームネタ
なお、本機のV確率をアップさせる為、「ハンドクリーム」を使う方法があった。
ただ、私から言わせれば、これは、「ゴト行為」と大差ないものだ。
以前にも、例えば、豊丸の一般電役「アメリカンドリーム」で、飴玉やグリースでベタベタさせた手で玉を握ってからヤクモノに入れると、ヤクモノ内の玉の動きが変わって、大当りし易くなる手口があった。
しかし、これらは正攻法と程遠いやり口で、台の劣化・故障にも繋がる。たとえ、どれだけ多くの玉を出したとしても、褒められたものではないし、評価する気もない。
そもそも、ハンドクリームをベタベタ塗りたくった手で、おむすびを握ったり食べたりするのは、衛生上、大いに問題があろう。やはり、おむすびならば、「塩」を使うべきだ(笑)。
★おまけのネタ★
・機種名の「おむすびくん」を、豪快に間違えた、某・攻略誌(1994年某月)。
単なる「誤植」というより、担当者の明らかな「勘違い」だろう。どうして、こうなった…(汗)
Youtube 90年代動画紹介(18)
Youtube 90年代動画紹介(18)
私が個人的に「神」と崇めるYoutube動画投稿者、ライルさん(Mr.Lyle Hiroshi Saxon)。
そのライルさんがアップした、90年代初頭の都内各地を撮影した動画を、紹介するコーナー。
何だかんだで18回目となる今回は、コチラの動画を取り上げる。
https://www.youtube.com/watch?v=A_-TwbulLpA
(803)
1992年(平成4年)7月の「早稲田」や「新宿」などを捉えた、貴重な映像だ。
タイトルは、「1992 バスと電車と早稲田と新宿など Buses Trains Waseda Shinjuku Etc 920719 」とのこと。
この動画で、ライルさんが辿った「足どり」は、以下の通り。
★(0:00~0:48)…西武池袋線・ひばりヶ丘駅(ライルさんの地元)周辺
・「ひばりヶ丘駅入口」停留所から、西武バス(田無駅行き)に乗車(0:48)
★(0:49~1:37)…バス車内(田無駅まで移動)
・ライルさんの車内コメント(1:14)が面白い。「このバスは確かに田無駅まで行くんだけど、ちょっと間違えて、遠回りのバスだった。(路線は)3つくらいある。真っ直ぐと、遠回りと…」
つまり、「ひばりヶ丘駅→田無駅」のバスルートは三系統あるが、ライルさんの乗ったバスは、あいにく一番遠回りだったという訳だ。停留所でいえば、「東京道」や「古河(ふるかわ)団地」(現「イオンモール東久留米」)「第三住宅」などを通る、最も大回りのルートであった。
★(1:38~3:09)…西武新宿線・田無駅と、移動中の車内(車窓)
・田無駅ホームから、10時09分発、急行「西武新宿」行き(上り)に乗る(1:55)
★(3:10~5:02)…西武線・高田馬場駅→地下鉄東西線・高田馬場駅→早稲田駅
・西武・高田馬場駅で下車(3:10)
・東西線・高田馬場駅ホームから、「西船橋」行き(下り)に乗車(4:11)
・早稲田駅で下車(4:21)
・早稲田駅の改札(地下)をくぐり、「1番出口」の階段から地上(早稲田通り)に出る(5:02)
★★(5:03~15:50)…早稲田界隈を散策
→これについては後述
★(15:51~20:56)…文京区目白台、関口界隈を散策
・胸突坂(15:51~16:17)
・永青文庫(16:18~)
・蕉雨園(旧・田中光顕邸)(16:38)
・和敬塾(16:40~)
・目白通りに出る(16:53)
・椿山荘(17:14~)
・独協中学校(高校)および周辺(17:29~19:47)
・聖園(みその)幼稚園の看板(19:48)
・東京カテドラル聖マリア大聖堂、関口教会(19:55~20:00)
・鳥尾坂(20:22~20:39)
・目白通りに出て、「椿山荘前」の都バス停留所に到着(20:47)
・都バス(白66、「新宿駅西口」行き)が来る(20:55)
★(20:57~21:51)…都バス(白66、新宿駅西口行)で新宿駅に移動
(江戸川橋通り→外苑東通り→靖国通りのルートで、新宿駅に向かう)
・歌舞伎町・靖国通り(21:48)
★(21:52~22:02)…おそらく、新宿駅西口(終点)の手前、「歌舞伎町」停留所で下車。近くの新宿三丁目界隈(靖国通り脇、「丸井ヤング館」付近)を撮影。
★(22:03~22:38)…紀伊國屋書店(洋書コーナー)→新宿通り(歩行者天国)、駅東口に向う。
★(22:39~25:24)…新宿駅(東口)地下構内→JR中央線(下り)乗車→移動→JR中野駅下車→「中野サンモール」撮影、動画終了
(移動経路まとめ)
ひばりヶ丘→田無→高田馬場→早稲田→目白台・関口→新宿三丁目→新宿駅→中野駅
これら一連の映像の中で、個人的に特に思い入れの深い箇所といえば、(5:03~15:50)の早稲田界隈を、ライルさんが散策するシーン。
やはり、学生時分の丸5年間(1990年4月~1995年3月…訳あって1年余計に通った)、色々とお世話になったエリアだから、少なからず「郷愁」を覚える訳だ。
しかも、撮影時期の1992年は、前年の「不真面目」を猛省して、せっせと講義に通い詰めた頃。
当時の手帳を見返してみた所、幸いにも、撮影時期である「1992年7月19日」前後の予定が、乱雑ながらメモってあった。ちょっと紹介したい。
(1992年当時使っていた、黒革の手帳。小田急沿線のパチ屋や、当時のスロ設置機種などもメモってある。今や、自分にとって貴重な存在だ。)
(当時のメモ書きを拡大…手帳の一角に、92年7月の予定が「殴り書き」されていた)
かなり乱雑な字で見づらい為、あらためて書き起こたのがコチラだ。
7/8 日本政治史 7-114(3:10~4:10)
7/9 国際法 7-218 教・可(9:20~10:20)
国際政治学 3-402(3:10~4:10)
7/15 3限 社会調査 12:30~ 持込可
4限 行政法総論 13:50~
7/18 1限 マスコミ理論
7/20 1限 英書II
※7-114=7号館114号教室
※教・可=教科書の持込可
※英書II=政治英書II
ご覧の通り、書かれていたのは、7/8から7/20の「試験日程」と思しき内容であった。
つまり、1992年7月のこの時期は、ちょうど大学の「前期試験」の真っ只中だったのだ。
前年(1991年)は、講義そっちのけで、パチ・スロにのめり込んでいた。その為、卒倒するほど多くの単位を落とした。それを取り戻すべく、92年に入ると、目の色を変えて、講義や試験に臨んだ事を思い出す。
それでも、講義の合間や学校終りに、馴染みのパチ屋へ通っていた事は変わりない。ただ、学校をサボった回数が「激減」したのだけは確かだ。
因みに、この時期の早稲田界隈のパチ屋といえば、新目白通り(都電停留所近く)の「三光堂」と、西早稲田(バス停前)の「みよし」の2軒だけだった。なお、最近になって新たに判明した事だが、私が1年生の1990年暮れまで、「三光堂」の近く(新目白通り、都バス早稲田営業所の向い)に、「(パチンコ)にっぽん」という変わった名の、小さなパチ屋が存在したという。
(これは、本邦初公開の「レア」情報かも…)
実は、80年代、そこにパチ屋があったという話は、以前、大学の先輩に当る「さる方」から聞いて知っていた。ただ、私自身はその店の存在を全く知らなかった訳だが、なんと私の入学後も、僅かな期間ながら、営業を続けていたらしい。
「にっぽん」は、ネオンも出さぬ小店との事だったが、私がその存在に気付く前に、残念ながらクローズとなってしまった(気付いた時には、既に「ゲーセン」になっていた…)。
もうちょっと早く、あの界隈を入念にチェックしていれば…というか、偶然でも何でもいいから、店の前を通りかかっていたらと、大いに悔やまれる。だが、あの当時、三光堂の常連や店員達から、「にっぽん」に関する情報を貰うチャンスなど、微塵もなかった。嗚呼、勿体ない…。
なお、「にっぽん」は、三光堂と経営が同じで、換金場所(裏路地、長屋の玄関先)も共通だったという。一度は入ってみたかったなぁ…「にっぽん」。
おっと、話を本道に戻そう。
そんな感じで割と学校では頑張った92年だが、91年に落とした単位があまりに多過ぎた為、結局、僅か「1科目」の単位不足で4年での卒業が叶わず、不本意な5年目を迎えた(95年3月卒業)。
ここでは、人生の「挫折」を存分に味わった訳で、若き日の「ほろ苦い」思い出である。
それはともかく、ライルさんが撮影で早稲田を訪れた当日(92年7月19日)は、まさに前期試験の期間中であった。
但し、この日は「日曜」だった為、学生の姿はあまり多くない。おそらくは、私も自宅にこもって、翌日の「政治英書II」の試験準備を、入念に行っていたハズ。
以上が、撮影当日の背景というか、他愛もない「プチ情報」だ。
では、ライルさんが早稲田を撮影した(5:01~15:50)の、簡単な説明に移る。
(5:01~7:21)
地下鉄東西線・早稲田駅の「1番出口」(大学から一番遠い出口)から、地上の「早稲田通り」に出たライルさん。メイン通りを一本入った裏道から馬場方面に戻る格好で、「早稲田高校(中学)」脇のバス通りへと向かう。
なお、この動画ではハッキリ映らないが、このバス通り沿いには「メルシー」という有名なラーメン屋があり(現存)、学生時代に何度も食べた。ウマいラーメンを安価で出す店で、金欠の時は特に重宝した。具は、チャーシュー、メンマ、もやしにコーンで、食べごたえもあった、当時の値段は、ラーメン一杯350円だったと記憶する(今は、少し値上がりしたのかな?)。
(7:23~7:38)
バス通りを隔てて早稲田高の反対側にあった、「早稲田実業」(国分寺に移転する前)の校舎付近を撮影。
(7:48~8:15)
早稲田高校の角を曲がって、大学の「南門」に通じる裏路地を撮影。
→この路地は、地下鉄で大学に通う際の「定番」コース。当時、路地沿いには「早美舎2」(サークルのシャツやジャンパーを作ってくれる)や「喫茶エビアン」(ママさんが美人)といった香ばしい店が点在。注意深く動画を見ると、これら店舗の姿が映っている。
(8:17)
今はなき、「第一学生会館」の建物。その奥に大隈講堂の「時計塔」。第一学生会館の地下には、当時古びた食堂があって、たまにカレーライスなんかを食べた。確かに安かったが、具はほとんど入っておらず(溶けていた?)、味もハッキリ言って…だったな。懐かしいけど。
(8:20)
大学の南門が一瞬映るが、日曜日なので、門は閉鎖中。
(8:21~9:00)
「南門通り」の光景。早美舎1、喫茶ぷらんたん、平山時計店、尾張屋(蕎麦)、クボタ洋服店といった老舗の名物店が映る。また、南門通りから裏路地に入って、早稲田高校を裏から撮影。
因みに、この南門通りには、「稲穂(いなほ)」(閉店)という、早大生なら誰もが知るラーメン屋があり、私も名物の「タンメン」を食べによく通った(アツアツ・野菜たっぷりで美味かった)。
1年生の時分、大学祭でサークルの「広報誌」を出す事となり、学校近辺の店に、雑誌への広告掲載(サークルの広告収入用)を依頼して回った事がある。で、私は馴染みだった「稲穂」に出向いて広告を依頼したのだが、オヤジさんに「すまない、そういう話は全て断っているよ」と、丁重に断られた。
確かに、無数にいる常連学生の依頼をいちいち聞いていたら、店だって大変だ。私の依頼は、いかにも厚かましすぎた。
だが、その時、傍らにいた奥さんが、「この子は、いつも食べに来てくれるのよ。少し話を聞いてもいいじゃない」と、有難い「助け船」を出してくれた。そのお蔭で、広告依頼の件は、無事OKが貰えたのだった。奥さんの優しさには、今でも感謝している。
(9:01~11:20)
早美舎2と喫茶エビアンのある路地に戻った後、再び早稲田高校脇のバス通りを歩いて、地下鉄・早稲田駅に向かう。
(11:21~13:00)
早稲田駅の改札前から、「3a出口」の階段を上がって地上に出た後、再び駅地下構内に戻り、今度は逆の「3b出口」から地上に出て、早稲田通りを歩く。途中、早稲田高の入口や靴屋をチェックした後、馬場下町の交差点に出ると、本部キャンパスに向って南門通りに入る。
地下鉄出口脇「ダンキンドーナッツ」(12:04)の看板が懐かしい。また、12:13では、早稲田通りで停車している都バスの「行先ボード」を接写。「早77」系統、「新宿駅西口」と「早稲田」を結ぶバスは、当時、大学から歌舞伎町のパチ屋へ向かう時によく使った「直行便」だ。講義が終わると、大隈通りを通って「グランド坂下」の停留所でバスに乗り込み、「歌舞伎町」停留所で降りるのが定番パターンだった。但し、現在は一部ルートが変更されており、この「早77」バスは、「グランド坂下~坂上」の「グランド坂通り」を通らなくなった。
キッチンオトボケ、三朝庵(蕎麦)、竜泉寺、穴八幡などがある「馬場下町」に出た後(12:54)、交差点を右折して、再び南門通りを散策、大学方向を目指す。
(13:01~13:49)
南門通りを歩いて、大隈講堂のある早大正門前に向かう。
13:28では、「工事現場」「第一学生会館」「時計塔」が一度に映る。工事しているのは、従来「廣文堂書店」(南門店)が入っていた建物だ(第一学生会館の向かい)。当時、廣文堂は南門通りと「グランド坂上(店)」の二店舗があったが、現在はいずれも確認できず(閉店か)。当時、この書店で教科書を買っていたっけ…。
13:30で、高田馬場駅と早大正門を結ぶ「学バス」が通過。これも勿論、お世話になった。
13:37では、大隈講堂の左後方で、「大隈会館」(及び「リーガロイヤル早稲田」)が建設中
(翌1993年竣工)。
13:43でチラッと映る青い屋根のバス停は、早大正門と渋谷駅東口を結ぶ、「早81」系統のバスの始発停留所だ。当時、私は、この停留所から、授業終わりに四谷三丁目に出向き、書店のバイトに毎週通っていた。13:46では、待機中の渋谷行きバスの姿がチラッと映る。
(13:40~15:50)
正門前(大隈講堂前)を起点に、「早大通り」を鶴巻方面に歩く。「早稲田鶴巻町西」交差点を左折してバス通りをしばらく歩くと、大通りの「新目白通り」に出る。さらに新目白通りを超えて、その先に流れる神田川を渡ると、「胸突坂」の階段から目白台に向かう。
14:06辺りで、大隈講堂裏の「早稲田ゼミナール」(予備校)が映る。今でも同じ場所にあると思っていたが、とっくの昔になくなった模様(現在は早大の「エクステンションセンター」が入る)
14:13では、ライルさんがコカ・コーラの自販機で、「Mone(モネ)はちみつ梅」を購入。実に美味しそうな飲みっぷりを見せる。確かに、このドリンクは甘酸っぱくて旨かったと記憶。
14:59で、新目白通り沿いで建設中の、「リーガロイヤル早稲田」の現場が一瞬だけ映る。
15:30・・・駒塚橋(神田川)、看板など
15:33・・・駒塚橋から臨む、目白「椿山荘」の立派な建物
(以後は、上掲「文京区目白台、関口界隈を散策」の項を参照)
旅打ちの記憶(1998年8月) ~広島、新見、鳥取~
今から17年前の1998年(平成10年)8月、私は「旅打ち」という名の小旅行に出かけた。
まぁ、日頃たまった仕事のストレスを解消させようと、休暇を使ってパチ・スロの「地方遠征」を決行した訳だ。
そういえば、私は「BOSSとしのけんの旅打ち(企画)」(1998年~2000年)に触発されて、旅打ちを始めた…と言うようなことを、過去記事で書いた事がある。
しかし、過去の行動記録をあらためて見ると、私は「1997年」に旅打ちを開始している。その頃は、まだ「旅打ち企画」も始まっておらず、当初は「自発的」に旅打ちを決意した事が窺える。
その後、2人の遠征企画を雑誌やビデオで見る機会が増え、自分の旅打ち意欲も増幅して、地方に出向く頻度が多くなった…という感じだ。実際、1999年~2001年の記録を見返すと、旅打ちの機会がグンと増えている。
まぁ、それはともかく、98年8月の旅打ちの際、私が目的地に選んだのは「広島」であった。
なぜ広島に決めたかは、イマイチよく覚えていない。正直な所、「遠出」さえできれば、場所は何処でも良かったと思う。ただ、過去に修学旅行で行った事があったり、小学生の頃から広島カープのファンだったりした事が、影響したのかもしれない。
この時は、広島での宿泊先を事前予約しておいたが、移動については、完全に「行き当たりばったり」であった。
さらに、宿代や交通費等の経費は、遠征先のパチ屋で全て回収したかったから、なるべくカネがかからない手段を選んだ。
随分と虫のいい話かもしれないが、これが面白いくらいにうまくいった。私の旅打ちの成績は、地元でのヘボい立ち回りとは違って、実に芳しい成果を収めた。
出発当日、小田急線で小田原駅まで出ると、そこで初めて新幹線の時刻表を見て、乗るべき列車を決めた。こんな適当な計画だったから、「ひかり」や「のぞみ」ではなくて、時間がかかる「こだま」で新大阪まで行った(のぞみは、当時割高料金で、ハナから使う気がなかったし、そもそも小田原には止まらない)。
途中の岐阜羽島駅で、やたらと長い「通過待ち」をした事も記憶に刺さる。「新幹線のクセに、通過待ちしやがって」と、結構なカルチャーショックを受けたからだ。
新大阪からは、別の新幹線(これも「こだま」だったかな)に乗り換えて、広島まで直行した。ずっと座っていたとはいえ、疲れがたまる長時間の移動であった。
広島駅につくと、駅前のパチ屋などをブラブラとチェックして回った後、この日の宿泊先である「ホテル広島ガーデンパレス」に向かい、チェックインを済ませてから、ホテルの周辺を散策。
すると、ホテルの近くに「キング」という香ばしいパチ屋を発見。中に入ってみると、パチスロのシマの一角で、NETの「ネイバルソルジャーS」というマイナー4号機と初遭遇する。
見れば、出玉も案外よさげである。「マイナー機」という物珍しさも手伝って、適当な空き台に座って、いきなり勝負を開始した。まぁ、いかにも無謀な挑戦である。
が、その台は意外に食いつきが良く、同じ台で夜まで粘った結果、行きの交通費とホテルの代金が出る程度の勝ちを拾った。まったくの「マグレ勝ち」に過ぎなかったが…。
過去の旅打ちを思い返すと、こうしたいい加減な立ち回りでも、けっこう勝つ事が多かった。ハッキリいえば、「ヒキ」に助けられてばかりの旅だと思う。
ひょっとすると、見知らぬ地での孤独な実戦が、独特な「緊張感」をもたらして、私に不思議なパワーを出させたのかもしれない…(未確認)。
その夜は、広島名物の「お好み焼き」を堪能…する事ができず、近くのコンビニで弁当を買い、ホテルの部屋で一人寂しく食べた。その後、移動や実戦の疲れがドッと出てで、いつしか眠りに落ちた。
で、翌朝になると、なぜか、「もう広島は満足だな。何処か別の場所に移動しよう」という気分になっていた。
たった半日程度、ホテル近くのパチ屋でスロのマイナー機を打っただけで、私の「旅打ち欲」は満たされてしまったようだ。名所の「広島市民球場」や「原爆ドーム」に行ってみようとは、全く思わなかった。
(実は、2000年にも広島旅打ちの機会があって、その時は球場もドームもちゃんと訪問した)
そんな訳で、朝早くにチェックアウトを済ませると、すぐに広島駅へ向かった。前日の下見で、駅前にパチ屋が多い事は判っていたが、まだ開店前だったし、前日に勝ったという「充足感」もあり、わざわざ開店待ちして、駅前ホールで実戦する気にはならなかった。
で、駅構内で時刻表や経路図とにらめっこした後、唐突に「山陰地方に行こう」と決めた。
山陰エリア、特に島根・鳥取の2県は、当時の自分にとって、まだ「未知の領域」だった。その近くの広島に来たことで、「ぜひ、一度足を踏み入れたい」と思い付いた訳だ。
移動費用に関しても、広島駅から在来線を乗り継げば、松江や米子まで、割安で辿り着く事ができると判った。
そこで、携帯で宿泊先を割り出して、米子駅近くの「アルファ―ワン(α―1)」というホテルに、当日の宿泊予約を入れた。これで、今日の宿は安心。後は移動だけである。
広島駅で私が乗り込んだのは、JR芸備線というローカル線だった。一両か二両編成のひなびた鈍行列車で、広島から「三次(広島県)」~「新見(岡山県)」と乗り継いだ。
が、これが、エラく時間のかかる移動になってしまった。中国山地の奥深い山間を縫うように、ひたすら単線を走り続ける、まさに「ローカル線の旅」。
車窓に映る木々や渓流を眺めたり、途中で仮眠したりして、5時間くらいかけて、ようやく新見駅に到着した。
流石に腹が減っていたので、駅構内にあった、古い立ち食いそば屋で、軽い昼食をとる。
腹が満たされると、今度は「パチりたい」という欲求に駆られた。幸い、次に乗るべき電車は、だいぶ先だったので、待ち時間を利用して、「パチ屋探し」をする気になった。
古びた改札を出て、ふと後ろを振り返ると、なんだか「まんが日本むかし話」に登場しそうな、丸くて大きな山が、駅舎の背後に「デン」と構えている。
「こんな山深い場所に、パチ屋なんてあるのか…」と、不安に駆られつつ駅周辺を探索すると、駅から少し歩いた国道沿いに、一軒のホール※を発見。
※この時は、立ち寄ったパチ屋の名前を全く知らず、独自調査で、「京極遊技場」(閉店)だと思い込んでいた(過去記事でも、そう紹介した)。しかし、京極遊技場はもっと小さい店で、場所ももっと駅寄りだった。で、私が入ったパチ屋は、「エンドレス」という店だった事も判明。実に、大きな勘違いであった(過去記事を読まれた方、申し訳ない。該当箇所は、訂正させて頂く)。
この新見「エンドレス」の一角にあった、奥村の現金機「モナコボートSP」に座り、短時間勝負を挑んだら、最初に両替した1000円が無くなる前に、大当りしてしまったのだ。しかも、まさかの保留玉連チャンまで付いてきた。
またも旅打ちでの「ヒキ」を見せた私は、約4000発の玉をさっさと換金すると、交通費が出た事に満足して、意気揚々と新見駅に戻った。
新見からは、芸備線で備後落合駅に戻ると、JR木次線という別のローカル線に乗り換えて、島根県の木次駅→宍道駅と移動。そこで山陰本線に乗り換えて、一度は立ち寄りたかった、松江駅を目指した。ここでも、特急・急行の類は使わずに鈍行で移動したから、えらく時間がかかってしまった。
松江駅に着いた時には、すでに夜9時半を過ぎていた。確か、広島駅を出たのが午前8時過ぎだから、松江までの移動には、途中の寄り道も含めると、およそ13時間もかかった訳だ。
流石に私もヘトヘトで、夜の松江でパチろうとは、少しも思わなかった。だが、半ば義務的に、駅前の路地(まだ再開発前)を歩いて回り、2,3軒のパチ屋を覗いてみた。流石にどの店も、この時間ともなれば、客はまばらだった。まぁ、遠征の証に100円くらい打ってもよかったが、あまりの疲れに、そんな気すら起きなかった。
松江に戻ると、再び山陰本線に乗り込み、ホテルがある鳥取県の米子駅に向かった。駅に着いてホテルに直行すると、夜11時の遅いチェックインを終えて、駅前の小さな居酒屋で晩飯をとった。しかし、ローカル線の長距離移動が、ここまで過酷だとは思わなかった。完全に、中国山地をなめていたな…。
なお、現在の「経路探索」ソフトで上記ルートを調べてみると、私が動いた上記の経路(全てローカル線の鈍行列車)で、約13時間で広島から米子に移動するのは、無理のようだ。98年当時は、現在と比べて在来線の本数が多かった事も判る。
さて、米子に泊まった翌朝は、「もう、移動は沢山だ。早く帰りたい」という気分になっていた。
ああも一日中列車に乗り続けていると、余程の鉄道ファンでもない限りは、疲れ切ってしまう。駅周辺のパチ屋探しは諦める事にして、帰京すべく米子駅に向かった。
ただ、駅に着くと、「鳥取といえば、『温泉』と『砂丘』」だな。砂丘などは興味もないが、昨日の疲れを取りたいし、鳥取駅に出向いて、温泉にでも入ろう。」と、急に思い立った。
米子から鳥取駅まで電車で出ると、パチ屋探しならぬ、「風呂屋探し」を開始した。勘を頼りにしばらく歩き回ると、街はずれの川っぷちに、「鳥取温泉」という小さな看板が出ている建物を、偶然にも発見した。
見ると、「温泉」というよりは、地元の「銭湯」に近い、こじんまりとした施設であった。それでも、お湯自体は天然温泉なので、贅沢は言うまい。鳥取に立ち寄った証に、此処のお湯で疲れをとる事にした。
中に入ると、やはり銭湯調の番台と脱衣所があった。料金を払い、服を脱いで浴場に入ると、まだ午前10時半くらいだった事もあって、先客はいなかった。
すっかり「貸切状態」の中、気持ちよい天然温泉の湯につかって、天にも昇るような気持ちで、しばし休息する。湯気を存分に吸いこみ、ジンワリ汗をかいて、「あぁ、気持ちいい」…。昨日の長距離移動の疲れも、一気に吹っ飛ぶ。
すると、突然、「ガラリ」と浴場の戸が開く音がして、数名の男達がゾロゾロと入ってきた。
その瞬間は、「おっ、地元の常連が、団体で朝風呂でも浴びに来たか」と、思っていたが…
ふと、近づいてきた彼らの方を見やると、一人残らず、その背中や両腕に、赤や緑のカラフルな「模様」が入っているではないか。
それは、明らかに「その筋」のご一行であった。確かに、地元の常連には違いないが…。
その数、7、8名。手拭を担いだ背中には、龍や鯉の鮮やかな「イラスト」が、チラチラ見え隠れする。
「ヤバイ…」私は、そう直感した。だが、大きな湯船は1つしかなく、彼らは次々と湯船に入って来ては、私の至近距離に腰を下ろしていく。
その間、私を支配した感情は、まさに「恐怖」であった。鳥取にまで来て、なんたる展開か…。いくら旅打ちの「ヒキ」が良くても、こんなものまで引き連れてくるとは、夢想だにしなかった。
コワモテの男達は、チラリとコチラに一瞥をくれた後、湯船で楽しそうに会話を始めた。しかも、私の両サイドから取り囲むような形で…。とてもじゃないが、落ち着いて温泉を楽しむ状況じゃない。
その時、背後で「オイッ」と声がしたので、ドキッとしてそちらを振り向き、「あの…私ですか?」と恐る恐る聞くと、「いや、あっちだ」と、洗い場にいる仲間の方に声をかけていた。
まぁ、何とも滑稽なやり取りだったが、それを楽しむ余裕など、微塵もなかった。
しばらく緊張の時間が流れたが、結局、彼らが洗い場に立った一瞬のタイミングを見計らって、バッと湯船から飛び出すと、ダッシュで洗い場の横を通り抜けて、脱衣所に「脱出」した。
そして、慌てて服を着て表に出ると、入口前に、黒塗りの高級外車が2台、横付けされていた。
やっぱり、あれは、地元の「その筋」だったんだ…と確信する。
まぁ、よくよく考えれば、彼らも彼らなりに気を遣い、カタギの人たちになるべく迷惑をかけないよう、「午前10時過ぎ」の早い時間をわざわざ選んで、温泉にやってきたのだ。
そこに、遠征中の私が先客で立ち寄っていたので、運悪く鉢合わせしてしまった。ある意味で、イチゲンである私の方が、「間が悪かった」のだろう。
その昔、ドリフのコントで、サウナにヤ〇ザが次々と入ってくるネタがあったが、まさか、こんなところで、自分がリアルな「ドリフネタ」に巻き込まれるとは、夢にも思わなかった。
しかしまぁ、見方を変えれば、これはこれで、「貴重な体験」だったのかもしれない。
その後、鳥取駅に舞い戻った私は、11時49分発の「スーパーはくと6号」で、終点の京都駅に向けて出発した。
ただ、あまりに「衝撃的」な体験をしたせいか、京都駅に着いてからも、パチる意欲はいっこうに沸かなかった。とりあえずは京都まで来たので、地下鉄を使ったり歩いたりして、平安神宮、南禅寺、銀閣寺などの名所を回ったが、やっぱり我が家が恋しくなって、そのまま帰京した…。
まぁ、これが1998年8月に行った、旅打ちの「全貌」である。
よく考えれば、計3日間の日程で、パチ・スロに費やした機会は、たった2回きり。打った台も、NETの「ネイバルソルジャーS」と、奥村モナコの「モナコボートSP」だけだ。
その他は、長距離の列車移動と、ホテル宿泊と、鳥取温泉の「入れ墨」という具合(笑)。
パチ・スロの戦績は「2戦2勝」だが、この程度では、「旅打ち」と呼ぶには、少々不甲斐ない。
しかし、道中で味わった「濃密」な体験は、17年経った今でも、脳裏に焼き付いている。
今、あらためて同じ経験をしようと思っても、色んな意味で無理だろう。やはり、90年代だからこそ敢行できた、「若き日の貴重な思い出」である。これからも、忘れる事はないだろう…。
この旅打ち時のホテル領収書や切符の類は、残念ながら大半が手元に残っていない。唯一、今でも残る「証」が、この特急券。平成10年(1998年)8月20日、11時49分発、鳥取発・京都行きの「スーパーはくと6号」。これを見るたびに、あの夏の日の記憶がジンワリ蘇る。
ディーゾーン(エマ、4号機)の思い出
前記事に続いて、過去の「旅打ち」での、他愛ない思い出話などを…
「一期一会」(いちごいちえ)…一生にたった一度だけの、大変貴重な出会い。
唐突な出だしで恐縮だが、この言葉を聞くと、私には、真っ先にピンとくる台がある。
それは、当時、マイナーメーカーだったエマから出た、マイナー4号機「ディーゾーン」だ。
(こう「マイナー、マイナー」と繰り返しては、エマの熱烈なファンから怒られそうだが)
ディーゾーン(D-ZONE)
(エマ、4号機、1999年リリース)
BIG REG
1/298 1/661
1/280 1/661
1/260 1/661
1/246 1/578
1/237 1/486
1/237 1/356
恥ずかしながら、私が本機と対戦した機会は、たった1回きりしかない。
チェリーの形を暗記するほど打ち込んだフリークの方は、「何だ、その程度でこの台を語るな」と、感情を害されるかもしれない。至極、もっともな話だ。
ただ、その1回限りの実戦が、私にとっては大いに「刺さる」ものであり、鮮烈な印象を残した。
今回は、その時の体験談を、少々お話ししたい。
15年前の2000年(平成12年)5月、私はゴールデンウィークの休みを利用して、パチンコのメッカ、名古屋に遠征した。
もちろん、単なる旅行ではなく、遠征先のパチ屋、スロ屋での「旅打ち」が、主たる目的だ。
名古屋には、それ以前に二度ほど訪れた事があって、拠点となる宿は、同じビジネスホテルにいつも決めていた。JR名古屋駅・太閤口(新幹線口)近くにある、「名古屋リバティーホテル」と「名古屋フラワーホテル」である。
この時は、5月4日~6日の「2泊3日」で遠征を計画。宿泊先は、「駅の真横」という好立地で便利な「フラワーホテル」であった(リバティホテルは、駅からチョイ離れている)。
遠征初日は、手近な場所で楽しもうと、ホテル近辺のパチ屋・スロ屋で実戦を行った。ホテルから歩いて数秒の「スロットピーチ」や、ターミナル前の老舗「太陽」、さらに、「ウィングレット」「ジャンボ」「ニューひかり」など、太閤口に点在するホールをハシゴした。
この日は、朝から「ウィングレット」の地下で沖スロ「シオサイ30」を打ち、そこそこの額の勝ちを拾った後、他の店のパチやスロを、アレコレ「つまみ食い」したハズだ。
(ウィングレットのシオサイは、何かと収支に貢献してくれた)
「ニューひかり」では、バークレスト4号機「プレリュード2」を打った事が印象に残る。その傍の「太陽」では、デジパチのシマに初期・新要件機「リバティIII」(奥村)が置いてあり、懐かしさと共に実戦。
勝負終わりには、名古屋駅地下街の一角にて、「ひつまぶし」を食べた事も思い出す(店員のオバさんが、正しい食べ方をレクチャーしてくれた)。過去の名古屋遠征では、「コンビニ食」がメインで、地元の名物を堪能できなかったから、「ひつまぶし初体験」は、それなりに感動した。
続く二日目は、最初、「ウィングレット」でシオサイ30を打ったが、あまり調子が芳しくなかった。その後、他店に移動してみてが、どうにもヒキが悪く、結果はサッパリだった。
そんな状況になった時、「せっかく名古屋まで来て、ずっと同じ場所で停泊しているのも、何かつまらないな…」と感じて、夕刻、名古屋駅からの移動を決意する。
ただ、過去の名古屋遠征では、ほとんど名駅周辺で打っていたので、他のエリアの土地勘は、全く無かった。
なので、とりあえず路線図で適当なエリアを選び、そこで、行き当たりばったりのパチ屋探しをする事にした。この「行き当たりばったり」も、私の旅打ちにおける「キーワード」だ。
手始めに移動したのは、名古屋有数の繁華街、「栄」であった。名駅から、市営地下鉄の東山線で栄駅に出ると、多くの店舗が居並ぶ地下街を歩いた。まず腹ごしらえという事で、地下で見つけた食堂で、名古屋名物「味噌カツ定食」を注文。確かに美味かったが、ちょっと値段が高いと感じた。
食事後、地下街から地上に出て、多くの人でごった返す栄の繁華街を探索。予想通り、多くのパチ屋・スロ屋に出くわしたが、あまり触手は動かず、どの店も「チラ見」程度で終わった。
やはり、ゴールデンウィーク真っ只中という事で、どこもかしこも客が多すぎて、空き台探しがままならない状況だった。しかも、太閤口で負けていた事もあり、適当な台で勝負する勇気はなく、加えて設置機種のラインナップも、今一つグッとこなかった。
結局、栄での実戦は諦めて、再移動を決意する。正直、他の目的地はなかったが、地下鉄の経路図をジッと眺めつつ、栄駅の近くで複数の鉄道が乗り入れる、ターミナル駅を探した。
すると、さほど遠くない位置に、「金山」という駅を発見。どんな場所か皆目判らなかったが、JR・私鉄・地下鉄が乗り入れる大きな駅なので、パチ屋も多いだろうと考えた。
栄から、地下鉄・名城線に乗り込んで、お目当ての金山駅で下車。外に出てみると、いきなり、大通り沿いに大きなパチ屋があった。看板には「京楽会館」とある。旅打ちで、初めてメーカー直営店らしき大型店舗を見つけて、「本場の名古屋に来たんだな…」と実感した。
ただ、この店でも打ちたい台は見当たらず、さらに駅周辺を色々と歩き周り、幾つかホールを覗いてみたが、栄と同様に、設置や出玉の状況に、グッと来る事はなかった。
「このエリアも微妙っぽいし、早いとこ、名古屋駅に戻ろう」と思いつつ、最後に、一軒のパチ屋へ足を踏み入れた。
しかし、この店で、まさに「運命の出会い」が待っていたのだ。
駅から少し歩いた広い通り沿いに、「某店」(設置機種がアレな為、実名は伏せる)はあった。大きい雑居ビルに入っている店舗で、上階にはカプセルホテルやサウナもある。
私自身、こういう雰囲気のパチ屋が大好きだったから、自然と店内に引き込まれた。
中に入ると、スロのシマの一角に、ちょっと見慣れない台を発見。それが、コイツだった。
ブルーの独特な筐体に、一クセも二クセもありそうな、いかつい表情のサメ。
機種名にしたって、いかにも怪しげだ。D-ZONE?「D」って何だ?Dangerって事か?
この台、地元でも、職場近くでも見た事はなく、攻略誌で見たかどうかも、あやふやだった。
しかし、筐体からは、コチラを惹きつける、独特の「引力」めいたものを感じる。
しかも、その雰囲気たるや、どうみても、「アレ」な出方をするヤツだ。
あいにく、ディーゾーンのシマはガラガラで、爆裂中の客の姿もない。常連風のオッチャンが、2名ほど現金投資中。あとは、水商売風の綺麗なお姉さんが、一人黙々と打っているだけだ。
他のシマには結構な客がついているのに、ディーゾーンのシマだけは、何故か活気が無い。
データランプをみると、ゲーム数表示と、当日のビッグ、レギュラー回数が表示される。だが、目を疑うボーナス回数の台はない。まぁ、稼働がイマイチなので、仕方ない。しかし、総ゲーム数がチェックできないのが、何とも残念(「アレ」の判断には、大いに役立つのに…)。
こうしたシマの状況を見る限り、眼前に佇むディーゾーンの「性格」を判断するのは、いかにも難しく思えた。
それでも、せっかく出会った台、しかも興味を引くマイナー機。ともかく3000円くらいは打っておこうと、弱気にペシペシ打ち始める。3000円で何も来なかったら、とっとと諦めて太閤口に帰ろうか…。
筐体をよくみると、ボタンやレバーや下パネル辺りが、デコボコ、ザラザラしている。この妙な「突起」は、もしかして「サメ肌」を意識したものだろうか?触ってみると、ちょっと気持ちいい。
そうこうするうちに、あっけなく3000円はノマれてしまった。時折、「WARNING」と書かれたリール窓上の文字ランプが光るが、ボーナスが入っている様子はない。赤7もサメの図柄も、実に「香ばしい」フォルムで、一度は揃えてみたい。しかし、旅打ちでの大負けも怖い。ここは、今日のヒキの弱さを認めて、潔く引くべきだろう。
そう思って、「さて、帰るか…」と席を立ちかけた時、近くで明らかな「異変」を感じた。
三台隣りで打っていた「おミズ系」の女性は、さっき、ビッグボーナスが始まったばかり。「彼女のビッグ後の挙動を見れば、台の特徴が判るかも…」と、ビッグの消化を横目でチラチラ見ていたのだが…。
あろう事か、このお姉さん、ビッグボーナスが終わるや否や、速攻でクレジットを全部落として、1回転もさせずに、そのままヤメて帰ってしまったのだ。しばし唖然、茫然である。
ノーマル台なら有り得る展開だが、自分の頭の中では、すでに「この台は『アレ』なヤツ」という期待感で満ちていた。そんな台が、「ビッグ後0回転」で、目の前でポイッと捨てられたのだ。
あのお姉さんは、時間切れでやむ無く台を捨てたのか、或いはズブの素人で、ノーマルだと思ったのか。もしや、凄く打ち込んでいる常連で、このビッグが連チャンしない、何らかの「サイン(挙動)」を見抜いたのか…。
あれこれ考えたが、答えは出るはずもない。しかし、ビッグを終えた0ヤメ台が、気前よく捨てられたのは、明白な事実。ここは、どう考えても「移動」が正解だろう。
幸い、これに気付いて後釜を狙うハイエナの姿はない。ただ、露骨に飛びついてハイエナするのもアレなので、お姉さんがシマから消えたのを確認して、サッと台移動を決行した。
もし、この台が「アレ」で、しかも連ゾーンに入っていたら、すぐに「ウハウハ」な展開が訪れる。うまくいけば、今日の負け分も回収できる…と、期待感タップリに打ち始める。
だが、ビッグ後のクレジット分を打ち込んでも、さらに100ゲームまで回してみても、大当りはサッパリ引けない。バケすら、全く引ける気配がない。
そう、彼女が捨てたのは、ただの「単発ビッグ」だった。まさか、初めから見切っていた…?
ぬか喜びにガックリしつつも、「ひょっとして、引き戻しがあるかも…」と、投資を続ける事に。
ただ、「ビッグ終了後から打ち始めた」という特殊な状況が、何となく、「やめるにやめられない」雰囲気を作ってしまった。このまま投資が止まらなくなれば、大事である。
勝手も知らぬ遠方の地で、大負け喰らって凹むのだけは、何としても避けたい…。
そこで、「アレ」な機種の引き戻しゾーンでありがちな、「400ゲーム」を限度にヤメようと決意。何があっても、この線を超える事だけはダメと、強く自分に言い聞かせる。
そんな覚悟を決めた矢先の350ゲーム辺りで、まさかの「初ビッグ」が入った。0ゲームヤメから追ったので、案外と投資が掛かった。
リーチ目もリール制御もよく判らないから、唐突にビッグが飛び込んだ感じだ。かなり攻撃的なファンファーレに、ちょっと腰が浮く。
ビッグ中に、あらためてリール配列を観察すると、リプレイハズシは効きそうな気配※。
※ハズシは可能だが、配列上、「上段受け」しかハズせない(保険ハズシで対応可)。
しかし、もしこの台が「アレ」な台で、なおかつ、ハズシで連チャンが止まるVerだったら、あまりに勿体ない。念の為、ハズシはせずに、順押し・小役狙いで消化。それでも、小役はそこそこ落ちるので、ハズシなしでも380枚以上は出てくれた。
そして、「連チャン」への期待を込めたビッグ終了後。まずはクレジット分を回したが、ボーナスは入らず。50ゲーム回しても、100ゲームを過ぎても、ダメ。これって、もしやノーマル…?
すると、150ゲーム辺りで、レギュラー(サメ)が揃う。どうやら、左リールの「7・スイカ・サメ」は「強い目」のようだ(註:スイカこぼしorボーナス)。「D-ZONE」と書かれた「0枚役」も、揃えば、おそらくリーチ目だろう。もし、コイツがダイナマイトバージョンなら、このバケをきっかけに、ガンガン噴く可能性もある。
しかし、バケ後は何も起こらぬまま、あっさりと100P経過。ヤバい、本当にノーマルかも…。
すると、持ちコインをノマレる寸前、再びビッグを引く。これで、首の皮一枚繋がった。
さらに、そのビッグが終わって、80ゲームほど回した所で、またビッグが入る。
これは、ひょっとして、来たのか…?
そう、まさに、このビッグをきっかけに、待望の「アレ」がやって来たのだ。ビッグ終了後、クレジット内でビッグばかりがポンポン続く、シビれる展開に。
たまに、50ゲーム以上かかる事もあるが、大半がビッグの「速攻」連チャン。やっぱり、コイツは正真正銘の「アレ」であった。
こんなに出るのに、何で、こうも客付きが悪いのか…。やはり、爆裂度が高い分、初当りがキツかったり、滅多に連チャンしなかったりと、そういう類の台かも知れない。むしろ、この程度の投資で済んだのは、運がよかったのかも。
連チャン中は、赤7が左・中リールでテンパれば、面白いくらいにそのまま揃う。左リールの「7・スイカ・サメ」や「リプ・7・スイカ」も、ほぼガセらない。リール窓上の「WARNING」ランプも、途中で消えずに、第3停止まで点灯する場合がほとんど。さらに、第三停止時、派手な効果音と共に、いきなり「WARNING」ランプがつくことも。
さらに、レバーオン後、リールがしばらく回り出さない「フリーズ」(註:本機での呼び名は「クラッシュ」)のレア演出も、1回だけ出てしまった。町田の「さくら屋」でつい先日打った、「キングジャック」を思い出す。何とも凄い演出だ。
一撃の破壊力も凄いが、これ程ビッグが立て続けに出ると、リーチ目や演出といったゲーム性も存分に堪能できる。いやぁ、いい台に座ったな。
そんな感じで、あれよあれよという間に、ビッグオンリーの10連チャンを達成。短時間で3500枚のコインを獲得。これで、本日の「逆転勝利」がほぼ確定。後はアツくならず、連チャン終了後、すぐにヤメればよい。
結局、最後に単発バケを引いて(バケは自力っぽかった)、引き戻しゾーン(?)の400ゲームを超えても当たらずに、ヤメ。ちょっと引っ張ったので、ピークの枚数よりは少し減ったものの、それでも3000枚オーバーの大量獲得である。
うーむ、旅打ち時の私の「ヒキ」は、何か特別なモノがあるのだろうか…。
ズシリと重いドル箱を担ぎ、意気揚々とシマ端のジェットカウンターに向かい、コインを流す。予想通り、3000枚チョイ獲得だった。
等価交換なら6万、6枚だと5万、7枚でも4万強だ。予想外の嬉しい展開に、自然と頬も緩む。
景品カウンターで特殊景品を受け取ると、裏手の自動ドアから、同じビル内にあった換金所に向かう。特殊景品を小窓に差し入れて、出てきた現金を受け取って数えてみると…
「あれ、何か、ちょっと少なくないか?」
3000枚も出したのに、手元には「3万ン千円」しかないのだ。これって…まさか?
そう、この店の換金率は、まさかの「7.8枚交換(或いは「8枚」かもしれない)」だった。
(換金を誤魔化された可能性もあるが)
余裕の大勝ちかと思いきや、最後の最後に、期待外れの「ドンデン返し」が待っていた。
まぁ、それでも勝った事に変わりはなく、それまでの負債を全部取り返して、さらに「お釣り」が来る収支にはなった。その夜、何を食べたかは…ちょっと思い出せない(多分、コンビニ飯)。
それにしても、この時は、名古屋駅(太閤口)での実戦が「たまたま」不調で、「たまたま」栄に移動する気になり、「たまたま」栄から金山に出向き、「たまたま」入ったホールで、「たまたま」ディーゾーンを見つけて、「たまたま」近くのお姉さんがゼロヤメしたのでハイエナしたら、「たまたま」3000枚オーバーの爆発を見せた。まさに、全てが「たまたま」づくしで、「偶然の産物」だった訳だ。
ちょっとしたタイミングのズレで、この台、そしてこの展開に出会えなかった可能性もある。だから、こんな陳腐な体験でも、「一生に一度の出会い=一期一会」と呼ぶ価値は、十分あるハズ。
因みに、金山で勝った翌日は、チェックアウト後、すぐ名古屋駅から帰京した。その後、金山・某店でディーゾーンと対決する機会もなく、都内・神奈川で遭遇するチャンスもなかった。
但し、都内に設置が無かった訳ではなく、たまたま、自分の活動エリアで見かけなかっただけ。当時の設置状況をあらためて調べると、案外と、色んなホールに導入されていた模様。
まぁ、早い話が「金山の7.8枚交換の店で、「アレ」なディーゾーンをハイエナして、約3000枚出した」だけに過ぎない。
しかし、そこには、上述したドラマチック(?)な展開が、ガッツリと凝縮されているのだ。
たった一度の出会いだったが、この時のディーゾーンにまつわる稀有な体験は、私のスロ歴において、強く印象に残るものになった。
このテの記事に「需要」は少ないかもしれない。それでも、共感して頂ける方がたった一人でもいれば、それだけで私は十分だ。
(参考)
(2000年5月、名古屋旅打ちの証…ホテル宿泊料金の「預かり証」が2枚。このホテル代と、行き帰りの交通費は、太閤口の「シオサイ30」と、金山の「ディーゾーン」が賄ってくれた。)
フィーバースパークED(三共、デジパチ)

1991年(平成3年)に三共から登場した、新要件デジパチ「フィーバースパークED」
★ドラム機(5ライン)
★賞球…7&15
★大当り確率…1/210.7
★大当り図柄…3、5、7、9、F、Sの各3つ揃い
★ドラム停止順…左→中→右
★最高16ラウンド継続
★出玉…約2400個
★保留連チャン機(攻略要素のない「たそがれ連チャン機」(無差別連チャン機)
⇒保1での仕込み連チャンあり(保1連チャン率=14.95%)
⇒自力連(保2~保4)込みの、保留連チャン率=約16.15%
1990年(平成2年)10月の「風営法規則改正」を受けて、翌91年になると、「旧要件」から「新要件」の時代に入る。デジパチやハネモノでも、最高ラウンド数や賞球数などの仕様が、大きく変容した。
(ハネモノは8Rから15R、デジパチは10Rから16R、13個戻しから15個戻し、過度な釘曲げの禁止(オマケチャッカーデジパチや一発台がNGに)、電動役物の搭載要件の緩和など)
その「新要件初期」、主力の三共が送り出したドラムデジパチが「フィーバースパーク」シリーズで、スペックの異なる「GP」「ED」「CX」が存在した。
(当時、OEM関係だった大同も、「フィーバースパーク」「フィーバースパークDI」をリリース)
当時の流れを軽く振り返ると、まず1991年初頭、三共・新要件デジパチ第一弾となる「フィーバーチャレンジI」が登場。但し、コチラはドットデジパチで、同社お得意の「ドラム機」ではない。
(兄弟機「FチャレンジII」も、その後リリース)
同年5月には、待望の三共・新要件ドラム機第一弾、「フィーバースパークGP」がデビューを飾る。また、ほぼ同タイミングで、旧要件機「フィーバーフラッシュI」の新要件版、「フィーバーフラッシュSP」も登場。
さらに数ヶ月後の同年秋、「スパークGP」の後を追う形で、「フィーバースパークED」と「フィーバースパークCX」が、同時発表された。いずれも人気があり、91年末の新装でも多くの店が新台導入したから、両機をご記憶の方は多いだろう。
スパークシリーズのうち、三共・新要件ドラム第一弾「GP」と、無制限タイプの「CX」は、当ブログでも既に紹介済み。今回は、主にラッキーナンバーや一回交換向けに出回った、「ED」を取り上げる。兄弟機の中で、もっとも設置率が高かったのがコイツだ。
(無制限主流の地域では、「CX」の方が多く出回ったケースもあるが)
本機の大当り図柄は、「数字」4種(3、5、7、9)と、「アルファベット」2種(F、S)の、計6種類。
旧要件ドラムの「レクサス」シリーズ(特にV、VIIなど)やフラッシュIと比べると、図柄のデザインは随分とシンプルであった。
まぁ、時代をさらに遡れば、「アバンテ」や「ロイヤル」などのシンプルなタイプもあったが、私の世代とは若干ずれる(アバンテは、スエイ編集長のお気に入りだったので、いつか取り上げたい)。
因みに、本機と同時期には、マルホンの新要件ドラム機「ウルトラセブン」も、「数字のみ」というシンプルな大当り図柄を採用。そういえば、旧要件末期の三共からは、「フィーバースピリットS」というのも出たが、アレも、大当り図柄が数字とアルファベットのみでシンプルだったな…。
しかし、「黒い背景に、黄色い縁どりの立体的な図柄デザイン」は、実に洗練された印象を与えた。
ドラム停止順は、左⇒中⇒右。大当り有効ラインは、上・中・下段及びクロスラインの計5本。
左・中が同図柄でリーチとなり、右ドラムは、やや速度を落として回転。さほど「引っ張る」事もなく、数秒回ってピタッと停止。再始動アクションも無く、「ビタ止まりの興奮」を味わえた。
以前も書いたが、一連の「フィーバースパーク」シリーズで、リーチサウンドと大当りファンファーレがもっとも華やかでカッコいいのが、「ED」のサウンドだと思う(あくまで個人的見解)。
配列上、ほとんどがヨコかナナメの「シングルライン」で揃うが、一箇所だけ、上段「3」と下段「F」が平行に揃う、「ダブルライン」の形が存在した。Wリーチ後、2図柄が重複して揃うので、特に期待感が倍増した訳ではない。しかし、見た目のインパクトは、それなりに大きかった。W揃いのせいで、大当りパターンは「6図柄×5ライン―1」で、29通りとなっていた。
(無制限タイプの「CX」はW揃いがなく、5図柄×5ラインで25通り)
では、なぜ「3」と「F」だけが、特別扱いされたのだろうか?特に、深い意味はないかもしれないが、私の考えでは、「三共」の「3=三」と、「FEVER」(三共の冠名)の「F」を強調したのではないか。
最高継続ラウンド数は16回。出玉も2400個程度が期待できた。初当りが「1/210.7」と高く、出玉もそれなりに稼げて、約16%の保留連チャン(自力連含む)まで付いてきた。今思えば、非常に「打ち手に優しい」スペックではなかったか。
私自身も、本機に惹かれて積極的に追っていた時期がある。向ヶ丘遊園・北口の「ニューギンザ」(現「GINZA P-style」)、新宿・西口ガード「ニューミヤコ」(閉店、跡地は「カレイド新宿」)、歌舞伎町・コマ劇前「オデヲン」(閉店、跡地は「オリエンタルパサージュ」⇒「マルハン」)、歌舞伎町あずま通り「ニューメトロ」(閉店、跡地は岩盤浴「OSSO」)、新宿・東南口「トーオー」(閉店、跡地はパチンコ「ニューアサヒ」⇒現「ムラサキスポーツ」)など、対峙したホールは数多い。
ただ、確率の甘さと連チャン率の高さが、ホールで「シブ釘化」を招いたのも事実だ(特に、繁華街で「回収」傾向にあった新宿は…)。
さて、ここからは、本機の「大当り判定」や、「連チャンシステム」について、少々説明を加えたい。
なお、同時発表された無制限用の「CX」も、ほぼ同一の仕組みだったが、大当り確率が異なる。
本機は、兄弟機「CX」と同様、大当り判定に「二段階抽選方式」を採用。
なお、シリーズで最初に出た「スパークGP」は、二段階抽選でなく「一発判定方式」を採っており、後発の二機種とは、「毛色」が異なる。登場時期の違いが、判定方式にも如実に表れている。
一次当選率は、「4/126」(=1/31.5)。二次当選率は「29/194」(≒1/6.7)。
よって、トータルの大当り確率は、4/126×29/194≒1/210.724(約1/211)となる。
(「CX」は、一次が「4/205」(=1/51.25)、二次が「25/125」(=1/5)で、大当り確率は「1/256.25」(約1/256)と低め)
次に、本機の大きな特徴だった、「保留玉連チャン」のカラクリについて。
やはり、本機で大当りが来た後は、毎回、連チャンを期待できるのが楽しかった。
連チャン方式は、大当り終了後の保留1個目が、一次抽選「フリーパス」となり、二次抽選の「29/194(14.95%)」さえ当選すれば、大当り(連チャン)となる仕組み。
よって、保1連チャン率は、二次抽選率と同じで、約15%となる。
(「CX」は、二次当選率が「25/125(1/5=20%)」なので、保1連チャン率20%)
なお、保2~保4に関しては、意図的なカラクリはなく、「自力連チャン」しか起こらない。
それでは、どうして大当り後の保1は、必ず一次抽選をフリーパスしたのだろうか?
以下は、かなり専門的な内容を、「文系人間」の私なりに咀嚼(そしゃく)して、解釈したもの。
その為、言葉足らずで、不正確な表現も含まれると思う。その点は、どうかご了承願いたい。
まず「前提」として、本機は、「連チャン機」と「非連チャン機」にいう風に、性格がハッキリ分かれる。
これは、電源を入れた瞬間に台の性格が決まり、一旦決まると、電源を切るまで変わらない。また、何度電源を入れ直しても、「連チャン機は連チャン機のまま」「非連チャン機は非連チャン機のまま」になる、という特徴がある。
この前提のもと、本機の保1連チャンには、「大当りフラグ」と呼ばれる、プログラム内の状態コードが絡んでいた。
大当りフラグは、二次抽選に進むか否かを判断する「一次通過フラグ」と、最終的な大当りか否かを判断する「ハズレフラグ」の2つを含む。
「ハズレフラグ」で当否を判断するのは、妙に思えるかもしれないが、本機は「ハズレフラグが「オフ」なら大当り、「オン」ならハズレ」という仕組みになっている。
大当りフラグが「オン」か「オフ」かによって、内部状態は以下のようになる。
・大当りフラグ「オン」…一次通過フラグ「オン」、ハズレフラグ「オフ」(大当り状態)
・大当りフラグ「オフ」…一次通過フラグ「オフ」、ハズレフラグ「オン」(ハズレ状態)
一次抽選に当選すると、大当りフラグ「オン」となり、大当りの条件がいったん整う。
一次抽選でハズれると、大当りフラグは、現状のまま変更されない。通常は「オフ」の状態。
一次抽選が終わると、再び一次抽選の結果を参照。但し、参照するのは「一次通過フラグ」だけで、「ハズレフラグ」はチェックしない。
つまり、一次通過フラグが「オン」ならば、自動的に二次抽選へ行き、「オフ」ならハズレ処理に行く。
二次抽選に当選すると、大当りフラグは「オン」のまま変わらず、大当りセットの処理に行く。
二次抽選でハズれると、大当りフラグが「オフ」に切り替わり、ハズレ処理に向かう。
大当り消化中は、大当りフラグ「オン」のまま、変わらない。
大当たり終了時(パンク含)、大当りフラグを「オフ」に戻す、事後処理が行われる。
(そうしないと、保1消化時に、大当りフラグが「オン」のまま残ってしまうから)
但し、これは「非連チャン機」に限った事で、「連チャン機」の性格を持つ台では、この事後処理が有効に行われず、大当りフラグ「オン」の状態のまま、保留消化に移る。
保1消化時は、まず、普通に一次抽選が行われる。ここで当れば何の問題もないが、一次でハズれてしまっても、無条件でフリーパスとなり、二次抽選に行くという「怪現象」が疑問となる。
先述の通り、「連チャン機」の場合、大当り終了時の事後処理に失敗する為、大当りフラグは「オン」のままだ。その状態で一次抽選に外れても、「一次通過フラグ」はまだ「オン」になっている。したがって、保1の一次抽選の結果がどうであれ、二次抽選に行く事ができるのだ。
もし、一次抽選に外れた時、一次通過フラグを「オフ」にする積極的な処理があれば、こういう事は起こらない。しかし、そういった処理はなく、現在の一次通過フラグを参照するに過ぎない。その為、「連チャン機」で大当りフラグが残った状態では、保1消化時だけ、一次通過フラグが生き残るのだ。
そして、フリーパスで到達した二次抽選で、「29/194」の振り分けにさえ合格すれば、めでたく「保1連チャン」が発生する。
だから、保1連チャン率は、二次当選率と同じで、「29/194=14.95%」となる訳だ。
一方、保1で二次抽選に外れた場合、大当りフラグを「オフ」にする積極的な処理が、今度は間違いなく実行される。
いったん「オフ」になってしまえば、再び一次抽選に当選しない限り、大当りフラグが「オン」に切り替わる事はない。
よって、大当り後の保2以降については、常に通常確率の「1/210.7」(二段階抽選)で、大当りの判定が行われる。
それでは、なぜ、同じ機種にも拘らず、「連チャン機」と「非連チャン機」に分かれたのだろうか?
本機は、電源オンにした直後、「RAMクリア」と呼ばれる初期化作業が行われる。
本来なら、この時、大当りフラグが書かれた領域(2進数で「8ケタ」の数列)も、綺麗サッパリと初期化、つまり「ゼロクリア」されてしまう。
ところが、大当りフラグが書かれた領域は、プログラムの「後方」に位置するから、初期化の順番が「後回し」になる。その為、RAMクリアの完了前にリセット信号が入ってしまうと、その領域の初期化に失敗して、大当りフラグの部分に、初期化前の古い数値、いわゆる「キズ」が残る。具体的には、8ケタ(2進数)の数列のうち、一番上と一番下の各ケタに、計2つの「キズ」がつく。一旦ついたキズは、電源を落さない限り、永遠に残りつづける。したがって、この台の大当りフラグは、常に「キズ」の付いたフラグとなる。
要は、初期化失敗によって出来た大当りフラグの「キズ」が、大当たりが終了してフラグを「オフ」に戻す大切な「事後処理」を、思いっきり妨げていた訳だ。
しかも、本機の場合、高確率で電源オン時の初期化に失敗するので、ホールにある大半の台は、「連チャン機」の性格を持っていた。
だが、中には、電源を入れれば、必ずRAMクリア、つまり初期化に成功する、「優等生」の台も含まれた。こういう台は、大当りフラグに「キズ」が残らず、大当り終了後も、フラグを「オフ」に戻す事後処理が正常に行われる。よって、保1消化時も「一次フリーパス」とはならず、通常通り、一次と二次の双方に当選しなければ、大当りとならない。
したがって、「ホールで幾ら打っても連チャンしない台」は、その性格が「非連チャン機」だった可能性が高く、「初当り確率1/210.7のノーマル機」となる。一方の「連チャン機」は、初当り確率が同じで保1連チャンも付いて来たから、非連チャン機より圧倒的に甘かった訳だ。また、ホールで一度保1連が出れば、それ即ち「連チャン機の証」となったので、そちらを追えば、常に連チャンの期待が持てた。
なお、ここまで書いた保1連チャンの特徴は、兄弟機の「CX」も全く同じである(大当り確率を除き)。また、同時期に「二段階抽選」を採用した「三共・保1連チャン機」の多くに、この事は当てはまる。
実は、この保1連、旧要件デジパチの名機「舞羅望極II」(1990年、平和)の連チャンシステムを、見事に「踏襲」している。当時の三共・開発陣が、「極II」の保1連の「カラクリ」に影響を受けていたであろう事は、想像に難くない。特に、「万人が平等に連チャンして、攻略が効かない」という点が、メーカー側にとって大きな魅力だったと思う。
まぁ、文系人間の私が、あまり深く突っ込むのもアレだから、今回は、この辺りで終わりたい。
CR撃墜王(西陣、デジパチ)

年末進行の多忙により、更新がやや遅れてしまったが…
今回は、1995年(平成7年)に西陣から登場した、CRデジパチ「CR撃墜王」について。
某・人気アニメ映画「紅の〇」などを彷彿とさせる、プロペラ戦闘機がモチーフ(黒いサングラス姿のパイロットの風貌も、それっぽく見えた)。
また、デジタル回転音や大当りBGMは、有名な「サン〇ーバード」のテーマを思わせた。
まぁ、過去の「名作」から、あれこれと「影響」を受けるのは、当時のパチの定番でもあったが…。
それでも、戦闘機が左右に飛び回ったり、その下を流れるデジタルが、奥から手前にグングンと迫ってくるアクションには、独特の「味」があった。
リーチアクションは「3パターン」とシンプルだったが、ノーマルでも多少は期待が持てたり、激アツとなる「SPアクション」もあったりして、退屈せずに楽しめた。
スペック的に見ると、当時のCRで流行りだった「フルスペック」(確変突入率1/3、プラス2回ループ)とは違って、同じプラス2回ループでも、突入率(継続率)「4/19(1/4.75)」と、低く抑えてあった。
その分、初当り確率はCR機にしては高めで、CRに有りがちな1000G超えの「特大ハマリ」は、割と喰らう機会が少なかった。
また。設定が3段階あった為、高設定台に座れれば、自然と勝つチャンスが広がった。その為、釘チェックに加えて、シマの挙動をよく観察して、初当りが多い台を探す事も肝要となった。
さらに、確変終了後は、必ず「200回の時短モード」に入る仕様。「狭き門」の確変に、いったん突入してしまえば、ワンチャンスで爆裂する可能性も秘めていた。
一方、設定やヒキ次第では、「単発当り」のみがポンポンと繋がって、確変ゼロで勝つ事もあった。
都内での設置率は高めで、大きな繁華街のホールを回れば、どこか1軒は入っている感じだった。馴染みの「新宿」も同じで、日拓、オデヲン、ジャンボ、アラジン、メトロなど、本機を導入した店舗は多い。特に、東南口の「平和」(2013年閉店)は、2000年以降も「みなし機」として、本機を置き続けていた(但し、ヘソ釘は…汗)。
(基本スペック)
★ステレオスピーカー付きの真っ赤な新枠、「アルファ」を本機で初採用
(旧枠は、「CR花満開」等に使われた「Y&O枠」)
⇒アルファ枠は、後続の「CRヤッタルデー」にも使われたが、何故か、定番となる事なく、あっという間に姿を消してしまった。
★メイン画面は、6インチの小型CRTモニター(ブラウン管)、液晶より鮮明な表示が可能。
★天下にワープの入口有り。ここに入ると、画面下のステージ上に出て、手前のヘソに転がる。
(ステージ⇒ヘソの入賞率は、釘や「ネカセ」で変化した)
★賞球…5&10&15(ヘソ5個戻し、アタッカー15個戻し)
★大当り確率(通常時)…設定1=1/275 設定2=1/315 設定3=1/350
★最高16ラウンド継続(出玉=約2300個)
★デジタル停止順…左⇒右⇒中
★図柄
・左右…緑の「0、2、4、6、8、9、A、B、C、D、E」、赤の「1、3、5、7」 (計15図柄)
・中…左右と同じ15図柄に加えて、緑の「1、3、5、7」もアリ (計19図柄)
★大当り図柄…計19通り
・赤の同色揃い(4通り)
・左右赤で、中のみ緑の色違い(4通り)
・緑の同色揃い(11通り)
⇒左右で「1、3、5、7(赤)」がテンパイすると、中デジの大当り図柄は「赤」(確変)「緑」(単発)の2通りあるので、事実上の「ダブルリーチ」となる。
★全19図柄中、「1、3、5、7」の赤揃いで当ると、プラス2回の確変に突入
(突入率4/19、ループあり)
⇒赤「1、3、5、7」の大当りは、中デジが「赤」か「緑」かで、雲泥の差となる。確変リーチ時は、否が応でも中デジの行方に注目してしまうが、大抵は「緑」の方が揃ってガックリする。
⇒確変中は、デジタル画面に「高確率中」の表示が出現。
★大当り確率(確変中)…設定1=1/91.7 設定2=1/63 設定3=1/50
⇒確変中は、通常時と逆に、低設定ほど高確率となり、次の大当りが早く来やすい。よって、確変中の挙動から、ある程度は設定を読めた(確変中にハマり易いほど、設定1を期待)。しかし、肝心の確変に入るのが大変。
★確変終了後は、必ず200回の時短に突入
CRならではの「プラス2回ループ」爆裂に加えて、現金機で注目された「時短」(「お助け連チャン」とも呼ばれた)も搭載した本機。確変突入率の低さをカバーする役割。
⇒200回以内の「引き戻し率」は、最低の設定3でも43.45%。設定1なら51.74%とハイチャンス。ループ率が「4/19」と低く、ワンセット終了が多かった本機だが、200回の引き戻しゾーンで再び確変を引くこともあり、ツボにハマれば、フルスペックに負けず劣らずの爆裂ぶりを見せた。
★小デジ変動時間…通常時=約29秒(一定)、確変中/時短中=約1秒~約6.1秒(不定)
(小デジ始動時の保留点灯数や始動タイミングにより、変動時間は1秒~6秒の間で変化)
⇒左右の肩チャッカー(「GO」)通過で、天下の7セグデジタル(1桁)が始動(保留ランプ4つ付き)。「7」で当選、ヘソ下の電チューが開放する。
★小デジ当選率…常に1/4(通常時、確変中、時短中の区別なし)
★電チュー開放時間…常に3.1秒(又は2個入賞)
★通常時の「止打ち攻略」について
上記のように、小デジタル確率が「常に1/4」、電チュー開放時間が「常に3.1秒」、そして通常時の変動時間が「約29秒」と一定だった事から、電チュー開放に合わせて数発を打ち出す、通常時の「止打ち攻略」が編み出された。
本機よりも前に出た、ニューギンの「エキサイトレディ―2」(業界初の「時短デジパチ」)でも、やはり止打ち攻略が発覚して、「通常時、電チューの開放タイミングを狙えば、1000円で80回もまわる」と、必勝G誌で騒がれた。同誌はEレディの止打ちを「昇天打法」と呼んだが、後に出てきた本機の止打ちについては、台のイメージに合わせて「大当り迎撃打法」と命名した。
止め打ちの方法はシンプル。左右の肩チャッカー(小デジ用の「GO」チャッカー)を通過したら、手元のストップボタンで打ち出しを停止する。同時に、秒針付きの時計※などで、カウントを開始。肩チャッカー通過から27秒経ったら、玉を「8発」だけ打つ。但し、小デジがハズレた時点で、8発未満でも即、打ち出しは停止。小デジが当った場合、キッチリ8発打って打ち出しをヤメる。以後は、「小デジ始動開始から27秒打たずに待機⇒27秒後に8発打ち出す」を繰り返す。これで、無駄玉が大幅に節約される格好だ。
※盤面のランプ点滅を目安にすると、デジタルが回っている時と停止中で点滅タイミングが変化する為、タイミングがとりにくい。
なお、止め打ち実行中、打ち出した玉が天下のワープ入口に入ってしまうと、ヘソに届く時間が不安定となる。その為、ストロークは弱めにして、ワープを避けて打ち出すのが効果的、とされた。
しかし、この止打ち攻略には、大きな問題点があった。確かに、上記手順を使えば、「1000円当りの回転数」は、普通に打つよりも多く稼げる。しかし、「27秒」も待って「8発」だけ打つのは、非常に根気のいる作業。しかも、同じ時間内に回せるデジタル回転数は激減する為、「時間効率」の面で大きなハンデがあったのだ。「理論上は効果があっても、実戦的ではない」との批判が多かった。
★リーチアクションについて
本機のリーチアクションは3パターンのみ。「シューティングリーチ」(=ノーマルリーチ)と、SPリーチの「マシンガンリーチ」、そしてマシンガンから発展する「アクロバットリーチ」の3種類。
・シューティング(ノーマル)…左右テンパイ後に画面が赤くなり、戦闘機が中デジタルを機関銃で狙い撃つ。中デジは高速回転とスローを繰り返すが、スローになるのは、リーチ図柄の2コマ手前から1コマ先まで。1周目で当る「ショート」と、2周目に当る「ロング」がある。
・マシンガン…通常、奥から手前に「平行移動」するだけの左右デジタルが、いきなり「縦回転」(縦スクロール)を始めると、このリーチに発展する。左右テンパイ後に、画面が黒く変化。リーチ中に、戦闘機が中デジを狙撃するアクションは、シューティングと共通。
・アクロバット…マシンガンから発展。中デジが一旦ハズレで止まると思いきや、戦闘機が急下降⇒急上昇を見せる。同時に、全図柄が上に持ち上がった後、左右の図柄が「パラシュート」付きでゆっくりと降下。同時に、中デジは縦回転でスクロールする。高確率で大当りに繋がるゲキアツリーチ。
なお、確変中は、リーチアクション無しで、いきなり揃う事が多い。
上記リーチの信頼度は、設定や図柄によって異なる。全リーチにおいて、(1)高設定ほど信頼度がアップ、(2)確変図柄リーチの方が、単発リーチより信頼度が高い。
以下は、平均的といえる「設定2」のリーチ信頼度を示したもの。
ノーマル…確変⇒5.3% 単発⇒2.57%
マシンガン…確変⇒7.62%、単発⇒3.73%
アクロバット…確変⇒91.9%、単発⇒85%
(リーチ出現率は、言わずもがなだが、ノーマル>マシンガン>アクロバットの順となる)
★故・田山幸憲プロと本機との関係
※参考文献…名著「パチプロ日記」(V)(VI)(VII)(田山幸憲著、白夜書房)
1996年~1997年(平成8年~9年)の桜新町「H店」※(パチーノヒノ)時代に、田山さんは本機と対峙した事がある。但し、舌ガンの手術直後で、体調的には、かなりキツイ時期であった。
※H店は、地下がCR機、地上が現金機とパチスロ
H店での遭遇当初、本機は、田山さんにとって「何だかよく分からない台」或いは「通路を引き返す際の風景」程度の認識に過ぎなかった(その頃のメイン機種は、同じCR機でも、「CR球界王EX」「CRバトルヒーロー」「CR黄門ちゃま2」といった辺り)。
その後、常連仲間の「モデル・オノ」氏や、夫人の「マダム・オノ」女史などが調子良く出すのを見て、段々と「守備範囲」にしていったようだ。それでも、さほど「積極的に追っていた」様子はなかった。
そんな中、とりわけ印象深いのが、H店の撃墜王のシマ、左から三番目の「78番台」だ。
田山さんは、この台を「後学のために」初めて打ってみたところ、一度も確変を引かず、10回出した大当りが全て単発だったが、それでも計2万円の勝ちをモノにする。その翌日、再び同じ台にて挑戦したところ、またも確変に巡り合えず、計8回の当りはいずれも単発で、結果は「チョイ勝ち」だった。
つまり、2日続けて本機を実戦したが、「18回連続」で単発を引いてしまった訳だ。幾ら、突入率「4/19」と低くても、これではちょっと悲しい。だが、収支でいえば「2戦2勝」なので、初当りのペースは決して悪くなかった。もしかして、二日間とも初当りの甘い「設定1」の台に座って、たまたま確変が引けずに、「ノーマル然」とした出方になったのではないか。
因みに、その日の実戦では、途中で溝の口B店(PSビッグトップ)時代の常連であった「ヤカン君」が久々に顔を出したり、田山さんが打っている撃墜王のシマに「モデル・オノ」夫妻がやって来て、オノ氏がお座りたったの3回転で確変を引いたり、ある熱心なファンが田山さんにサインを貰いに来たが、用紙に「田山」と書いた途端に大当りしてしまい、サインが名字までしか書けなかったりと、様々なエピソードがあった。
日記を読む限り、その後、本機との実戦場面はあまり出て来ない。実際、「オレは撃墜王を打って二十三回くらい当てているが、一度も確変を当てたことがない。ついにそのまま、こいつとはお別れする事になりそうだ」と述べている。
その間、H店における本機の「シブ釘化」も酷かったようで、田山さんが朝一に地下でCR機の釘を見て回る際には、必ずと言ってよい程、撃墜王のシマが「とても打てそうにない」(シメシメルックな)状況である旨を、嘆くがごとく報告していた。
(「その奥の黄門ちゃまと撃墜王は無用の長物。年が改まっても、クギの方は一向に改まらない。過去の栄華を胸に秘め、ただひたすら死期を待っているだけ」など)。
★兄弟機について
「撃墜王DX」(現金機デジパチ、1995年登場)
大当り確率1/230の「2回ワンセット」機(確変デジパチ)。
全19図柄中、「1、3、5、7」の赤数字で当ると、次回までの小デジ確変(ループなし)に突入。この時、小デジの大幅な時短が働く為、出玉をほとんど減らさずに、次回大当りをゲットできる仕組み。一方、それ以外の15図柄で当ると、次回までの小デジ確率アップはあるが、肝心の「時短」がなく、確変中の玉減りが大きい(止め打ちでの対処法もあるが…)。また、コチラはCR版と違って、ノーマルリーチからアクロバットリーチに発展する事がある。
汽車ぽっぽII(三共、ハネモノ)

1990年(平成2年)に三共から登場した、旧要件ハネモノ「汽車ぽっぽII」
★賞球…オール13
★ハネ開閉時間…オトシ0.35秒×2(左右オトシ入賞で、ハネは2回開く)
★ヘソチャッカー入賞で、ヤクモノの汽車が常時始動を開始(ヘソはハネ始動チャッカーではない)
★継続ラウンド数…最高8ラウンド
★大当り中、ヤクモノに最大5個貯留(5カウントで貯留解除)
盤面中央でクルリと回る、赤い汽車のヤクモノが印象に残る。ヘソとオトシにも、一風変わった特徴を持った本機。
90年秋頃~翌91年初頭に、小田急線・下北沢駅裏手の「下北レジャー」というパチ屋で実戦。
(90年代半ばに閉店。その後、跡地では「カレイド下北」が営業開始。現在に至る。)
在りし日の「下北レジャー」…すりガラスの自動ドアの正面がパチンコフロアで、左の階段を下りた地下がパチスロだった。当時、本機や「パニックコスモ(コスモII)」(三洋)を打ちに通った。地下では「ドリームセブン」(高砂3-1)、「ムサシ」(パイオニア2-2)と戯れた。91年に「ワイルドキャッツ」(アークテクニコ3-1)の貯金Verが入った。
因みに、下北レジャーのすぐ近く、小田急の踏切を渡った目の前には、「ワールド」という別のパチ屋があった。ワールドでは、「エンタープライズ」(三共)や「魔界組」(西陣)といった、旧要件ハネモノを打った事を思い出す。
夜、ワールドからレジャーに「ハシゴ」すべく踏切待ちをしていると、レジャーが入った線路向かいのビルの上に、「下北レジャー」と地味に書かれた屋上ネオンが見えた。一方、レジャーからワールドにハシゴする時は、踏切の前で派手に光る、「ワールド(WORLD)」のネオンが、嫌でも目に入ってきた。当時は、こうしたネオン看の類にも、味わい深い「情緒」があったと思う。
在りし日の下北沢「ワールド」…1Fがパチ、2Fがスロ。スロの実戦機種は「アニマルG」(アークテクニコ、2-1)、ワイルドキャッツ(貯金)、「ミスターマジック」(サミー3-2)など。ミスマジは、クローズとなるまで置いていたと記憶。跡地は、現在「大庄水産」になっている。
また、当時の下北沢界隈では、「ミナミ」「グリンピース下北沢店」「富士ホール」「ゴールデン会館」といったパチ屋・スロ屋も営業。グリンピの「ホワイトアラジン」(初代アラジン、白パネル)やスーパーウィンクル、スーバニが懐かしい…。上記ホールの中で営業を続けるのは、今や「ミナミ」のみ。
そういえば、下北沢駅周辺は、近年再開発が進み、小田急の駅は地下化され、シンボリックな駅前の踏切も消えるなど、1990年当時とは趣きが大きく変わっている。平成初期の当時を知る者からすれば、こうした変貌はちょっと寂しい気もするが、これも時代の移り変わりだから、仕方ない。
おっと、下北沢界隈の思い出にかまけて、本機の説明をすっかり忘れていた。
ヤクモノは大きく見れば二段構造。上段が平坦なステージ、下段は円型の線路を模したステージ。
「線路」といっても、実際にゲージは敷かれておらず、線路や風景の「イラスト」のみ。
で、その線路の上にあるメインヤクモノが、半円状にカーブした、「赤い汽車ぽっぽ」である。
(構造上、若干見づらいのが難点)
外観は「グリコのおまけ」のような華奢な作りだったが、そのチープさが、却って味わい深かった。
この汽車も「一層」にカウントすれば、本機のヤクモノは「三層構造」となる。まぁ、円形のステージと汽車をまとめて、「下段」と考える事も出来よう。
因みに、本機と同時期には、ライバルメーカーの平和も、「汽車ポッポDX」という旧要件ハネモノを出していた。単なる偶然とは思うが、同じモチーフが思いっきり「カブった」格好だ。
「汽車ポッポDX」では、ヤクモノの汽車がデンと正面を向いていて、前面の蓋がパカッと開いたり、汽車が奥から手前に出てくるなどの特徴があった。一方の本機は、円型の線路を模したステージの真上を、赤い半円状の汽車が、反時計方向にクルリと回る。同じ「汽車」でも、両機の構造やゲーム性は、全く違っていた。
そういえば、子供時代、地元近くに「汽車ぽっぽ」という和風民家型のレストランがあって、注文した料理や飲み物を、SL機関車のミニチュア模型(といっても結構大きい)が、テーブルまで運んできてくれた。本機を見ると、このレストランの事を自然と思い出す。
ところで、「半円状にカーブ」の表現では、本機のヤクモノをイメージしづらいかもしれない。ザックリ言えば、「ルーレット」の半分が欠けていて、残る半分が汽車の形をした、「水平回転体」である。
先頭が煙突付きの汽車で、その後ろには一応「運転席」もあって(運転士のイラストがある)、最後尾が石炭を積んだ貨車(=石炭車)。
「線路に沿ってカーブした、半円状の長い汽車型回転体」といえば、イメージして頂けるだろうか。
汽車は、普段停止したままだが、(1)ハネ開閉後(オトシ入賞時)、(2)センターチャッカー入賞後、(3)大当り中の貯留解除後に限り、円形の線路(ステージ)上を回転する。
(1)は2周で止まってしまうが、(2)は大当りするまで延々と回り続ける。また、(3)は、ラウンド終了まで回っている。
左右オトシ入賞で、「遮断機」を思わせる小さいハネが、「0.35秒」の素早い開放を2回繰り返す。
この時、踏切特有の「チンチンチン」という警告音が鳴ったハズ。
さらに特筆すべきは、左右オトシが「2回開きチャッカー」という点だ。「オトシ=1回開き」が定番のハネモノで、二回も開けば何やら得した気分になるが、その理由は、読み進めれば判るだろう。
一方のヘソ(センター)は、「チャンス」と表示された特殊なチャッカーで、ここに入賞しても、ハネは開かない。
しかし、この「チャンス」に入賞すると、停止中だった赤い汽車が、通常時にも拘らず、反時計回りに動き出すのだ。
つまり、ヘソのチャンスチャッカーは、「ヤクモノの動きを変える」という、重要な役割を持っていた。
本機に1チャッカーはなく、ハネ開放時は必ず「2回」開く仕組み。ヘソ入賞でもハネが開かない分、両オトシを2回開きにした訳だ。ただ、このスペックが「シブ釘化」につながったのも事実。
「左右オトシが2回開きで、ヘソがチャンス(ヤクモノの動きが変化)」というチャッカーの仕組みは、三共から同年登場した、ハネモノの先行機「レオパードII」を継承したもの。
レオパードIIは、通常時、ヘソの「ACT」チャッカー入賞で、ヤクモノ上部の山型プレートが反転し、さらに左右の砲台も停止して、V獲得の大きなチャンスとなる。但し、その後オトシに入ってハネが開くと、ヤクモノの状態も元に戻ってしまう。
一方の本機は、チャンスに入賞して汽車が動き出せば、大当りが来るまでの間、ずっと回り続ける。つまり、「常時回転」の状態になる訳だ。ヘソ入賞の効果が、レオパードIIよりもグレードアップしていた。
しかも本機は、汽車が「常時回転」している時に、とりわけ大当りし易い構造だった(理由は後述)。
つまり、チャンス入賞時は、文字通り、大きな「チャンス」となったのだ。
さらに、途中でタネ銭が尽きたり、ジリジリした展開に嫌気がさしたりして、汽車が回ったままヤメる客もいたから、ハイエナが効果的だった。
だが、時には、そのハイエナが仇となり、見事な「ダマシ釘」に引っかかる事もあった。ヘソのチャンスにはよく入っても、肝心の始動チャッカー(=左右オトシの2チャッカー)にサッパリ入らず、さらに寄り釘まで酷く、ヤクモノにさっぱり玉が入ってくれないケースだ。
こんなイジワル台に捕まってしまうと、「汽車が回っているから」と止められなくなり、ついつい投資も嵩んで、ミイラ取りがミイラになったりした。まぁ、「客に金を使わせるのが巧い台」だったともいえる。
もちろん、大当りのポイントが「チャンス入賞」という点は変わらないから、本機を打つ上で、ヘソ釘チェックは「最重要事項」であった。
おっと、始動チャッカーの話だけでは、記事が偏ってしまう。ヤクモノ内の「玉の動き」も説明しよう。
本機の大当りパターンを簡単にいえば、「上段から下段奥に落ちた玉が、反時計周りに回る汽車の力で手前に送られて、V手前のゼブラゲートを通り抜けて、そのままVに入れば大当り」となる。
因みに、「ゼブラゲート」とは、円型ステージと手前Vゾーンの間にある、黄・黒の二色線で囲まれたゲートの事だ。下段奥から手前に転がった玉は、このゲートの間を通過しないと、Vには入らない。但し、ゲート下の両脇には大きなハズレ穴があって、大半が行く手を阻まれてしまう。
逆に、ゼブラゲートを抜ければ、大チャンスとなる。但し、クセ悪台だと、ゲートを通過しても、最後にVの左右に蹴られてしまう、口惜しいパターンが多発した。まぁ、大当りまでには、いくつもの「関門」があったのだ。
ところで、先述の通り、本機はヘソの「チャンスチャッカー」に入賞すると、大当りし易い構造だった。
というよりも、逆に、チャンスに入らないと、なかなか大当りしなかったのだ。クセ良台ならともかく、普通の台では(もちろんクセ悪台も)、汽車が止まった状態は「ローチャンス」。特に、ハネ開閉1回目に拾われた場合は、ほぼ「ノーチャンス」となる。
一方、ヘソのチャンスに入って、汽車の「常時回転」がスタートすると、一転して、大当りの期待度はグンと高まる。
もちろん、Vを1回外したからといって、汽車の常時回転が止まる事はなく、大当りになるまで回転は続く。
但し、この状態でヤクモノに入れて、なかなかVに決まらない台は、致命的なクセ悪台となる。
それでは、なぜ、チャンスに入賞すると、普段よりも大当りし易くなったのだろうか?
その理由は、ヤクモノの汽車が「常時停止」か「常時回転」かによって、下段ステージ奥に落下する玉と、汽車が近づくタイミングが、大きく違っていたからだ。
チャンス未入賞時、ヤクモノの汽車は「常時停止」しているが、オトシ入賞でハネが2回開くと、反時計周りに回転を始める。汽車の回転周期は約3秒で、2周回ると再び停止。
しかし、汽車が回り始めるタイミングがいつも一定で、回転周期も「約3秒」と一定な上、下段に落ちるポイントも似通っていたから、落下した玉と汽車の「位置関係」も、大体が同じになったのだ。
この時、多くの玉が、反時計回りする汽車の「前面」に押し出されて、左奥から手前ゼブラゲートに向かって転がる。だが、ゲート下には、左右に大きな「ハズレ穴」があって、押し出した玉の大半が、左のハズレ穴にとられてしまう。
たまに、ハズレ穴をクリアしてゲートを通り、そのままVに飛びこむこともあったが、よほどクセが良くないと、そうそう決まるパターンではなかった。
ここで、一応確認しておくが、下段のハズレ穴は、「ゼブラゲート下の左右」と、「Vゾーン両脇」の計4か所もある。Vへの道のりが決して甘くない事が、お判りだろうか。
一方、チャンスチャッカー(ヘソ)入賞後は、汽車が「常時回転」を開始するから、下段に落ちる玉と、汽車との位置関係も、一定とはならない。汽車が常に回っている以上、ナキのタイミングによって、大きくバラつくのだ。
この時も、落下した玉が先頭車両に押し出されてしまえば、大半がゲート脇のハズレに入るから、大当りのチャンスは低い。
だが、先頭部ではなく、半円状の汽車の「中央」付近で玉を拾った場合、V獲得の大きなチャンスとなる。この中央部には、内向きの「傾斜」が付いていて、乗った玉を真っ直ぐ手前のゼブラゲートに送る、絶妙な「スロープ」と化した。
スロープに乗った玉が、そのまま手前のゲートを通り抜ければ、V入賞の可能性は高い。このパターンは、チャンス未入賞時だと、汽車の回転周期が合わない為、実現しづらいのだ。なお、クセ悪台では、このパターンからでも、V両脇に外れる事が多い。
なお、ヘソ未入賞時(汽車は常時停止)でも、以下の場合は、スロープに乗る事があった。
(1)上段ステージで、玉が玉突きしたり遊んだりして、下段への落下タイミングが遅れた場合
(2)オトシに「連続入賞」して、汽車が回っている状態で、追加玉がヤクモノに入った場合
さらに、汽車の最後部の「石炭車」も、大当りする上で大きなポイントとなった。
最後部に拾われると、石炭車の荷台部分に玉をいったん貯留する。貯留された玉は、反時計回りで手前に戻ってくるが、途中でこぼれ落ちる事なく、荷台に1個貯留されたまま、ゼブラゲートに到達する。そして、ゲートの間から「コロリ」と手前にこぼれると、そのままVを目指すのだ。
このパターンも、汽車が「常時回転」しているがゆえに訪れやすいチャンス。ヘソ未入賞時だと、汽車のタイミングがなかなか合わずに、実現しづらい(但し、不可能ではない)。
なお、1個貯留すべき最後部の石炭車に、たまに「2個貯留」する事もあった。しかし、この場合、却って玉突きが起こる為、両方共にVをハズしやすい。
ともかくも、大当りするか否かは、汽車が周回するタイミング次第。「中央のスロープ」や「後部貯留」を経由するのが、V入賞の「王道」パターンで、チャンス入賞で汽車が回り続ける状態では、王道パターンでVを射止める確率が、大幅にアップしたのだ。
なお、その他の大当りパターンには、下段奥に落ちた玉が、汽車をかわして手前に転がり、ゲート手前のハズレも回避して、Vに入るパターンがある。但し、これはレアなパターン。
かくして、Vを射止めると、汽車が停止した状態で、大当りスタート。この時、汽車はゲート下にある左右のハズレ穴を塞いで停止するから、下段ステージ奥に複数貯留するようになる。
なお、大当り開始と同時に、上段奥に「駅弁小僧」と称する、妙なキャラが出現。ハネ2回開閉まで上段に貯留するが、すぐ下段貯留に切り変わる。この動きが、特にV継続に影響した訳ではない。
最大貯留は5個。上段奥の二穴についたセンサーが5カウントした瞬間に、汽車が再び動きだして、貯留解除となる。正しくは、「最大4個貯留から、一瞬5個貯留となり、すぐ貯留解除」だ。
解除された玉は、奥から押し出されるようにして、、一斉に手前へ転がる。そのままゲート下のハズレに入る玉も多いが、そのうち1個がハズレをかわして、Vまで到達すればOK。貯留が5個あれば、6割以上の確率でV継続となった(ここでも、クセが継続を左右)。
貯留解除でVを外した場合、チャンスチャッカー入賞後と同様に、汽車は「反時計回り」を続ける。
「5カウントで貯留解除、10カウントでパンク」なので、残るチャンスは5個となる。
但し、汽車の常時回転中は、「スロープ経由」や「後方貯留」でVに入り易いから、貯留解除後の「復活」も多く、V継続率は悪くない。完走時の出玉は、800個程度。
オール13で、通常時の玉持ちも何気に良く、当初は「勝てる」印象が十分にあった本機。だが、日を追うごとに、オトシもヘソもシブくなり、やがて、サッパリ動かない「展示機関車」になってしまった…。
しかし、思い返せば、90年当時の旧要件ハネモノは、「ハマりを喰らう」といっても、せいぜい数千円程度。万券が吹っ飛ぶことなど、余程アツくならない限り無かった。90年夏、JR大宮駅のパチ屋で、クセ悪の平和「たぬき丼」を打ち、8000円負けたのが、旧要件ハネモノでの最大負け額。あの痛恨の敗戦は、その後のハネモノの立ち回りで、大きく役立った。
しかも投資は100円から可能で、「2.5円・4000発打ち止め」なら、ポッケに残った一枚の小銭が、1万札に化ける事だって、当時は普通にあった。
まさに、「ローリスク、ミドルリターン」の時代。
それに飽き足らなければ、オマケチャッカー付きのノーマルデジパチ、権利物、保留連チャン機、さらには一発台…と、他の「オプション」を選べばよかった。
換金率も千差万別で、自分の活動地域でも、「2.2円」で換金が低い分、釘が甘い店は多かった。
ひょっとして、パチンコの「遊技性」は、25年前の1990年の時点で、既に「完成」を見ていたのではないか?
実際、私にとって、最も「郷愁」が感じられ、かつ充実した時代が、この「旧要件末期」であった。
個人的に、「パチンコデビューの年」というのも、思い入れが深くなる原因だとは思うが…それでも、やっぱり「いい時代」だったな。
過去記事紹介(西陣、ジェットライン)
 平成元年(1989年)に西陣から登場した一発台の名機「ジェットライン」★賞球オール13 (ゲーム性について)天下に一つ穴クルーン、その下に回転...
>続きを読む
平成元年(1989年)に西陣から登場した一発台の名機「ジェットライン」★賞球オール13 (ゲーム性について)天下に一つ穴クルーン、その下に回転...
>続きを読む
http://blog.goo.ne.jp/selfconfide777mc/e/809cfb31935415faac585e660768f1c4
(西陣、ジェットライン過去記事)
こんな過去記事も、書いた事あったなぁ…。今後もちょくちょく、こういった「再放送」をお送りして行きたいと思う。まぁ、多忙期の「手抜き」といわれても、仕方ないのだが…。それでも、田山さんの池袋「S店」(山楽)時代のくだりなど、あらためて読み返してみても、結構面白いのではないか。一応、記事中の「一発台」実戦ホールのリストに、各機種の過去記事へのリンクを付した。ただ、実戦機種の全てをリスト化してある訳ではないので、今後、リストへの機種追加・補足なども行う予定。何かのご参考に。
1990年~1991年当時、一発台を打ちに行ったホール(小田急、山手線沿線)
・百合ヶ丘…「パーラー百合ヶ丘」⇒ワイワイワイ2(太陽電子、アレパチ)、サーカス(平和)
・読売ランド前…「パチンコランド」⇒ベータ(ニューギン)
・向ヶ丘遊園…「スター」⇒シャトル21(藤商事、アレパチ)、「銀座ホール」⇒キャラバン(マルホン)、ファミリー(大一)、ジャスティ(西陣)、「ニューギンザ」⇒ジャスティ、ビッグポーター(マルホン)、ターゲットI(三共)
・登戸…「玉の家」⇒ジェットライン(西陣)、「いろは」⇒タンブラーA(京楽)、「ハトヤ」⇒ジャスティ
・新宿…「モナコ」(スタジオアルタ裏)⇒ワイワイワイ2、「モナミ」(歌舞伎町)⇒フェアリー(京楽)、「ニューセブン」(モナミ隣)⇒ミュージック(マルホン)、「パチンコ747」(地下ホール)⇒メガトロン(藤商事)、ベータ
・新大久保…「サンキン」⇒スターライトI(三共)
・高田馬場…「ダイナム」⇒メガトロン、サイクロン(平和)、「東陽会館」⇒ターゲットI、「日拓」(1F)…ベータ
(今後も、リストの「充実化」を図る予定)
シーマスターX(山佐、4号機)、「逆押し」にハマった日々

1999年(平成11年)に山佐から登場した、純Aタイプ4号機「シーマスターX」
★ボーナス確率
BIG REG
設定1 1/287 1/655
設定2 1/273 1/606
設定3 1/260 1/565
設定4 1/248 1/528
設定5 1/240 1/468
設定6 1/240 1/364
業界初の「テトラリール」(第4のリール)搭載で一躍話題となり、斬新かつ分かり易いゲーム性や、手頃な技術介入性など、その高い完成度で人気を博した。
新たなテトラリールは、ボーナス告知、小役ナビ、チャンス演出(再始動)など、打ち手の期待感を大きく煽った。また、出目とテトラの絶妙なコンビネーションが、ゲーム性に一層の「奥行き」を与えた。むろん、山佐伝統の豊富なリーチ目も健在だった。
本機以後、テトラリールは山佐の「十八番」(おはこ)となり、オイチョカバX、アラベスクR、コングダム、ハイパーラッシュなど、様々に形を変えて、発展的に継承された。
その「元祖」である本機には、私自身も大変お世話になったし、本機を打ち込んだからこそ、上記の各後継機にも、全く違和感なく対応できた。
当時の職場にほど近い、東京・有楽町の「D店」(現存)や、当時の地元に近い、新百合ヶ丘「Z店」(現存)での実戦が、とりわけ記憶に刺さる。平日は有楽町でアフター5の短時間勝負、土曜・休日は新百合で終日実戦と、シーマスとの付き合いは案外長かったし、勝率もそこそこ良かった。
導入から暫くの間は、左リールを最初に押す、オーソドックスな「順押し」で楽しんだ。ビッグ図柄の一直線(鉄板)や、左「オレンジ・青7・オレンジ」の一確目、「オレンジ・赤7・オレンジ」(オレンジorボーナス)からの赤7単独テンパイ(二確)、小役のダイヤモンド型(菱型)など、私の「ツボ」を突く出目は、実に豊富だった。また、出目とテトラの「矛盾」でボーナスを察知する機会も多く、分かり易く楽しめるゲーム性に、グイグイと心を奪われた。



そんなある時、最初に右リールから狙う「逆押し」手順にも、独特の「持ち味」がある事を知る。
逆押しは、右リールの停止形で、成立フラグがほぼ「丸わかり」な上、順押しで厄介だった「オレンジの取りこぼし」も回避できた。先述の通り、順押しでは、中段オレンジを1/2で強制的に取りこぼす「イジワル制御」があり、テトラにオレンジ(チェリー)ナビの「コヤック」が出た時、対応役ハズレでもガセるケースが多発した。一方、逆押しだと、このガセが一切なくなる事が判ったのだ。
当時の私は、スロを打つ際に、「特定の一箇所」を徹底して狙う事が多かった。「多彩なリーチ目」を楽しむよりは、なるべくシンプルにフラグ察知ができる、「効率的手順」を優先していたのだ。そんな私にとって、本機の逆押しは、まさに打ってつけの打法といえた。
ファンの中には、「逆押しは出目が単調になるから、通常時が退屈だ」といって逆押しを敬遠したり、テトラ作動時のみ逆押しに切り替える人もいた。だが、私にそんな感覚など、全くなかった。
「この形は小役確定」とか、「この形だと、この小役がハズれれば入り」とか、「青7がここに止まれば、ビッグ確定」とか、「この出目で、テトラがこうなれば鉄板」など、成立フラグの察知が順押しよりシンプルで、その単純明快さが、却って「ツボ」だったのだ。
以後は、順押しそっちのけで、逆押しをメインに本機を堪能する事となった。幸い、「変則押し禁止」の理由で、遊技を妨げられる機会もなかった。
そんな訳で、今回も「今さら感」タップリだが、私が現役時にハマった、シーマスターXの「逆押し」を振り返る。
~山佐4号機「シーマスターX」、逆押し手順~
★リール配列
★テトラの意味
※テトラはレバーオン時に始動。始動音はA(低音)とB(高音)。停止タイミングは、A(第1停止)又はB(第3停止)。回転方向はA(順回転)かB(逆回転)。いずれも、AよりBの方が高期待度となる。なお、キャラ一旦停止後、「再始動」する事もある。テトラの作動パターンは、成立フラグに応じて、計44通りのテーブルから選択される。
・テトラに赤7三つ揃いの「777」が出れば、ビッグ確定。真ん中がBARの「7B7」だと、BR共通。
・アンディ(フグ⇒「アンディ・フグ」にかけた)、コヤック(魚)、キックン(クジラ)は小役ナビ。コヤック以外は、対応役ハズレでボーナス確定。コヤックは「チェリーorオレンジorボーナス」だが、順押し時、中段オレンジテンパイを「1/2」で強制的に取りこぼす制御があり、ナビハズレでのガセが多発。
さらに、右リールにはオレンジが7コマ離れたポイントもあって、コボシ制御がなくても適当押しではオレンジを取りこぼした。一方、以下の「逆押し」手順を行えば、こういったコボシを回避できるので、目押し次第でガセは一切出ない。
・レアキャラの「ネッシー」は、チャンスキャラである「ミドリ」(亀)からの再始動後に出現。派手に再始動を繰り返した後、最後は「777」(ビッグ)か「7B7」(BR共通)のボーナス告知で停止するので、「ボーナス鉄板」のキャラとなる(テトラ始動時に逆回転なら、ビッグ確定)。なお、ネッシーは、ビッグ終了時にも登場。
・「オッキー」(マンボウ、目が大きい方)停止後、再びオッキーが止まった場合は、必ずボーナスの鉄板告知に繋がる。地味キャラの二連続停止で、「鉄板」となった訳だ。
・再始動後、「ネムー」(マンボウ、眠たい目の方)が止まると、ノーチャンス。ヤメ時に使える。
★逆押し時、最初に狙う箇所…右リール上段に「青7」(14番)
右リールの青7は1個だけなので、目押しは楽。
(1)右枠上に青7が止まった場合
枠上に青7が止まった「ベル・リプ・オレンジ(ベ・リ・オ)」は、「リプレイorオレンジorREG」。ハズレはなく、中・左でリプ、オレを狙って外れれば、バケ確定。但し、外れてもビッグの可能性はゼロ。
リプレイの単独中段テンパイは、ほぼリプレイ。但し、左にはリプをこぼす「NGポイント」※が1か所あるので、赤7を枠内に狙ってNGポイントを避ける。
※左「6番」のオレンジ(BARの下)を中段ビタで押すと、リプを取りこぼす(ボーナス中のJACゲームも同じ)

大半は中段リプレイが揃う 左がリプハズレならREG(NGコボシを除く)

オレンジの単独下段テンパイは、オレンジ確定形。左リールの取りこぼしを避ける為、「オレンジ・赤7・オレンジ」を狙う。なお、リプ・ベルの平行テンパイはどちらも揃う可能性があるが、やはり「オレンジ・赤7・オレンジ」を、左枠内にキッチリ狙えば、どちらも取りこぼさない。
普通に下段オレンジが揃う。
右「ベリオ」からオレンジが揃う時は、必ず「下段(横並び)」に揃う。よって、オレンジが「左上がり」にテンパイしたら、2リール確定目(中段リプレイテンパイも否定)。割と良く出る形だが、バケ確定。

さらに、右「ベリオ」から中リールを止めた時、「中段リプ」「下段オレンジ」の何れも非テンパイなら、全て二確目となる。例えば、中リール中段が「青7」や「ベル」でも、REG確定。
テトラとの絡みでは、例えば、「キックン」(ベルナビ)が出た場合。右「ベリオ」は「リプレイorオレンジorREG」なので、ベルは揃わない。よって、第一停止時、ベルナビのキックンが停止すれば、REGの1リール確定目となる。
(2)上段に青7が止まった場合
右「青7・ベル・リプ(青・べ・リ)」は、「リプorBIGorハズレ」。もちろんハズレも多いが、ボーナスならば必ず「ビッグ」となる(リプレイが揃った場合を除く)。
リプの左上がりテンパイは、リプ確定。左は「13番」の赤7を目安に、NGポイントを避ける。
個人的に「大好物だった」、美麗なテンパイ形。逆押し「青7左下がり」は、嬉しい「ビッグ二確目」だ。
(中リールに青7は1つしかないが、下のBARも含めて「様式美」なので、敢えてBARを入れた)
青7ではなく、中段に「赤7」が停止した時も、ビッグ確定。中リールに赤7は2つあるが、どちらでも可。まぁ、滅多に止まってくれないが…。
さらに、右「青・ベ・リ」から、左リール中段に「オレンジ」が止まれば、中リール不問で、ビッグ確定。配列上、必ず左上段又は下段に、何れかのボーナス図柄が停止する(対角テンパイを形成)。



つまり、上記4パターンは、全てビッ確目となる。その他、上段「BAR」(下にオレンジ)停止でもOK。
テトラ絡みでは、例えば、「コヤック」(赤魚⇒チェリー、オレンジ対応)停止時。右リールがこの形で止まれば、通常時のチェリー(orオレンジ)の可能性はゼロ。よって、コヤック降臨時はビッグ一確となる。因みに、キックン(ベル)が出た時も、ベルは揃わないので、ビッグ確定。
(3)中段に青7が止まった場合
右「ベル・青7・ベル」は、通常時ベル確定。但し、左リールを適当押しすると、取りこぼす事がある。左には「オレンジ・赤7・オレンジ」を狙う。中リールは適当押し。なお、ビッグ中も、同じ手順でベルが取れる。

ベル揃い(左下がり) ベル揃い(左上がり)
ベル揃い(下段)
因みに、ボーナス成立後は、右「べ・青・べ」から、角チェリーが揃う事もある。つまり、右がこの形でチェリーの払い出しがあれば、成立後のリーチ目(アト目)となる。この場合、配列上、角チェリー付ボーナス図柄が、必ず中段でハサミテンパイする。
(4)下段に青7が止まった場合
逆押しで最も興奮するのが、右リール下段に青7が降臨した、コチラの停止形であろう。問答無用の「ビッグ一確目」だ。特に、テトラが回って身構えた時ではなく、テトラ非作動で油断している時に、いきなりこの目がドスンと止まると、思わず腰が浮く。

この形は、中と左にも青7を狙えば、そのまま下段(又は左上がり)に青7が揃う。但し、左に「チェリー付き」の青7(9番)を狙うと、チェリーを蹴ったりイジワル制御が働いたりして、青7が逃げる事がある。なので、左リールには「オレンジに挟まれた青7」(2番)を狙った方が良い。
(5)枠下に青7が止まった場合
青7が枠下までスベッた「リプレイ・オレンジ・ベル」(リ・オ・ベ)は、「チェリーorREGorハズレ」。

中リール中段に「リプレイ」or「ベル」が止まったら、残念ながら、ほぼハズレ確定。良く出る形。

一方、リプレイ上段テンパイは、2枚(中段)チェリー確定。左リールにチェリーを狙う。



さらに、右「リオベ」からは、中リール中段に「赤7」や「BAR」が止まっても、必ず2チェが取れる。
中リールの赤7とBARは2つづつあるが、どちらが止まってもOK。但し、「青7」停止時はガセ多し。
中リール中段に「オレンジ」が止まった場合は、地味ながら二確目となる。但し、REG確定だが…
テトラ絡みでは、例えば、「アンディ」(リプレイ対応)が止まった場合。この形からリプレイが揃う事はなく、アンディ停止でREG一確。また、右の目押しが正確なら、青7を枠下に蹴った形から、「ベル」も揃わない(右で青7の目押しをミスると、揃う事もある)。したがって、テトラに「キックン」が止まった場合も、REG確定の一確目となる。
(6)右に「チェリー・リプレイ・オレンジ」が止まった場合
青7がさらにスベって、「チェリー・リプレイ・オレンジ」(「チェ・リ・オ」…ジュースではない)が出たら、「オレンジorリプレイorREG」となる。ハズレはなく、オレンジ/リプ外れでREG確定。
枠上に青7がある「ベリオ」と同様、リプレイの中段単独テンパイは、ほぼリプレイ。左には赤7を狙って、NGポイントを避ける。

中段リプレイ揃い リプハズレでREG(NGこぼしを除く)
同様に、オレンジ単独下段テンパイは、オレンジ確定。左は「オレンジ・赤7・オレンジ」を狙う。
オレンジ左上がりテンパイも、やはりREG二確。さらに、中リールで「中段リプレイ」「下段オレンジ」の双方を否定した形も、バケ確定の二確目となる。
テトラ絡み…もはや説明不要とは思うが、例えば「キックン」が出た場合。この形は1リールでベルを否定しているから、キックン降臨でバケ一確。
まぁ、ザックリと説明してきたが、以上が、シーマスターXの「通常時・逆押し手順」の概要だ。
確かに、順押しと比べると出目パターンが単調になるきらいはある。特に、フラグ成立中は、右枠内に青7があればビッグ、なければバケという風に、BR判別があまりにも判り易かった。
だが、個人的には、これくらいシンプルな方が、むしろ取っ付き易かったのだ。リーチ目マニアなど、生粋の山佐ファンにとっては、少々物足りない手順だったかもしれないが…。
おっと、ここまで説明した以上、ビッグ中の「リプレイハズシ」手順も、一応示しておこう。
本機は、通常時のゲーム性みならず、ビッグ中の程よい技術介入性も、魅力の1つであった。
といっても、1、2回目小役ゲームは、順押し・適当打ちでOK。3回目に入ったら、通常時の逆押し手順を使い、メイン小役のベルを取っていく。後は、リプレイ成立時、中⇒左の順でハズせばよい。
3回目の小役ゲームに入ったら、まず、右リール上段に「青7」を狙う。

右がこの形になれば、必ずベルが揃う。中⇒左と押してもいいが、私は、ベル成立時は「左⇒中」の順で逆ハサミ打ちした。但し、左を適当に押すと取りこぼすポイントがあるので、左には「オレンジ・赤7・オレンジ」を狙う。最後の中リールは、適当打ちでOK。


ベルは、通常時と同じく、対角又は下段に揃う。
一方、右上段にリプレイがズルッとスベれば、リプレイ(JACIN)濃厚。この場合は、中リール枠内に「青7」を狙う。


青7が枠下にスベり落ちて、中リール中段に「ベル」が止まれば、この時点でハズシ成功(アシスト)となる。左リールは適当押しでよい。

一方、リプレイが左下がりにテンパったら、左リールで外す必要アリ。左には、オレンジに挟まれた赤7(13番)を、枠内に狙う(やや遅めでもよい)。余裕コマ数が多いから、楽に外せる。

但し、中リールの目押しにミスると、リプレイが「上段受け」でテンパイする事もある。この場合、ビタハズシが必要。左リール上段に、BAR下のオレンジ(6番)をビタで狙えば、リプレイがハズれる。
右リールが上記以外の形で止まった場合は、ハズレ濃厚(チェリーもあるが、低確率)。中・左は適当押しでよい。
残り9ゲームになったら、ハズシをせずに順押しに切り替える(ハズシ効果は、プラス20枚程度)。
なお、ジャックゲーム中は、通常時の逆押しと同様、リプが外れる「NGポイント」が1か所ある。
ビタハズシでも使えるこの場所(左上段「6番」のオレンジ)は、ジャック中に狙うと、ジャックハズレで1枚の損になる。当然、毎回この場所を狙えば、JACの払い出しはゼロとなるから、この場所だけは避けて押す事が必要。但し、左に「赤7」を狙えば、NGポイントを回避できる。
(ビッグ中の各役確率)
・ベル…1/2.05
・ジャックイン(リプレイ)…1/3.41
・チェリー…1/341.33
過去記事紹介…松本明子主演ドラマ「グッドラック」(1996年)
 1996年(平成8年)のパチンコTVドラマ「グッドラック」(主演:松本明子、日本テレビ 放映時期…1996年7月3日~9月11日(全11回))...
>続きを読む
1996年(平成8年)のパチンコTVドラマ「グッドラック」(主演:松本明子、日本テレビ 放映時期…1996年7月3日~9月11日(全11回))...
>続きを読む
今回も、過去記事の紹介で恐縮だが…1996年(平成8年)7~9月に日テレ系でOAされた、松本明子主演のドラマ「グッドラック」を久々に取り上げたくなり、コチラの過去記事を引っ張り出した。
http://blog.goo.ne.jp/selfconfide777mc/e/4efdbe572ced6a46a4c0303100cbd603
松本明子演じる主人公・飛鳥鈴子(あすか りんこ)が、急逝したパチンコ店初代オーナー・光太郎(橋爪功)の後を継いで、慣れない二代目オーナーを務めた、「飛鳥球殿」(JR代々木駅東口の「平和会館」(閉店)がロケ地)が懐かしい。今回は、第1話の概要を新たに加えたので、興味ある方はご覧を。
(「グッドラック」第1話の概要…ネタバレあり)
商店街の片隅で、地元客相手に細々と営業する、老舗の小さなパチンコ店、「飛鳥球殿」。
手打ち時代から自ら釘を叩き、店を切り盛りしてきたオーナーの飛鳥光太郎(橋爪功)には、長女・鈴子(松本明子)、次女・友利(秋本祐希)という、共に暮らす二人の娘がいた。
鈴子は三十路間近の銀行OLで、妹・友利は海外留学予定の女子大生。早くに妻を亡くした光太郎は、男手ひとつで二人の娘を育てあげたが、そんな父の苦労とは裏腹に、娘達は家業のパチンコ屋…というかパチンコが大嫌い。
ある朝、結婚願望の強い鈴子は、結婚相手を家に連れてくると父に告げるが、父も友利もまともに取り合わない。過去に二度、結婚するはずの男にフラれた、「前科」があるからだ。鈴子が、今日来る彼に「娘さんを下さい」と言われたらどうするの、と真剣に問いかけても、光太郎は「脳ミソ、フィーバーだね!」と茶化してしまう。
それでも、自分の小さな「城」である飛鳥球殿に来ると、気心の知れた店員や常連に、「娘がやっと結婚できそうだ」と嬉しそうに話す。何だかんだいって、光太郎も我が子の幸せを願っていた。
そんな彼のもとで働く従業員は、ベテラン主任の松岡(金田明夫)、ホール係の杉本(原田泰造)に長谷川(伊藤俊人=故人)。景品カウンターには、ちょっと斜に構えた妙子(網浜直子)と、元気だけが取り柄の緑(宮地直子)。大型店には遠く及ばぬ小所帯だが、人情に篤い光太郎を慕って、みな甲斐甲斐しく働く。
対する常連客は、八百屋(ドン貫太郎)、床屋(山田明郷)、易者(徳井優)、浪人生(桑原貞夫)、主婦(高木孝子)といった面々。こちらも、光太郎の人柄に惚れこむ、地元客ばかり。いつも開店前に並んでは、10時の開店と同時に、お目当ての台を目指して突っ走る。
そんな折、鈴子は同僚で恋人の秀明(愛称はヒデちゃん※)(川本淳一、現「淳市」名義)から、突然の「別れて下さい」宣告を食らう。彼には、別に好きな女性が出来たのだった。しかも、同じ職場にいる鈴子の後輩。またも、直前になって男に逃げられた鈴子は、大ショックを受ける。ヒデちゃんに作った愛情弁当を、ビルの屋上で「バカヤロー!」と一人ヤケ食い。
※当時、松本がレギュラー出演した深夜バラエティ「DAISUKI」の共演、中山秀征を意識した役名と思われる
一方、鈴子の父・光太郎のもとには、地味な黒のスーツを着た、猫背のメガネ男が訪れる。かつて、飛鳥球殿で凄腕の「ジグマプロ」として鳴らした、藤堂竜作(佐野史郎)だ。竜作は、訳あって光太郎の前から長く姿を消していたが、縁あって小さなバーの雇われ店長をする事となり、久々に地元へ戻って来たのだ。釘師としても一流の光太郎と、実力派の元パチプロ・竜作…古きよき「ライバル」との再会を嬉しく思った光太郎は、二人の思い出話に花を咲かせる。
そこへ、再開発事業を手掛ける「黒部興産」の高原俊輔(豊原功補)がやってくる。彼は、飛鳥球殿と周辺の土地を買収して、大型ショッピングセンタービルを建てる、「再開発プロジェクト」のリーダーだった。だが、常連の為に、昔と変わらない形でパチンコ店を続けたい光太郎は、「店も土地も絶対売らない」と突っぱねる。土下座で必死に頼み込む俊輔だが、光太郎の怒りは増すばかり。すると、あまりの興奮と心労で、持病の心臓発作が出た光太郎は、その場で倒れてしまう。焦って駆け寄る俊輔に、「動かすな、すぐ救急車を!」と、冷静に指示する竜作。
父が倒れたとの報に、急いで病院に向かう鈴子。友利や俊輔と共に病室へ入ると、「心筋梗塞」と診断された光太郎が、弱々しくベッドに横たわっていた。だが、光太郎は、自身の容体よりも鈴子の結婚相手が気になり、「どんな男だ?いい男なのか?」としきりに尋ねる。そんな父に、「フラれた」とは、とても言い出だせない鈴子。適当に誤魔化していたが、最後には思わず「いい男だよ…」と嘘をついてしまう。一方、俊輔の好青年ぶりに惹かれた鈴子は、出会って間もない彼に、淡い恋心を抱く。
翌日、鈴子は倒れた父に代わって、飛鳥球殿での仕事を手伝う。だが、「パチンコど素人」の彼女は、ハッキリ言って足手まといだった。従業員達に呆れられて、ホールから事務所に追いやられる。そこで、偶然出会ったのが、店に出入りするメーカー(ラッキー商会)の若手営業マン、祐二(原田龍二)だった。鈴子をただのバイトと勘違いした祐二は、先輩風を吹かせるが、彼女が光太郎の娘と知った途端、恐縮する。さらに、お世話になった光太郎に恩返ししたいと、店の手伝いを申し出る。
フロアに戻った鈴子と祐二は、ハネモノ数台を一人で掛け持ちして打つ、ガラの悪い客(BOB藤原)と遭遇する。祐二は、店員の注意を聞き入れない客に、「掛け持ちお断りの看板が見えないのか?漢字が読めなきゃ、想像で読むんだよ!」と、嫌味タップリに注意。その態度にブチギレた客と、小競り合いが勃発。そこに、通りすがりのセールスマン、佐藤年男(勝村政信)が現れて、「別のパチ屋で押さえておいた、釘のガバガバな台を譲る」というと、掛け持ち客は喜々として店を飛び出す。とっさの機転で混乱を救った佐藤は、主任の松岡から謝礼代わりに小箱一杯の玉を受け取ると、「ついでだから」と、自身が営業で売り歩くチベットの怪しい秘薬、「チべトロンX」を常連に宣伝して回る。
さて、結婚目前になって、またも挫折を味わった鈴子は、仕事でも絶不調だった。元彼を奪われた後輩とは気まずくなった上、後輩の仲間からもつまはじきに遭う。挙句に、銀行の窓口業務から、電話交換係への「左遷」。もはや、職場に自分の居場所などない…そう悟った鈴子は、荒んだ気持ちを癒そうと祐二と飲みに出ると、昼間出会った佐藤と居酒屋で再会する。愚痴を言い合い、ベロベロになった三人が飛鳥球殿に戻ると、自分をフッた元彼のヒデちゃんが、神妙な面持ちで鈴子を待っていた。「ヨリを戻しに来た」と思った鈴子は、「私にも、女のプライドってもんがあんだよ。土下座したって、許してやんないから」と、精一杯強がる。だが、ヒデちゃんにそんなつもりは毛頭なく、鈴子を憐れに思い、「手切金」を渡しに来ただけだった。つくづく、男を見る目がない…そう痛感した鈴子は、札束入りの封筒を持ったヒデちゃんに、強烈なパンチをお見舞いする。
一方、駅前再開発を狙う黒部興産も、そのまま黙って手をこまねいてはいなかった。若きリーダーの俊輔は、嫌われているのを百も承知で、土地の売却を求めて光太郎のもとを何度も訪れる。社長の黒部辰吉(西田健)から「買収の為なら、幾らでも使え」と小切手帳を渡された俊輔は、是が非でもプロジェクトを成功させねばならなかった。「飛鳥球殿を私共にお任せ願えれば、ビルのテナントとしてお店は残します。借金も、全て肩代わりします」と言葉巧みに誘うが、光太郎には全く通じない。すると俊輔は、自分に好意を抱く鈴子に、光太郎の説得を頼み込む。好きな相手から依頼されて、まんざらでもない鈴子。「今の時代、そういう生き残り方もアリでしょ?」と、頑固な父を説き伏せようとする。一方で、俊輔と祐二が実の兄弟である事を知り、複雑な気持ちにもなる。
因みに、黒部興産の社長、黒部には、美沙子(真梨邑ケイ)という愛人がいた。妙齢の和装美人で、銀座の高級クラブでママをしている。その美沙子には、実は、竜作の「元妻」という意外な過去があった。黒部のもとから車で銀座に戻る途中、美沙子は、飛鳥球殿の近くをトボトボ歩く、竜作の姿を偶然見かける。思わず車から降りて、竜作に声をかけた美沙子。その彼は、近くで「グッドラック」という名の、小さなバーをオープンする予定だった。
一方、甘い言葉で光太郎に土地の売却を勧める俊輔だが、彼の誘い文句は巧みな「罠」だった。「テナントとして店は残す」といいながら、移転予定先のフロアには、パチンコ屋と全く関係のない、ファミリーレストランを出店する「裏計画」があったのだ。全て、黒部興産のドス黒い策略だった。兄・俊輔の仕掛けた「カラクリ」に、たまたま気付いた弟の祐二。鈴子と一緒に、病室の光太郎のもとを訪れる。「突っぱねて正解でしたよ、危うく、ヤツラに騙される所でした」と裕二は言うが、光太郎の様子がどうもおかしい。実は、鈴子の説得により、黒部興産に店を任せてもいいと思い直した光太郎が、自ら俊輔を呼び寄せて、仮契約書にハンをついてしまった、というのだ。
まさかの事態に、愕然とする鈴子と祐二。一方、まんまと俊輔に騙されて、怒りに震える光太郎は、ベッドから起き上がり、猛然と病室を飛び出すが、廊下で再び発作が起きて、その場に倒れ込む。
ストレッチャーに乗せられ、苦悶の表情で手術室に運ばれる光太郎。傍らの鈴子に、「あいつなら…店を守ってくれる…ブッコミ…ブッコミの…」と、必死に声を絞り出した後、「鈴子、よかったな、嫁に行けて…」と最後の言葉を残したまま、帰らぬ人となる。息絶える前、光太郎の手からこぼれ落ちたのは、「アスカ」と刻印された、手打ち時代の錆びついたパチンコ玉だった。それを拾い上げた鈴子は、手術室に向かう父の背後で、「お父さーん!」と涙ながらに何度も呼び続けた。
父は死んだ…。いいようのない悲しみに、打ちひしがれる鈴子。灯りの消えた飛鳥球殿から、喪服姿のままフラリと外に出ると、夜の原宿陸橋の上で、ヘッドライトやテールランプの連なる車列を、ぼんやり眺めていた。そこへ、グデグデに酔っぱらった、ダメセールスマンの佐藤が通りかかり、酷く落ち込んでいる鈴子を見ると、「女性にも効きます」と、売り物のチべトロンXを彼女に手渡す。
佐藤の激励で、少し元気が戻った鈴子は、雨の降りしきる中、店に戻る。すると、誰もいないはずの飛鳥球殿のネオンが、命を吹き返したかの如く、いきなり煌々と光り出した。店に入った鈴子は、父の形見となった錆びたパチンコ玉を手に取り、ジッと見つめる。すると、背後から黒スーツの竜作がヌッと現れて、鈴子の手から銀玉をそっと取り上げると、こうつぶやいた。
「オヤジさん、釘をアタりながら、よく言っていた…。『面白れぇのは、玉がどこに落ちるかじゃない。どうやって落ちて行くかだ…』」。そして、パチプロ時代の自身の通り名が「ブッコミの竜」だった事を鈴子に告げて、「この店は、オヤジさんと共に終わる…」といって鈴子に銀玉を返すと、静かに店を立ち去る。
暗い店内に、一人残された鈴子。手には、形見の錆びついたパチンコ玉。竜作の、いや、亡き父の残した「どうやって落ちて行くか…」という言葉を、我が身になぞらえる。その玉を上皿にポンと落とし入れて、ハンドルをひねる。すると、キン、キン、キン…と小気味よい音を立て、右に左に弾かれた玉は、ヘソの始動チャッカーにスッと吸い込まれた。そして、リーチが掛かり、一発で777が揃って、見事に大当りする(台は、SANKYO「フィーバービューティフルII」)。
そして気が付けば、店の全台が賑やかに動き出して、どの台も、フィーバー、フィーバーで玉が溢れ出てくる。鈴子の足元には、台からこぼれ落ちた、無数の銀玉が散らばる。まるで、父が遠くから、元気のない自分を後押ししてくれている…そんな思いに駆られた鈴子。ピカピカと輝くパチンコ台を見つめながら、亡き父に思いを馳せて、涙を流すのだった。
翌朝、いつも通りに営業を続ける飛鳥球殿に、自信満々の表情を浮かべた俊輔が、大勢の部下を引き連れて現れる。手には、店と土地の「明渡し承諾書」が、しっかりと握られていた。店に入るや否や、全ての電源を部下に落とさせた俊輔は、「これが、ビジネスですよ」と、鈴子に本契約を迫る。
だが、鈴子は、手渡された契約書を、その場でビリビリと破り捨てる。あ然とする俊輔に、「店も土地も、誰にも渡しません。ここは、私の店です!」とキッパリ言い切った鈴子。不安げに見守る店員や常連の前で、黒部興産、そして俊輔との「対決」を堂々と宣言した…。
(第1話の概要、ここまで)
★10時開店前の飛鳥球殿で、光太郎と店員達が、お決まりの挨拶(声出し)を行うシーン(「いつも笑顔で!動作は機敏に、態度は明るく元気よく」など)。一通りの声出しが終わって、光太郎が「ミュージック・スタート!」と叫ぶと、オープニングテーマの「Good Luck」(Big Horns Bee)が流れる。
★ストレッチャーで手術室に運ばれる光太郎の背後で、鈴子が何度も「お父さーん!!」と悲しげに叫ぶ場面。そして、喪服姿の鈴子が悲しみに暮れる次のシーンでは、挿入曲「もっと静かに」(鈴里真帆)が流れて涙を誘う。
★鈴子が、俊輔の眼前で契約書を破り捨て、黒部興産との「対決」を表明した直後、エンディングテーマ「SQUALL」(氷室京介)が流れて、ラストのスタッフロールに切り替わる(バックでは、「カエルデジパチ」※の大当り画面が流れる)。
※番組用にSANKYOが作った、オリジナル台(大一の「ケロケロジャンプ」とは無関係)
Youtube 90年代動画紹介(19)
youtube 90年代動画紹介(19)
私が「神」と崇めるユーチューバー、ライルさん(Mr.Lyle Hiroshi Saxon)の「90年代動画」を拡散すると共に、レトロパチンコ的考察を加えるコーナー。
数えて19回目の今回は、コチラの「ライル動画」を取り上げる。
https://www.youtube.com/watch?v=U6j5W7jPNeM
(226)
1991年(平成3年)10月、小田急線(JR東海道線)藤沢駅周辺を捉えた、貴重な映像。
タイトルは、「1991 藤沢散策散歩 Fujisawa Walkabout 911012 」。
賞味約15分の動画には、言うまでも無いが、古き良き、「ノスタルジー」を感じる平成初期テイストが、ふんだんに盛り込まれている。
この当時、まだ昭和の香りが至る所に残存しており、そこに映る風景や人々を見るにつけ、何とも心地よい気分になる。
どのシーンも、見る人が見れば「感涙モノ」だが、個人的に「ツボ」なのが、コーヒーブレイクを終えたライルさんが、偶然通りかかった一軒のパチンコ店に焦点を当てて、果敢に店内の様子を捉えた、14:14~14:55(約40秒)の短い一場面。
場所は、藤沢駅・南口本通り商店街のパチ屋「グリーン」(現存)。
因みに、当時の藤沢駅界隈のホールは、南口がグリーン、フォーラム、ダイヤモンド、中央プラザ、オデオン、ニューフロリダ(スロ屋)など。一方の北口は、ハッピー本店、ハッピー駅前店、エキマエクラブなどが点在した。
ライルさんが「グリーン」に足を踏み入れると、パチ屋独特の喧騒の中で、多くの客が盤面をグッと睨んで遊技している。
店内BGMは、定番の「軍艦マーチ」。その軽快な調べに混じり、独特の甲高い電子音も聞こえる。よく聴けば、ニューギンの一発台、「ベータ」の大当りサウンド。電チューが開放→閉鎖と切り替わるたびに、効果音も変化する。
右端のスロットシマには、瑞穂製作所の3-1号機「コンチネンタルI」が、2シマ並ぶ。客付き良好、当時の人気ぶりが見て取れる。連チャン機・コンチIの人気は凄まじく、何処へ行っても主力級の活躍を見せていた。だが、この年の8~10月、新聞等でコンチIの「違法改造」がクローズアップされ、10月29日付の読売新聞でも、大々的に報じられた。翌11月には、当局が疑惑を「クロ」と断じて、コンチIの「検定取消し処分」を発表(瑞穂製作所は、以後3年、新たな検定申請が出来なかった)。
まさに「疑惑の渦中」にあった、当時のコンチI。だが、ホールでの集客力は、相変わらず高かった事が、映像からも見て取れる。但し、91年11月の検定取り消し後は、コンチIをノーマル基板に改修するホールが続出して、客付きもガタ落ちした。映像では、まだ勢いあるコンチIの「末期」の様子が確認できる。実に貴重だ。
ライルさんは、一発台「ベータ」→右隣の「コンチI」→左隣のベータ(戻る)の順で、通路を移動。さらに、ベータの左隣の通路には、「ドリームX」(奥村)が並ぶ。独特のデジタル音が響くシマ。コチラも客付きは良く、立ち見のオッサンもいる。
ドリームXの左隣は、台枠ランプや上皿から推測して、平和のデジパチ(旧要件機「舞羅望極II」の可能性が高い)。シマでは、男性店員がレールをよじ登って、真上から台を覗き込んでいる。玉づまりを直しているのだろうか。店員のファッションは、「濃い青シャツ、ネクタイ、黒のスラックス」。以前のパチ屋ではよく見かけた、懐かしい格好だ。若い女性店員はまだ少ない時代で※、大半が男。50代~60代と思しき、中高年の従業員も多く見かけた。
※若い女性が「皆無」だった訳ではない。店によっては「看板娘」的な女性店員もいたし、あえて、「若い女性店員だらけ」をウリにする店もあった(「浅草国際ゲームセンター」や「てんとう虫」など)。また、攻略誌でも、パチンコ必勝ガイドの「ミス・ジェットカウンター」や、パチンコ攻略マガジンの「僕のホールのキラ星GAL」など、若くて綺麗な女性店員を、写真入りで紹介する連載欄があった。
さらに左隣の通路では、ニューギンの旧要件デジパチ「エキサイト麻雀5」(よく見ると、「3」でなく「5」と判る)の、独特な「中華風」デジタル音が鳴り響く。例のチャカチャカしたリーチ音も聞こえる。
右端の通路は、映像での判別が、かなり難しい。それでも、「ニューギン」の盤面だと判る。さらに、盤面をよく見ると、1チャッカー、2チャッカーらしきものが、薄っすらだが見える。おそらく、ハネモノのシマだろう。当時人気があった、「さめざんす5」に見えない事もない。(90年秋には、この店に「ポップアート」「フラッシュマン5」「ビッグシューター」「魔界組」などのハネモノが入っていた、とする資料アリ)。通路の右側のシマには、若い女性客がいる。実際、「さめざんす」は女性ウケが良かった台なので、右はサメざんすのシマなのかも知れない。
かくして、ライルさんは、メイン入口側のシマを一通り観察すると、そのまま店外に出る。入口には、「パチンコ大好き!」と書かれたノボリが。また、ほんの一瞬だが、「札幌ラーメン ギョーザ はるみ いらっしゃいませ」と書かれた、小さな看板も映る(14:54)。「グリーン」の左隣にあったラーメン店、「はるみ」(閉店)のものであろう。
あらためて、「グリーン」の当時のラインナップ(パチンコ)を見ると、ニューギンの「ベータ」、奥村の「ドリームX」、ニューギン「エキサイト麻雀5」といった旧要件機の面々が、幅を利かせている。
1991年10月といえば、新要件機への移行も徐々に進み、話題の新機種も、多数リリースされた。しかし、店や地域によっては、まだ、旧要件機が多く残っていた事が判る。
かくいう私の地元(当時)も、91年秋の改装で新要件の「麻雀物語」(平和、液晶連チャン機)が導入されるまでは、「パチンコ大賞13」(西陣、ハネモノ)、「ニュートランプカード2」(京楽、デジパチ)、「スーパーロボット」(西陣、権利モノ)といった旧要件機が、普通に残っていた。
なお、13:35では、画面奥に「フォーラム」(閉店)というパチ屋(南口、「グリーン」の近く)が映る。
また、13:39~14:06で、ライルさんが軽食をとったのは、喫茶「ドトール」。現在は、「カラオケ U-STYLE」のビルに変わっている。
魔界組(西陣、ハネモノ)

1989年(平成元年)に西陣から登場した旧要件ハネモノ「魔界組」
★賞球…オール13
★最高8ラウンド継続(10カウント)
★大当り時のハネ開閉回数…最高18回
★大当り中、ヤクモノキャラの両手の間に、一個貯留可能
ヤクモノの「キョンシーキャラ」のコミカルな動きに一喜一憂した、旧要件ハネモノの名機。
初実戦は1990年(平成2年)初夏。既に、新台時期からは時間が経っていたが、依然、人気機種として活躍していた。
馴染みの新宿でも、「ニューミヤコ」「アラジン」「オデヲン」「コスモ」「モナコ」といったホールに設置。また、小田急線・下北沢駅の「ワールド」にも1シマ置いてあった。
※上記各ホール(跡地)の現状
・ニューミヤコ(西口・大ガード)→閉店後「カレイド新宿」
・アラジン(西口・ヨドバシ本店エリア)→現存
・オデヲン(旧コマ劇向い)→閉店後、「オリエンタルパサージュ新宿」→「マルハン歌舞伎町店」
・コスモ(歌舞伎花道通り)→閉店(現在「互福ビル」)
・モナコ(スタジオアルタ裏)→「G-7」 →閉店(現在「サンドラッグ 新宿東口店」)
・ワールド(下北沢駅南口、踏切前)→閉店(現在「大庄水産」)
(当時の店名で今も営業を続けるのは、「アラジン」のみ)
1980年代半ばに一大ブームを巻き起こした、香港のホラー&コメディー映画「霊幻道士(れいげんどうし)」シリーズ。
この映画に登場するキャラとして有名になったのが、両腕を前に出してピョンピョン跳ねる、妖怪「キョンシー」である。
本機のヤクモノは、まさにキョンシーを彷彿とさせた。本機の開発陣が、この映画を「リスペクト」していた事が窺える。
さらに、ヤクモノキャラの表情を見ると、人気漫画「ドラ〇ンボール」の個性的キャラ、「ピラ〇」にも通じるものがあった。
まぁ、当時のハネモノといえば、こうした映画・TVの有名キャラの「オマージュ」が、普通に行われていた訳だが…(単刀直入にいえば「パ〇リ」)。
余談だが、映画の初代「霊幻道士」には、「シャンシー」という美人の女幽霊キャラが登場する。当時高校生だった私は、その妖艶な魅力にガツンとやられてしまった(「ド」が付くストライクだったのだ)。それからだいぶ経って、「イナバウアー」で名を馳せた、女子フィギュアスケートの荒川静香選手を初めて見た時、「あっ、シャンシーに似ている…」と、反射的に感じたのだった。

(シャンシー@霊幻道士) 荒川選手
…おっと、話が本道から逸れてしまった。
ともかくも本機は、大当り中、ヤクモノのキョンシーが見せる、芸の細かな動きに特徴があった。
一方、通常時のキョンシーは、ステージ最奥部で、来たるべき「時」を静かに待っていた。
こうした通常時と大当り中のギャップ(「静」と「動」)も、映画のキョンシーと見事に重なり合う。
ヤクモノは上下二段構造。ハネに拾われた玉は、上段ステージの左右穴(「DROP」と書いてある)を通って、下段に落ちる。
上段ステージには三角形の「突起」が付いており、突起の振り分けによって、左のハネに拾われた玉は左サイドに、右のハネに拾われた玉は右サイドに、流れ易かった。
下段ステージに落ちた玉は、バウンドして左右の壁にぶつかるなど、様々に角度を変えて、奥から手前に転がる。最終的に、手前の中央Vゾーンに入れば、大当り(V両脇はハズレ)。台のクセにもよるが、V入賞率はさほど悪くない。むしろ、問題となったのは「ヨリ」の方だ(→後述)。
なお、下段ステージには「JUMP」と書かれたジャンプ板があり、ハネ開閉中、パタパタ上下動を繰り返す。ジャンプ板に当った玉は総じてハズれ易く、V入賞率を下げる障壁となった。だが、時には、板に当って絶妙に角度を変えた玉が、Vに飛びこむ事もあったから面白い。
本機の「ハネ」についていえば、キョンシーを模した左右のハネは小さく、開く角度も狭かったうえ、開閉時間も短めだった。さらに、ハネの先端が内向きにカーブしていて、お世辞にも、「玉を拾い易い形状」とはいえなかった。
また、本機はゲージにも特徴があって、他機種と比べて、ハネ周辺に打たれた釘の数が多かった。つまり、基本的に「ハネに寄りにくい」ゲージだったのだ。もちろん、寄り釘の調整次第で変わるが、当時は多くのホールが、「ナキは良いが、寄りにくい」クギ調整にしていた。
(各攻略誌の論調を見返しても、ほぼ全誌が、本機の特徴を「ナキ良し・寄り悪」としている)
因みに、某・業界誌に載った、ホール向け釘調整の例によると、、左の風車の右下にある四本釘を全て内側に寄せ、互いに近づければ寄り易くなり、逆に放射状に拡げると、ヨリ悪台になる。さらに、ハネ先端のヨロイ釘の一番下を左に叩くと外に逃げやすく、右に叩けば寄り易いとした。
ともかくも、本機はヨリの悪さに泣かされる事が非常に多く、ハネの「空振り」にジリジリさせられた。しかし、見方を変えれば、ヨリを見極めれば勝率は大きく上がった。ナキも大事だが、それ以上に、本機では「ヨリの重要性」が問われた。
さて、首尾よく大当りすると、ステージ奥で静止していたキョンシーに、「生命力」が宿る。
(「死体妖怪」のキョンシーに、生命力があるかどうかは知らないが…)
V入賞で派手なファンファーレが鳴った後、ヤクモノのキョンシーは、霊幻道士の映画よろしく、両手を「前ならえ」して前に突き出して、前後に飛び跳ねるコミカルな動きを繰り返す。
この段階でVに入る事も少なくないが、出玉的に見れば、あまり嬉しくはない。
ハズレ4カウントで、キョンシーは奥の位置に留まり、前に出していた両手を内側に閉じる。すると、両掌の間に一個、玉を貯留できるようになる。
(片手貯留となる事も稀にあったが、ド突けば直ったw)
この時、両手の高さをよく見ると、キョンシーの左手(打ち手から見て右側)の方が、右手(打ち手から見て左側)よりも、わずかに上がっていた。つまり、両手の位置が、左右で微妙に「ズレて」いた。しかも、これはヤクモノの「経年劣化」などではなく、製造段階からズレが存在した。
この「ズレ」のせいで、基本的に、本機は左のハネから拾わせた方が、キョンシーの手に乗り易くなっていた。よって、大当り中のストロークも、重要なポイントとなった。
ところが、台によっては、逆に右のハネから拾わせた方が、貯留し易い場合もあったのだ。やはり、ヤクモノの「クセ」によるところが大きい。
この特性を見事に証明してみせたのが、当時「パチンコ必勝ガイド」誌上プロ(ライター)であった、石橋達也プロだ。
かつて、同氏が担当する「石橋達也の13時間デスマッチ」という連載欄で、本機が対戦台になった回がある(同誌1990年5月号)。
この時、石橋プロは、対戦ホールの候補地として、新松戸駅前の「バロンタウン」、小田急江ノ島線・大和駅「大和会館」の二店舗を挙げた(いずれも、読者紹介による)。下見の結果、後者での実戦を決めた。
計5日の下見後、石橋氏は当日朝イチから、大和会館で「魔界組」を実戦。本命、対抗、注意など、候補を数台決めていたが、電車に乗り遅れて遅刻した為、どれもキープ出来なかった(大和会館は朝イチから魔界組の客つきが良かった)。
結局、あまり良くない台を打ち回った後、途中でようやく「本命」の251番が空く。だが、この251番、大当りは来易いが、V継続が極端に悪い「パンク台」だった。その理由が、左のハネ経由の玉が、キョンシーの手に乗りにくかったからだ。
そこで、石橋プロは、通常ストロークから、天四本の一番右を狙う「右打ち」に切り替えた。すると、大当り中、右のハネから貯留し易い事が判り、継続率は大きく改善した。さらに通常時も、右から拾った方がVに決まり易いと気付き、ひたすら天四本の一番右を狙い続けた。その結果、前半のスランプから立ち直って、辛うじて勝利に転じる事ができたのだ。
まさに、台のクセを把握した上で、思い切ってストロークを変えた事が、状況改善に繋がった好例といえよう。こうした実戦での「臨機応変」さが、石橋プロの人気の要因でもあった。
なおキョンシーへの貯留については、ヤクモノに入った玉の「勢い」や「スピード」も影響した。上段から下段に落ちる際、玉にある程度の勢いがないと、キョンシーの両手の間まで届かず、手の外側に跳ね返されて、落下するケースが多発。なお、玉に勢いがつくかどうかは、ハネ周りの釘調整、ストローク、ハネに拾われたタイミング、台のクセやネカセなど、様々な要因が影響した。
ハズレ8カウント又はハネ15回開閉で、貯留は解除。この際、キョンシーが前にせり出し、掌の間の貯留玉を、ポンと手前に放り出す(この動きにも愛嬌があった)。Vのすぐ近くに落ちた玉は、高確率でVゾーンへ入った。貯留にさえ成功していれば、継続率は高かったといえる。
だが、この時、解除した玉がことごとくVの左右に逸れてしまう、酷い「クセ悪台」もあって、致命的な欠陥台となった。こんな性根の悪いキョンシーに捕まると、思わず台のガラスを開けて、ヤクモノのキョンシーの額に「お札」を貼ってやりたくなった。だが、そんな事をすれば、事務所連行で酷い事になるので、思うだけで実行はしなかった。
口惜しいパンクのパターンとしては、貯留解除された玉が、後続の玉と「玉突き」して、Vを逃す事もあった。これを防ぐため、解除タイミングのハズレ8カウント(ハネ15回開閉)時、速やかに打ち出しを止めるのも、継続率アップの有効手段だった(解除直前に打ち出しを停止できれば、なお良し)。
貯留解除でVを逃した場合、キョンシーは再び前後動アクションを繰り返す。この時は、ラウンドの前半と違って両手の「開閉動作」も伴うので、閉じた手の間にタイミングよく乗った玉が、Vに入るチャンスもあった。だが、チャンスは残り2個(orハネ3回開閉)しかなかったから、やはり、キョンシーへの貯留の成否が、V継続の大きなカギとなった。
賞球オール13、1個貯留タイプで継続率も高く、ラウンド後半にV継続するケースも多かったので、平均出玉は約600個とまずまず。「短時間で打ち止め」とはいかなくても、ジワジワと出玉を伸ばし、順調に終了させる展開もあった。しかし、遊び台も多かったので、小箱の800個でひたすら揉まれ続けた後、最後に全ノマレのパターンも、しばしば喰らった。
なお、基本的にヨリ悪の本機は、大当り中のハネ開放18回で、10カウントに届かない事もあった。当然だが、V継続率や平均出玉も、「ヨリ」の良し悪しに大きく左右された訳だ。
言い忘れたが、本機は大当りのBGMにも味があった。ラウンド前半はハイテンポで勢いある「冒険活劇風サウンド」。一方、貯留開始後は一転して、哀愁の漂うわびしいメロディーに切り替わった。対照的なメロディだが、どちらもそれなりにインパクトがあって、記憶に「刺さる」音だった。
最後に余談だが、当時リリースされたパチンコ映画(ビデオ)で、本機が登場した事がある。
シブがき隊のフックンこと布川敏和が主演を務めた、「パチンコグラフィティ」(1992年、にっかつ)がそれだ。 (C)にっかつ
(C)にっかつ
エリートサラリーマン・浩平(布川)が、場末のパチンコ屋「船橋センター」に左遷されて、下っ端店員から鍛え上げられるという、破天荒なストーリー。そして、本作に出てくる店(船橋センター)の常連が、一クセも二クセもある客ばかりだった。
その中に、一人の連続婦女暴行犯を追い続ける、若き女性刑事・祥子(井上彩名)と、部下・矢野(小森谷徹)の(迷)コンビがいた。
ある日、彼らは、マーク中の犯人をパチ屋で発見するが、運悪く逃げられる。この不手際と、店内の威嚇発砲が原因で、二人は上司から「謹慎処分」を言い渡される。
かくして謹慎の身となった二人だが、ここぞとばかりに、パチ屋へ入り浸る。そんなある日、魔界組の角から2番目のクギが甘い事に気付いた祥子は、その台をキープしようとする(矢野との台取りに勝利)。だが、上皿には百円ライターがある。祥子は、台の呼び出しとライター撤去を店に頼むが、やってきた店員の中西(古本新之輔)は、「じきに先客が戻ってくる」といって取り合わない。
仕方なく、祥子は隣の魔界組を打つ。すると、お座り一発でVが来る。中西が「その台だって、イイ線いってる」というが、1ラウンドであっさりパンク。「パンクしちゃたよ…」と祥子。一方、百円ライターの乗った角2の台には、ボディコン女子大生の友美(国実百合※)が現れて、ちゃっかり座って打ち始める。実は、友美に好意を寄せる店員の中西が、魔界組の甘釘台をライターで予めキープしておいたのだ。
※本作は「國實唯理」名義
友美の台は、お座り一発はもちろん、パンクもなく、出玉はグングン伸びる。友美も「やった!もっと入って!」と興奮。その様子を嬉しそうに、背後で眺める中西。だが、一部始終を見ていた祥子と矢野からキツイ視線を浴びて、バツの悪くなった中西は、逃げるようにその場を立ち去る。
(左から、古本新之輔(背中)、小森谷徹、國實唯理、井上彩名。正面にあるのが、魔界組のシマ)
なお、祥子と矢野の「迷コンビ」は、最後の最後で、ようやく婦女暴行犯を逮捕して、感激のあまり、結婚してしまうのだった…。
オメデタブラザーズZ(西陣、ハネモノ)

1993年(平成5年)に西陣から登場した、新要件ハネモノ「オメデタブラザーズZ」
★賞球…5&11
★最高10ラウンド継続(初回が「2R」表示で、最終が「11R」)
★大当り中は、傘の先端の磁石に1個、傘の上に最大8個の貯留を行う
★貯留解除…ヤクモノ10カウント後、又はハネ18回開閉後
★当時の実戦店…新宿・西口(大ガード)「ジャンボ」(現存)
★兄弟機…「オメデタブラザーズ」(1993年)
・賞球違いの「オメデタブラザーズ」。コチラは賞球「7&13」。10R継続は共通。
今年一年も色々とあったが、決して良い出来事ばかりでなく、殺伐とした事件や痛ましい事故、また、予期せぬ自然災害なども、数多く発生した。
一足早い形だが、来たるべき年2016年は、ぜひ、「オメデタイ」事ばかりが多く起こる、明るく平穏無事な1年であって欲しい。そんな気持ちを込めて、今回は本機を紹介する。
「来年の事を話すと、鬼が笑う」というが、鬼も悪魔も、笑わば笑え。笑う門には、福が来る。
おめでたい新年の席で、「おめでとうございまーす!」の賑やかな名調子と共に、伝統芸・太神楽の「海老一染之助・染太郎」兄弟が、見事な曲芸を披露する…一昔前は、定番の光景だった。
兄・染太郎さんが2002年に逝去された後は、弟の染之助さんがピンで頑張っていたが、近年は、その染之助さんも病と戦っておられるという。
また、あの元気な掛け声で、和傘を使って四角い桝をクルクルと回したり、口にくわえた扇子に茶瓶を乗せたりする「名人芸」を、TVや舞台で披露して頂きたい。
本機は、その「染之助・染太郎」をモチーフにした(と思われる)ハネモノ。平成5年・春登場。
センターヤクモノでは、コミカルな曲芸師が傘を両手で抱えて、クルクルと回している。
新要件初期に三共から出た、「名人会GPA」(1991年)を彷彿とさせる動きであった。
(通常時の動き)
「あっぱれ」と書かれたハネに拾われた玉は、上段ステージを通って、下段に落ちる。
上段から下段に至るルートは2つ。(1)上段センター奥から傘に落ちる「傘ルート」と、(2)上段左右脇の穴から、傘に当らず下段へ落ちる、「左右穴ルート」の二つだ。
因みに、兄弟機「オメデタブラザーズ」には、(2)の左右穴がない。本機との大きな相違点である。
(1)の傘ルートの場合、ハネ開閉中は傘が左右半回転を繰り返す。落下した玉が、動く傘に当って手前に転がり、Vゾーンに入れば大当り。
但し、1チャッカー入賞時は、傘の回転(遠心力)で玉の挙動が不規則となり、V穴の左右に逸れるケースが多い。一方、2チャッカー入賞時は、2回目のハネ開閉前に、傘の動きが一瞬止まるので、そのタイミングで傘に当ると、Vに飛び込み易かった。即ち、2チャッカーに入れば、大当りの大きなチャンスとなる。
また、本機は(2)の左右穴ルートから、大当りする事も多かった。傘に当らず、下段ステージ両脇に落ちた玉が、斜め手前に転がってVを射止めるパターンだ。当然だが、左右穴を持たない兄弟機「オメデタブラザーズ」には、このV入賞パターンも存在しない。
左右穴からV入賞するルートがあった分、トータルのV入賞率は、本機の方が、兄弟機よりも高い。賞球や出玉が少ない代わりに、初当りは取り易かったという訳だ。
(とはいっても、クセ悪台だとVは遠い…)
(大当り時の動き)
大当りすると、ヤクモノの傘がやや上昇して、時計周りを開始する。この変化によって、傘の上部に玉を多く貯留する。複数の貯留玉が、傘と一緒にクルクル回る動きが、視覚的に楽しかった。
さらに、傘にアプローチした玉の一つが、傘の先端に仕込まれた「磁石」にひっつく。この「磁石玉」が、貯留解除後、Vに入り易い構造だった。
大当り中も、ヤクモノに入った玉は、(1)の「傘ルート」と、(2)の「両脇ルート」の何れかから、下段に落ちる。(1)は必ず貯留されるが、(2)は貯留されない。
つまり、本機は、大当り中、ヤクモノに入った全ての玉を、貯留する訳ではなかった。一方、兄弟機「オメデタブラザーズ」は、ヤクモノ内の玉を、全て貯留する「大量貯留タイプ」。これも、両者の大きな違いといえる。
本機は、大当り中、(2)の左右ルートからVに入ったりもしたから、10カウント前にV継続するケースも普通にあった。一方の兄弟機は、ヤクモノ内の玉を全貯留した後、10カウント後に解除なので、10カウント前のV継続はあり得ない。
したがって、1ラウンド当りの平均入賞数は、本機の方が劣る。さらに、ヤクモノの戻しも「11個」と少ないから、出玉のボリューム感は劣る。一方、(2)のルートでもV継続する分、継続率は本機の方が良好だ(それでも、よくパンクしたが…)。
ヤクモノ10カウント後、又はハネ18回開閉後に、貯留は解除される。
解除は、二段階に分けて、素早く行われる。まず、(1)傘の上で回転する複数の貯留玉を全解除。続けて、(2)傘の先端の「磁石」についた、大事な「1個貯留」を解除する。
先に解除された貯留は、V両脇に外れ易い。一方、磁石に付いていた玉は、解除後、ステージ中央を手前に直進して、Vを射止め易かった。
但し、「クセ」による大きな差もあって、磁石の玉を頻繁に外してしまう、クセ悪台も存在した。
因みに、下段奥から手前にかけて、V穴を左右から挟むように取り囲む、二本の「段差」があった。この段差は、ステージ外側の玉をVから遠ざける「ガード」であると同時に、中心付近の玉をVに導く「ガイド」の役割も果たした。なお、段差は、通常時のV入賞率にも影響した。
最後に、もう一つ。本機と兄弟機では、大当り中(通常時も)、V穴に入る際の玉の「挙動」が、全く違った。
V穴にダイレクトで飛び込む本機と違い、兄弟機「オメデタブラザーズ」では、V穴の真上にいったん貯留後、ストッパー(フタ)解除で、あらためてV穴に入る仕組み(二段階V入賞)だった。これは、当時の西陣ハネモノに、しばしば見られた構造である(「リキゾー」や「デジマル」の大当り中など)。
こうして色々比較すると、本機と兄弟機は、賞球以外に、かなり多くの相違点があった事が判る。
★★本年の更新は、これで最後となります。本年も、当ブログを御贔屓頂き、御礼申し上げます。来年も、相変わらずのマイペースでやっていく所存ですので、どうか、よろしくお付き合い下さい。それでは皆様、良いお年を。
「まにあっく懐パチ・懐スロ」管理人M
ルーキーパステルP-3(西陣、デジパチ)
謹賀新年。
皆様、本年も当ブログ、「まにあっく懐パチ・懐スロ」をご愛顧の程、どうぞ宜しく願い致します。
相変わらず、ノンビリペースで更新して行きますが、「細く長く」続けていきたい、と思う次第です。
という訳で、新年恒例の堅苦しい挨拶を終えた所で、さっそく「通常営業」に戻りたいと思う。
さて、新春一発目の更新は何にしようか…とアレコレ考えていた折、ふと、この台を思い出した。
1991年(平成3年)に西陣から出た、初期・新要件デジパチ「ルーキーパステルP-3」
・賞球…7&15
・大当り確率…1/210
・大当り図柄…0~9、A、C、P、Tの14通り(右デジのみ、ハズレ図柄の「?」アリ)
・最高16ラウンド継続(10カウント)
・出玉…約2300個
・ノーマル機
・兄弟機…ルーキーパステルP-2(1991年、小デジ確変機)
・後継機…パステルNo.1(1992年、仕込みの5連チャン(保1)アリ)
そういえば、当ブログは、何だかんだありつつも、開設から既に「4年半」が経過した。色んな意味で「スレて」きた訳だが、そういう時こそ、初心を忘れないよう心がけたい。
「記憶の奥底に沈みかけた、90年代のパチ・スロ情報を、出来る限り詳しく、レトロファンに向けて拡散したい」。こんな目的から、当ブログは2011年8月にスタートしたのだった。
開設当初の純粋な気持ちを忘れずに、常に、「新人」(ルーキー)の気持ちで記事を更新しよう…
だからこそ、「ルーキー」と名のつく、本機を紹介したいと思った。
…というのは、完全なる後付けの理由(笑)。
現役時に好きだった台が、記事未作成のままだった、という単純な理由に過ぎない。
(このところ、西陣の台の記事が続くが、それも単なる偶然)
なお、いうまでもなく、「ルーキー」は、当時の西陣デジパチの「冠名」である。
(三共はフィーバー、平和はブラボー、ニューギンはエキサイト、三洋はパニック、大一はアイドル…など)
平成3年の晩秋、小田急・向ヶ丘遊園駅(北口)の「銀座スター」というパチ屋で本機と初遭遇した時、その特徴ある面構えに、いささか気持ちが高ぶった事を思い出す。 (C)Google
(C)Google
銀座スターは、現在「GINZA U-style」の名称で営業。最近はこのエリアもご無沙汰だが、グーグルマップで見る限りでは、随分と趣が変わった。店の目の前の大きなバスターミナルも当時は無かったし、駅前のクリーニング屋も「いすず食堂」という昭和然とした食堂だったし、「キッチン南海」の場所も、当時は「石川屋」という小さなメシ屋だった(割烹着のオッチャンとカツカレーが懐かしい…)。
コチラは1991年頃の「スター」の店構え。本機が並んでいたのは、1F左端の通路、右側のシマ。
(フロアの大きさは、現在の半分しかなかった。奥の半分は、その後の店舗拡張で出来たモノ)
ありきたりの7セグやドットとは違って、「ブロック崩し」(←譬えが古いw)を思わせる、3×10マスのカラーブロックデジタル。そのデジタルの色彩も、「パステルカラー」の如く、上から「濃いオレンジ、薄いオレンジ、黄緑」と、3段階のグラデーションが付いていた。
同社の新要件デジパチ第一弾「ルーキーデルタ」(兄弟機はP2)を初めて見た時、丸型デジタルをトライアングル状に配した、独創的な構造に驚かされた(しかも、デジタル外周に回転式の「磁石」が仕込んであった)。
西陣が、新要件デジパチ第一弾として送り出した「ルーキーデルタ」(1991年登場)
本機は、その「デルタ」の後続機として出た「第二弾」だが(正しくは、デルタの兄弟機「P-2」の後を受けた第三弾)だが、先行機に負けず劣らずの、オリジナリティを持ち合わせていた。
当時の西陣は、総じて「ハネモノ」の開発力に定評があったが、ハネモノばかりではなく、ファンキーセブン、アラシキング、スーパールーレット、ルーキーデルタ、そして本機という風に、独創的なデジパチも立て続けに出していた。
ファンキーセブン(西陣、1989年、旧要件機)
アラシキング(西陣、1990年、旧要件機)
スーパールーレット(西陣、1990年、旧要件機)
連チャン性云々とは関係なく、デジタル画面そのものに、「何度も打ちたい」と思わせる、一種独特の魅力が備わっていた(私の場合、オーソックスなドットデジパチの「ラスベガス」にも、ガッツリハマったクチだが)。
ラスベガス(西陣、1990年、旧要件機)…新宿西口「ジャンボ」地下フロアが、戦いの場所だった。
それから、本機は「左→中→右」の順で縦スクロールする、デジタルのアクションも面白かった。
左デジ停止後、中デジは3~6コマ進んで(スベッて)止まるが、スベリコマ数はランダムなので、リーチの「先読み」は、出来そうで出来ない。
また、リーチが掛かりそうで掛からない、「左・中1コマズレ」の目が続くこともあって、そういう時は「不調時のシグナル」として、ヤメ時の参考にした(完全にオカルトだが…)。
左・中ゾロ目でリーチが掛かると、右デジは、速度をやや落としてスクロール。1周以内で止まる時もあるが、2周目に入る事も。右デジは、停止直前にブレーキがかかって、スローに切り替わる。スーパーリーチは無い。また、右デジのみ、ハズレ図柄の「?」があった。
因みに、この「?」図柄をゲーム性に活かした兄弟機が、同時期登場の「ルーキーパステルP-2」。
(ホール導入は、「P-3」よりもわずかに後)
ルーキーパステルP-2(西陣、1991年登場、新要件機)
大当り確率は、本機よりやや低い「1/220」(それでも良心的な数値)。コチラは、「?」図柄が左・中デジタルにもあり、「???」でも大当りとなる(大当り図柄は15通りで、本機よりも1つ多い)。
また、「P-2」は小デジタルの確変機能を備えており、メインデジタルに「3・3・?」又は「7・7・?」が出れば、小デジ確変突入(メイン確率は不変)。つまり、3か7のリーチが「?」で外れると確変に入る仕様で、3・7リーチは「2倍」アツかった。突入後は、大当りするまで小デジ確率が10倍アップ(1/23→1/2.3)。電チューは「1.5秒の1回開放(2個入賞で閉鎖)」だが、ガバガバ玉を拾った印象は全くない。確変中は、各デジタル上のオレンジランプが点灯。西武新宿駅前「日拓1号店」の1Fで打った。 (C)Google
(C)Google
西武新宿駅前通りの日拓1号店は、「エスパス日拓・西武新宿店」の名で、現在も営業中。ただ、グーグルマップを見ると、路地向かい(左)にあった系列のスロ屋(当時の店名は「日拓ビッグプレイ1,2」)は、既になくなった模様…。
(90年代の新宿「日拓1号店」の様子)
電チュー(小デジ)といえば、本機、即ちルーキーパステルP-3にも、ヘソに電チューが付いていた。ヘソ両脇のスルーチャッカー通過で、メインアタッカー下の1ケタ7セグ(小デジ)が変動。当選率は「1/1.3」と高いが(0~9、F、L、Pのうち、数字で小当り)、「0.5秒の1回開放」だった為、あまり玉を拾ってくれなかった。「たまに入れば、御の字」という感じ。
なお、本機は、天下にワープゾーン入口があり、ここのクギ調整が甘いと、ワープ経由のヘソ入賞率が大きくアップ(兄弟機も同じ)。当時の西陣は、こうしたワープ付きの台が多かった(業界初のワープ搭載機も、同社の旧要件機「ファンキーセブン」である)。
さて、デジタルの挙動もさることながら、本機は、「連チャン機」か否かに関して、デビュー当時から、何かしらの「疑惑」が常に付きまとった。
新要件初期の当時は連チャンデジパチが人気で、特に、平和の保留連チャン機「麻雀物語」(1991年、業界初のカラー液晶モニタ搭載)が、空前の大ヒットを飛ばしていた。同じ平和からは、「ブラボークイーン」という保連機も出ていた。

(平和「麻雀物語」、1991年登場) (平和「ブラボークイーン」、1991年登場)
また、三共の「フィーバーフラッシュSP」や「フィーバースパーク」(GP、ED、CX)も、わかり易い「保1連」でファンの心を掴んだ。さらに、藤商事の4ケタデジタル搭載機「ターンバック」(「パチスロの波」を持つと言われた)やニューギンのドラム機「エキサイトカムカムAW」などの数珠連チャン機も、多くのファンから支持を受けた。

三共「フィーバーフラッシュSP」(1991年) 三共「フィーバースパークED」(1991年)

藤商事「ターンバック」(1991年) ニューギン「エキサイトカムカムAW」(1991年)
一方、三共・平和と共に、当時「ビッグ3」と呼ばれた西陣は、露骨な連チャン性のあるデジパチを、ほとんど出していなかった。だが、他社の初期新要件機の連チャン性に鑑みて、「西陣だって怪しいのでは?」と、ファンや攻略誌から勘ぐられていた。
実際、同社初の新要件デジパチ「ルーキーデルタ」や、兄弟機「ルーキーデルタP-2」も、当初から連チャン性を様々な角度から疑われたが、結局は「ノーマル機」との結論に至っている。
そして本機も、「1個入賞で閉じる仕様のVゾーンに、2個入れば連チャン確定」とか、「最終ラウンドをフルオープンさせると連チャン」とかいう噂が、まことしやかに流れた(こうした「連チャン打法」の類は、ルーキーデルタの時もあった)。
私自身、本機で保留連チャンの経験があるし、また、大当り後50回転以内で数珠連チャンさせた事も多い。その為、詳細が判るまでは、何らかの「仕込まれた連チャン性」があるのでは…と、絶えず勘ぐりながら打っていた。
だが、内部解析の結果、本機はプログラム的に怪しい部分の無い、普通のノーマル機だと判った。大当りカウンターは「0~209」の計210コマで、大当り値は「180」。大当り時の怪しい「書き換え処理」も見当たらず、確率1/210の「ノーマルデジパチ」に過ぎなかった。結局の所、もとの確率が「1/210」と甘い為、「自力連チャン」を誘発していた訳だ。
さらに、本機には「モーニング疑惑」もあって、朝イチ(電源オン直後)は大当り確率がアップすると言われた事がある。だが、これも「1/210」の確率がなせる、「偶然の産物」に過ぎなかった。
一方、本機の後継機として、1992年(平成4年)春にリリースされた「パステルNo.1」については、本機や兄弟機「P2」と違って、どう見ても「仕込み連チャン機」と思わせる挙動を見せた。コチラは、新宿・歌舞伎町あずま通り沿いにあった「ニューメトロ」に設置(「P-3」があった向ヶ丘遊園「スター」にも入った気がするが、記憶がイマイチ…)。
「パステルNo.1」(西陣、1992年登場、新要件機)
大当り確率は、本機と同じ「1/210」。小デジ(電チュー)も付いており、本機同様、アタッカー真下の1桁7セグに「0~9」が出ると、0.5秒の開放を1回行う(小デジ当選率は「1/1.3」だが、電チューの拾いが悪く、さほど意味をなさなかった)。
さらに、コチラには露骨な「保1連チャン」が仕込まれていた。しかも、いったん連チャンすると、一気に「5連チャン」(全て保1で発生)まで伸びる機会が大半。一気に「12000発」の大量獲得となる。但し、連チャンの発生率は、「初当りの約30回に1回」程度と低く、終日打って連チャンが来ない事も普通だった。当時は、パチスロ3号機「アポロン」の5連Verが有名だった為、パステルNo.1の5連も、アポロンを意識した仕様に思えた(偶然の一致かも知れないが…)。
パステルNo.1の連チャンシステムは、資料不足により不明。だが、「5連全てが保1で発生」という挙動から考えれば、「初当り約30回に1回」の極めて低い割合で、「保1~保4の乱数値をまとめて大当り値に書き換える」処理が、大当り中(或いは大当り終了直後)に行われる仕様と推測。但し、連チャンは2連で終わる事もあったので、保1のみ書き換わるケースもあったと思われる(自力ダブルの可能性もあるが…)。
(在りし日の新宿・歌舞伎町「ニューメトロ」(閉店)。当時のあずま通りは胡散臭さが満点。一歩足を踏み入れるのも、割と勇気が要った。現在、跡地は岩盤浴「OSSO」の綺麗な建物に変わっている(ビルの名称は今も「ニューメトロビル」)で、当時の足跡を残す。)
かくして、本機に端を発した西陣「ルーキーパステル」シリーズは、何故か、「P-3」→「P-2」→「No.1」の順でホールに登場。なぜ、No.1が最後だったかについては諸説あるが、「5連」の怪しい挙動が、登場時期にも絡んでいた気がする。つまり、一番インパクトの強い台を最後に持ってきたのでは…ということ。但し、真相は不明。
パステルシリーズで好評を得たカラフルなブロックデジタルは、その後、「花らんまん」(ルーキーVX)「ルーキーVXP-2」「宇宙伝説」「ルーキーVZ」と受け継がれて、90年代前半・西陣デジパチにおける、一つの「トレンド」を形成した。
花らんまん(西陣、1992年)→型式名称は「ルーキーVX」。数珠連チャン率20%
ルーキーVXP-2(西陣、1992年)→花らんまんの兄弟機。連チャン率15%。
※花らんまんとルーキーVXP-2の関係については、コチラの過去記事をご参考に。
http://blog.goo.ne.jp/selfconfide777mc/e/03b16000f3dd0df5c6d2618718fd1a12
宇宙伝説(西陣、1992年)→賞球7&15。大当り確率は1/237。大当り後の30回転は小デジ確率アップ。数珠連アリ。
ルーキーVZ(西陣、1992年)→宇宙伝説の兄弟機。確率はコチラも1/237。但し、賞球6&13で、出玉はやや少なめ。やはり、大当り後の小デジ変動機能付き(数珠連も発生した)。
という訳で、今回記事はここまで。
皆様、申年の2016年も、当ブログとお付き合いの程、どうぞよろしくお願いします。
ライル動画に見る、新宿「パチスロてんとう虫」
最近、当ブログを訪れる方々の「検索履歴」をチェックすると、「新宿 てんとう虫」のキーワードで、コチラに辿り着く人が、意外と多い。
(最も多い検索ワードは「パチプロ梁山泊」。次が「田山幸憲」)
このブログで「てんとう虫」といえば、もちろん昆虫のそれではなくて、かつて、都内や千葉などで、ユニバーサル社のアンテナショップとしてチェーン展開していた、「パチスロ専門店」の事だ。
1990年代には、新宿・東南口をはじめ、上野駅に二軒(PART1、PART2)、中野駅(北口・ブロードウェイ内)、武蔵小金井駅(北口)、千葉・市川駅(北口)、千葉・松戸駅(西口)など、首都圏各地に店舗が存在した。
決して「ボッタ店」というイメージはなく、それなりに良心的営業を行っていたようだが、90年代後半辺りに姿を消した。
私も、勝手知ったる新宿エリアで営業していた、東南口の「パチスロ・てんとう虫」には、現役当時、特に、1990年~1994年にかけて通ったクチである。
(1F、2Fの2フロアで営業。現在、跡地は1Fが「讃岐うどん かのや」、2Fが「もんじゃや」)
(当時の新宿「てんとう虫」 ムサシノ通り側の1F入口)
「パチスログリンピース新宿本店」と「パチンコ平和」という2つのホールに挟まれる形で、あたかも、「大きな葉の影に隠れたてんとう虫」の如く、目立たず営業を続けた小店。
グリンピース新宿本店の前で並ぶ開店待ちの人々。その左手に、「てんとう虫 777 パチスロ」と書かれた看板が見える。これが、新宿「パチスロてんとう虫」の2Fに通じる入口だ。自販機脇の狭い小さな階段を上がって、2Fに入る。1F入口は、この画像のもう少し奥。つまり、1Fと2Fの入口が別々にあるのが特徴だった。なお、「てんとう虫」は、駅側の通りとムサシノ通りに挟まれていた為、入口もフロア両サイドに存在した。
まぁ、目立たないとはいっても、それは店の「規模」の話で、店内に足を踏み入れれば、傍のグリンピースに負けない大音量で、女性店員が「ハイ〇〇番台、ビッグボーナススタート、おめでとうございます!」「ジャンジャンバリバリ、お出しくださいませ!」など、独特のマイクパフォーマンスを披露していた。マイクに乗った大声は自動ドアの外に漏れて、表に聞こえる程だった。その表通りでは、ジャンパーを来た店員が、通行人に宣伝のティッシュを配っている事もあった。
当ブログでは、これまで2回ほど、「新宿・てんとう虫」についての記事を作成した。ネットで検索してコチラに辿り着いた方々は、おそらく、以下の過去記事がヒットしたのだろう。「てんとう虫」に関する情報自体が少ないので、これらの記事が自動的に検索上位にくる。
「新宿東南口 パチスロてんとう虫をふりかえる」
新宿「パチスロてんとう虫の…」
ただ、当ブログの情報に触れた方々は、「どうせなら、新宿・てんとう虫の営業当時の映像(動画)を、一度は見てみたい」と思ったのではないか。
実は、そういった類の「レア映像」が、例の「ライル動画」に複数存在する。
ライル動画…ご存知の通り、私が「神」と崇拝するユーチューバー、ライルさん(Mr.Lyle Hiroshi Saxon)がアップした、90年代都内近郊を撮影した動画である。
私にとっては、まさに「タイムマシン」であり、古き良き、90年代前半に思いを馳せる時は、真っ先にライルさんのサイトを訪問している。
そして、今までライルさんがアップした膨大な動画の中には、偶然又は必然に、新宿東南口「パチスロ・てんとう虫」を捉えた映像が、幾つもあるのだ。
これをいきなり探し出すのは不可能に近いが、幸い、私はライル動画がアップされるたび、映像を隅々までチェックして、「どの場面に、どんなパチ屋・スロ屋が映っているか」について、細かくリストアップしてきた。今や、動画リストは、200項目以上に増えた。
そして、今の所、営業当時の新宿「てんとう虫」が映ったシーンが、計6箇所ある事が判っている。
今回は、その映像を、皆さんに紹介したいと思う次第だ。
相変わらずの「局地ネタ」だが、少なくとも、推定40名(?)の「てんとう虫ファン」には、それなりの「お宝映像」となるハズ…。
新宿東南口「パチスロてんとう虫」が映り込んだ、90年代「ライル動画」リスト
(A)1990年6月
https://www.youtube.com/watch?v=rO8dhv6U3Lo
(1990-Shinjuku at Night(East Side)夜の新宿(東口)900612)
→1:19の場面。新宿東南口の「ムサシノ通り(武蔵野通り)」を歩くライルさんが、「てんとう虫」店内に一瞬カメラを向ける。男性店員と女性店員のマイクパフォーマンスの音声が入っている。客付き良好の狭いシマには、ユニバーサル2-2号機「リバティベルIV」が並ぶ。当時の「新宿てんとう虫」は、1F・2FいずれもリバIVのみ置く、「リバIV専門店」だった(駅西口のスロ屋「ランガー」も同じ)。
(B)1990年8月
https://www.youtube.com/watch?v=6rUzpFwYYDk
(1990 Shinjuku Night,etc-(900802))
→15:45~15:53の約8秒。ムサシノ通りを歩くライルさん(先程の動画と逆方向に)が、「てんとう虫」店内の様子を捉えている。若い女性のマイクパフォ。頭上に札を刺す女性店員。当時の制服は、白のブラウス、黒のタイトスカート、胸には赤いリボン。この動画でもしっかり映っている。因みに、16:08では、グリンピース新宿本店の1F(当時はファイヤーバード7Uを設置)が映る。
(C)1990年11月
https://www.youtube.com/watch?v=0rbFWu-cgV8
(1990-A Night on the Town(Bubble Era Shinjuku)新宿の夜(901122))
→6:41で映るのは、「新宿てんとう虫」2Fの窓際付近。確か、ムサシノ通り側の2F窓際には踊り場的なスペースがあり、そちらからも下に降りられたハズ。その踊り場に立つ、二人の若者の後ろ姿。てんとう虫2Fの様子を捉えた、貴重なシーンだ。
(D)1991年3月
https://www.youtube.com/watch?v=V1VuGtP9WTA
(1991 Buying an Analog Video Camera in Shinjuku 910314)
→0:25で、新宿駅・東南口の階段から見た「新宿てんとう虫」(2F入口の看板)と、「グリンピース新宿本店」のネオン看板。グリンピのネオンには、「BF~4F」とあるが、この時期(91年3月)は、既に最上階(5F)にコンチネンタルIが入った頃。設置状況に看板が追い付いていない感じだ。
(E)1991年4月
https://www.youtube.com/watch?v=tcXWt8z4zeE
(1991 Shinjuku Old Squatter Area(910410))
→0:08で、一瞬だが「てんとう虫」の入口(駅側)が映る。手前と奥の2ヶ所にネオン。手前が2Fの入口で、奥が1F。回転ネオンには、「全台大開放」「2F リバティベルIV」の文字。記憶では、当時の1Fは全台「コンチIII」で、2FのみリバIV(リバIIIとセンチュリー21も数台)だったハズ。やはり、女性店員の甲高いマイクパフォ「777揃いましての、ラッキースタート!」。なお、0:05では、当時の東南口のシンボル的な台湾料理屋、「台北飯店」の赤い看板と古い店舗が映る(0:08でも台北飯店の建物と看板が見える)。
(F)1991年5月
https://www.youtube.com/watch?v=G8CVEKltlks
(1991 夜中の新宿など -ひばりヶ丘駅-池袋駅-新宿駅 Midnight Shinjuku Etc 910529)
→9:20で「てんとう虫」1F入口の看板が映った直後、9:21~9:24で、果敢にもライルさんが店内に近づき、自動ドア手前で店内にカメラを向けている。狭いシマは満席で、入口には立ち見の客も。女性店員のマイクパフォも威勢良い。居並ぶ台は識別できないが、時期的に考えれば「コンチIII」(橙パネル)である事は明らか(コンチIIIの効果音も聴こえるような…)。
とまぁ、こんな感じでピックアップしてきたが、動画をもっと細かく観察すれば、「パチスロてんとう虫」のみならず、「グリンピース新宿本店」や「パチンコ平和」といった、周辺のホールの姿も随所に映り込んでいる。さらに、件の「台北飯店」や、家電安売り店「セカンドハンズ」など、今は無き懐かしい店の姿もある。
再開発が進んだ現在とは違い、昭和然として、「戦後」の雰囲気すら残していた、90年代初頭の新宿・東南口。その当時の記憶をハッキリと呼び起こしてくれる、貴重な映像の数々。そうした動画を絶えずアップして下さるライルさんに、あらためて感謝したい。
※補足 (C)Google
(C)Google
2009年現在のストリートビュー(現在も閲覧可能)を見ると、新宿「パチスロてんとう虫」の看板が、まだ残っている(「パチスロ 2F」の表記)。直近の画像では確認できない為、既に撤去された模様。
ちょっと昔、「寝ドキッ!!」って深夜番組があった
「寝ドキッ!!」
1996年(平成8年)から日本テレビ(NTV)系で放映された、知る人ぞ知る「マイナー深夜番組」。
自分は、96~98年の「前期」の頃しか知らないが、調べてみると、割と息の長い番組だったようで、2002年(平成14年)まで続いていた模様。深夜枠で6年も続くなど、頑張った方ではないか。
ただ、放送時間がちょっと変わっていて、「夜中の3時過ぎ~4時過ぎ」という、「一体、誰が見てるんだ」的な時間帯でのオンエアだった。
1996年のTV番組欄より…放映時間は木曜・深夜3:15~4:10。この当時は「木曜決定版」という深夜枠でOAされた。しかし、「大島朱美」って誰だ…?)
しかも、自分が視聴していた当時(96~98年)は、「関東ローカル」での放映だったと思われる
(その他の放映地域もあったかもしれないが、北海道、東海、関西の番組欄には出ていない)。
なので、こうして番組名を紹介したところで、「何、それ?シラネ」と冷ややかな反応を見せる方も、少なくないだろう。
それでも、一部フリークに記事の内容が伝われば、それで十分だ。
さて、この「寝ドキッ!!」の番組内容だが、いかにも深夜らしく、何ともユルい感じだった。
毎回、一人のグラビアアイドル(タレント)にスポットを当て、彼女の「自室」にTVカメラが入り込む。そこで、プロフィール紹介のインタビューを行ったり、持っている私服を見せたり、現在ハマっている遊びを紹介したり、という様な事をやっていた。
同時間帯のメイン視聴層である「20~30代男性」をターゲットに、アイドル・タレントの「プライベート」な空間に、ちょっとだけ近づける…そんなコンセプトで、この番組は製作されたと思われる。
ただ、この「アイドル」というのが微妙で、さほど名の売れていない、「B級タレント」と思しき子ばかり出ていた。まぁ、「深夜3時」の時間帯からして、低予算の番組であった事は、容易に想像がつく。
(2000年以降だと、人気アイドルが出た回もあったようだが…)
で、こうした様々な企画の中に、番組の「主役」であるアイドルが、自宅キッチンで得意料理を披露するという、「定番」のコーナーがあった。
視聴者は、その一部始終を、TVカメラを通して見る訳だ。人によっては、「疑似恋愛」的な感覚が、生じたかもしれない。
材料を切る段から料理の完成に至るまで、全て「自力」で行うのがルール。鮮やかな包丁さばきを見せる女性もいた一方で、いかにも素人風で、危なっかしい手つきの子も多かった。
ここでも、調理の過程で、彼女達の「素」の部分が垣間見えて、意外と面白かった。
幸い、当方のビデオライブラリーには、当時のVTRが3本残っている。ざっと紹介したい。 (C)日本テレビ
(C)日本テレビ (C)日本テレビ
(C)日本テレビ
レースクイーン「守田奈緒子」(TV番組アシスタントとしても出演。レースクイーン界では有名だった模様)が、家庭的な「カボチャの煮つけ」を作ったり… (C)日本テレビ
(C)日本テレビ (日本テレビ)
(日本テレビ)
グラビアアイドル「吉田忍」(テレ東の深夜番組「BIKINI」にも出演)が、手間暇かけて「チンゲン菜のクリーム煮」を披露したり… (C)日本テレビ
(C)日本テレビ (C)日本テレビ
(C)日本テレビ
やはり、新人アイドルと思しき「上野麻耶」(詳細不明)が、「特製カレーライス」をこしらえたり…
しかし、なぜこの3本だけが録画してあったのかは、正直言って、よく覚えていない。
(パチ・スロの関連情報が出てくる番組でもないし…)
ひょっとすると、仕事のストレスや、パチ・スロでの手痛い敗戦でなかなか寝つけない時、このテの映像に「癒し」を求めたのかもしれない。
(番組では、シャワーシーンや生写真プレゼントといった、「視聴者サービス」も多かったな…)
ともかくも、20年近く経った今となっては、貴重な「映像資料」といえよう。
そういえば、この番組では、コーナーの合間に、ちょいちょい「音楽情報」を挟んでいた。 (C)日本テレビ
(C)日本テレビ
「教えて!美音子(みねこ)さん!!」というタイトルの、音楽情報コーナー。 (C)日本テレビ
(C)日本テレビ
「鳥羽美音子」(とば・みねこ)という女性MCが、最新の洋楽・邦楽の情報をピックアップして、映像と共に紹介。なお、彼女は、MC、ナレーター、ジュエリーデザイナーとして、今も活躍中とのこと。
(彼女のコーナー担当は「2000年3月」まで。その後、「川村ひかる」がMCを引き継いだ)
それと、アイドルが料理を作っている間、別枠の画面(ワイプ)では、新進気鋭のミュージシャン等のPV(プロモーション映像)が流れる事が多かった。
当時、まだ新人だった女性ボーカルグループ「SPEED」のデビュー曲、「BODY&SOUL」のカッコいいPVを初めて目にしたのも、この番組だった事を思い出す。
その後も、「寝ドキッ!!」では、SPEEDの新曲PVを頻繁に紹介した筈だ。それと並行するように、彼女達はメジャーの階段をグイグイと駆け上っていった。
そんな訳で、今回は、全くパチ・スロと無関係な話題に終始した。まぁ、私自身の「備忘録」であると同時に、「90年代」という時代そのものを懐かしむ、当ブログの趣旨にも合致するから、問題はないハズだ。少なくとも、推定33名(笑)の「需要」には、応えられたのではないか。